|
차
례
|
|
■
법률단어정리
|
|
■
독해문장에
자주나오는 부언, 요약,강조, 설명, 부사어
|
|
■ 裁判(さいばん)傍聴(ぼうちょう)用語(ようご)集(しゅう)(재판방청용어집)
|
■ 법률사무소의 개요, 특징, 활동범위, 대상
|
| ■ 企業(きぎょう)法務(ほうむ) 活動(かつどう)分野(ぶんや)
(기업법무활동분야)
|
|
■
裁判所(さいばんしょ)の組織(そしき)(재판소의 조직)
|
|
1 概要(がいよう)
2 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)
3 下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)
(1) 高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
(2) 地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
(3) 家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)
(4) 簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
|
|
■
民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)(민사소송법
1조~6조)
|
|
■
第1 民事(みんじ)訴訟(そしょう)とその手続(てつづき)
(민사소송절차)
|
|
|
1 民事(みんじ)訴訟(そしょう)の種類(しゅるい)
(1) 通常(つうじょう)訴訟(そしょう)
(2) 手形(てがた)小切手(こぎって)訴訟(そしょう)
(3) 少額(しょうがく)訴訟(そしょう)
(4) その他(ほか)
2 民事(みんじ)訴訟(そしょう)の審理(しんり)手続(てつづき)
(1) 手続(てつづき)の開始(かいし) -訴(うった)えの提起(ていき)
ア 訴(うった)えの提起(ていき)
イ 管轄(かんかつ)
(2) 口頭(こうとう)弁論(べんろん)等(など)
ア 訴状(そじょう)の審査(しんさ)等
イ 口頭(こうとう)弁論(べんろん)
ウ 争点(そうてん)及(およ)び証拠(しょうこ)の整理(せいり)手続(てつづき)
エ 証拠(しょうこ)調(しら)べ
オ 口頭(こうとう)弁論(べんろん)調書(ちょうしょ)
(3) 訴訟(そしょう)の終了(しゅうりょう)
(4) 判決(はんけつ)に対(たい)する上訴(じょうそ) -控訴(こうそ)と上告(じょうこく)
3 訴訟(そしょう)費用(ひよう)及(およ)びその補助(ほじょ)
(1) 訴訟(そしょう)費用(ひよう)の負担(ふたん)
(2) 補助(ほじょ)の種類(しゅるい)
|
|
■
第2その他(ほか)の民事(みんじ)事件(じけん)とその手続(てつづき)
(그외 민사소송과 절차)
|
|
|
1 民事(みんじ)執行(しっこう)手続(てつづき)
(1) 強制(きょうせい)執行(しっこう)手続(てつづき)と担保(たんぽ)権(けん)の実行(じっこう)としての競売(きょうばい)手続(てつづき)
(2) 不動産(ふどうさん)執行(しっこう)手続(てつづき)と債権(さいけん)執行(しっこう)手続(てつづき)
2 倒産(とうさん)手続(てつづき)
(1) 破産(はさん)手続(てつづき)について
(2) 民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)について
ア 通常(つうじょう)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)
イ 個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)
|
|
■
第3 近時の民事訴訟の状況と問題
(최근 민사소송의 상황과 문제)
|
| ■ 意見書(いけんしょ,
의견서)
|
|
|
1.貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)施行(しこう)規則(きそく)17条(じょう)1項(こう)の改正(かいせい)について
2.「金融(きんゆう)審議(しんぎ)会(かい)金融(きんゆう)分科(ぶんか)会(かい)第(だい)一(いち)部会(ぶかい)の「投資(とうし)サービス法(ほう)」制定(せいてい)に関(かん)する中間(ちゅうかん)整理(せいり)に対(たい)する意見(いけん)書(しょ)」
3.「消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)の在(あ)り方(かた)について」に対(たい)する意見(いけん)書(しょ)
|
| ■
最近の主な最高裁判決(최근 주된 최고재판결)1.
|
|
■
最近の主な最高裁判決(최근 주된 최고재판결)2.
|
|
|
|
最高(さいこう)裁判所(さいばんしょ):최고 재판소
下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ):하급재판소
地方(ちほう)裁判所(さいばんしょ):지방재판소
家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ);가정재판소
簡易(かんい)裁判所(さいばんしょ):간이재판소
裁判(さいばん):재판
裁判権(さいばんけん):재판권
裁判官(さいばんかん):재판관
判事(はんじ):판사
判決(はんけつ);판결
判例(はんれい):판례
平成(へいせい):평성
第(だい)643号(ごう):제 643호
113条(じょう)による改正(かいせい):
113조에 의한 개정
平成(へいせい)12年(ねん)4月(がつ)1日(にち)施行(しこう):평성4월1일 시행
要旨(ようし):요지
理由(りゆう);이유
内容(ないよう):내용
件名(けんめい):건명
主文(しゅぶん):주문
破棄(はき):파기
棄却(ききゃく):기각
法(ほう):법
違法(いほう):위법
憲法(けんぽう):헌법
法律(ほうりつ):법률
法規(ほうき):법규
法務省(ほうむしょう);법무성
法文(ほうぶん):법문
法案(ほうあん):법안
法人(ほうじん):법인
法典(ほうてん):법전
法廷(ほうてい):법정
法令(ほうれい):법령
民法(みんぽう):민법
立法府(りっぽうふ):입법부
司法(しほう):사법
国家(こっか)賠償法(ばいしょうほう):국가배상법
検事(けんじ):검사
検事(けんじ)からの回答(かいとう):검사로부터의 회답
検察(けんさつ):검찰
検察官(けんさつかん):검찰관
検察庁(けんさつちょう):검찰청
証(あかし):증거, 증명
証(しょう)する;증거하다
証拠(しょうこ)調(しら)べ:증거조사
~容疑(ようぎ)で再(さい)逮捕(たいほ):
~용의로 다시 체포
証言(しょうげん):증언
証人(しょうにん):증인
弁護士(べんごし):변호사
弁護士(べんごし)会(かい):번호사회
国選(こくせん)弁護人(べんごにん):국선변호인
弁護士(べんごし)に事件(じけん)を依頼(いらい):
변호사에게 사건을 의뢰
原告(げんこく):원고
被告(ひこく):피고
疑問(ぎもん):의문
口頭(こうとう)弁論(べんろん);구두변론)
接見(せっけん);접견
接見(せっけん)を申(もう)し入(い)れる:접견의 제기하다
申(もう)し出(で):신청, 의사표시
接見指定(せっけんしてい):접견지정
面会(めんかい):면회
選任(せんにん):선임
法律相談(ほうりつそうだん):법률상담
問題(もんだい)を解決(かいけつ)するための窓口(まどくち):문제해결을 위한창구
金銭(きんせん)トラブル:금전트러불
交通(こうつう)事故(じこ):교통사고
不動産(ふどうさん)売買(ばいばい):부동산매매
医療(いりょう)問題(もんだい):의료문제
労働(ろうどう)問題(もんだい):노동문제
暴力(ぼうりょく)問題(もんだい);폭력문제
離婚(りこん)問題(もんだい):이혼문제
家庭問題(かていもんだい):가정문제
専門的(せんもんてき)に対応(たいおう):전문적으로 대응
事件(じけん)処理(しょり):사건처리
法律(ほうりつ)事務所(じむしょ):법률사무소
長官(ちょうかん):장관
上告(じょうこく):상고
飛躍上告(ひやくじょうこく):비약상고
特別(とくべつ)上告(じょうこく):특별상고
上告審(じょうこくしん):상고심
抗告(こうこく):항고
第一(だいいち)審(しん):제일심
第(だい)に審(しん):제 2심
終審(しゅうしん):종심
事件(じけん):사건
解釈(かいしゃく):해석
事項(じこう):사항
手続(てつづ)き違反(いはん);절차위반
確定(かくてい)判決(はんけつ):확정판결
事由(じゆう):사유
行政(ぎょうせい)事件(じけん):행정사건
独立(どくりつ):독립
|
刑事(けいじ):형사
民事(みんじ):민사
民事(みんじ)訴訟(そしょう)とその手続(てつづ)き:민사소송의 절차
民事訴訟の種類(しゅるい):민사소송의 종류
民事訴訟の審理(しんり)手続(てつづ)き:민사소송심리절차
民事(みんじ)執行(しっこう)手続(てつづ)き:민사집행절차
原判決(げんはんけつ):원판결
審理(しんり):심리
規則(きそく):규칙
制定(せいてい):제정
許可(きょか):허가
任命(にんめい);임명
審決(しんけつ):심결
非公開(ひこうかい):비공개
控訴(こうそ):공소
訴訟(そしょう);소송
通常(つうじょう)訴訟(そしょう):통상소송
訴訟(そしょう)費用(ひよう):소송비용
少額(しょうがく)訴訟(そしょう):소액소송
手形(てがた)小切手(こぎって)訴訟(そしょう):어음수표소송
訴願(そがん):소원
訴状(そじょう):소장
訴追(そつい):소추
関与(かんよ):관여
権利(けんり):권리
権限(けんげん):권한
権益(けんえき):권익
被疑者(ひぎしゃ):피의자
被害者(ひがいしゃ):피해자
上告(じょうこく)代理人(だいりにん):상고대리인
取(と)り調(しら)べ:취조하다, 조사하다
拒否(きょひ):거부
罪(つみ):죄
刑事裁判(けいじさいばん):형사재판
双方(そうほう)の言(い)い分(ぶん):쌍방의 주장, 변명, 말할거리
立証(りっしょう):입증
処罰(しょばつ):처벌
警察(けいさつ)に逮捕(たいほ)された場合(ばあい):경찰에 체포된 경우
犯人(はんにん):범인
犯人(はんにん)を捜(さが)す:범인을 찾다
犯罪(はんざい)を犯(おか)す:범죄를 저지르다
公正(こうせい)な裁判(さいばん):공정한 재판
捜査(そうさ):수사
捜索(そうさく):수색
事件(じけん):사건
無罪(むざい)釈放(しゃくほう):무재석방
無罪(むざい)になる:무죄가 되다
有罪(ゆうざい)判決(はんけつ):유재판결
起訴(きそ):기소
提起(ていき):제기
争点(そうてん):쟁점
整理(せいり):정리
強制(きょうせい)執行(しっこう):강제집행
担保権(たんぽけん)の実行(じっこう):담보권의 집행
訴訟費用(そしょうひよう)及びその補助(ほじょ):소송비용 및 그 보조
担保権(たんぽけん)の実行(じっこう)としての競売(けいばい)手続(てつづ)き:
담보권집행의로서의 경매절차
不動産(ふどうさん)執行(しっこう)手続(てつづ)き:부동산집행절차
倒産(とうさん)手続(てつづ)き:도산절차
破産(はさん)手続(てつづ)き:파산절차
個人(こじん)債務者(さいむしゃ):개인채무자
民事訴訟(みんじそしょう)の状況(じょうきょう)と問題(もんだい):민사소송의 상황과 문제
慰謝料(いしゃりょう)請求(せいきゅう):위자료청구
事実関係(じじつかんけい):사실관계
本件(ほんけん):본건
異議(いぎ)を述(の)べる:이의를 서술하다
変更(へんこう):변경
改正(かいせい):개정
法律(ほうりつ)の施行(しこう)に伴(ともな)う:법률시행에 동반된다
関係(かんけい)法律(ほうりつ)の設備(せつび):관계법률의 정비
送達(そうたつ):송달
広報(こうほう):공보
公布(こうふ):공포
決定書(けっていしょ):결정서
命令書(めいれいしょ):명령서
書面(しょめん):서면
記名(きめい):기명
決定(けってい)又(また)は命令(めいれい)の告知(こくち):결정 또는 명령의 공지
裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん):재판소 서기관
方法(ほうほう):방법
規定(きてい)を準用(じゅんよう)する:규정을 준용하다
予告(よこく)通知(つうち):예고통지
紛争(ふんそう)の要点(ようてん)を記載(きさい)する:분쟁의 요점을 기재하다
事項(じこう):사항
具体的(ぐたいてき)に記載(きさい):구체적으로 기재
相手(あいて)に送付(そうふ)する:상대에게 송부하다
|
|
|
● なお: 추가하여, 첨언을 할 때 사용 、또한
14日 テストをします. なお, テストの 範囲(はんい)については 明日 お知らせします
(14일 테스트를 합니다, 또한 시험범위에 관해서는 내일 알려드리겠습니다)
● ただし: 단/ 다만, 단서가 붙음, 조건부
この 映画(えいが)は 20日 公開(こうかい)される, ただし 成人(せいじん)向(む)けです
(이 영화는 20일 공개됩니다, 단 성인용입니다)
● ただ: 단 , ∼에 ∼을 보충하는 설명
彼女は 性格が 明(あか)るい, ただ 一面 そそっかしいです
(그녀는 성격이 명랑하다, 단 일면, 덜렁, 경솔합니다)
● および: 및
工場内(こうじょうない)は カメラ および ビデオ 撮影(さつえい)は 禁止(きんし)です
(공장내에서는 카메라 및 비데오의 촬영이 금지입니다)
● すなわち: 즉
日本の首都(しゅと)は すなわち 東京は アジア最大(さいだい)の 都市です
(일본의 수도 즉 동경은 아시아 최대의 도시입니다)
● いわゆる: 소위, 이른바
これが いわゆる 民主主義(みんしゅしゅぎ)の 原理(げんり)だ
(이것이 소위 민주주의의 원리다)
● 一方: 한편
彼は 銀行につとめる 一方で 作曲家としても 活動(かつどう)している
(그는 은행에 근무하는 한편 작곡가로써도 활동하고 있습니다)
● ゆえに: 고로
Aは Bより 大きい, Bは Cより 大きい, ゆえに Aは Cより 大きい
(A는B보다 크다,B는 C보다 크다, 고로 A는 C보다 크다)
● 要(よう)するに: 결국/ 요점만을 설명하면
あなたが 言いたいのは, 要するに お金(かね)が ほしいと言うことですね
(당신이 말하고 싶은 것은 결국 돈이 필요하다는 것이군요)
● とりわけ: 그중에서도 특히
最近, 人気(にんき)が ある 本は 小説(しょうせつ), とりわけ 推理(すいり)小說です
(최근 인기가 있는 책은 소설, 그중에서도 특히 추리소설입니다)
● 一槪(いちがい)に: 일률적으로
全面的な 調査(ちょうさ)が いい ことだと一槪(いちがい)に 言えない
(전면적인 조사가 좋다고는 일률적으로 말할 수 없다)
● または: 혹은
授業料は 銀行 または 郵便局(ゆうびんきょく)で はらってください
(수업료는 은행 또는 우체국에 지불해 주세요)
● また: 또한, 게다가
彼は 有明な 政治家(せいじか)で あるとともに また すぐれた 作家(さっか)である
(그는 유명한 정치가이기도 하고 또한 휼룡한 작가이다)
● それとも: 혹은, (=あるいは, もしくは)
山に 行こうか, それとも 海に 行こうか
(산에 갈가, 혹은 바다에 갈까)
● 取(と)り敢(あ)えず: 우선
時間が ないので とりあえず 用件(ようけん)だけ 話して すぐ 帰(かえ)った
(시간이 없기 때문에 우선 용건만을 말하고 바로 돌아갔다)
●若(も)しくは:혹은
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)若(も)しくは家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)
(지방재판소
혹은(내지) 가정재판소
|
 裁判(さいばん)傍聴(ぼうちょう)用語(ようご)集(しゅう)(재판방청용어집) 裁判(さいばん)傍聴(ぼうちょう)用語(ようご)集(しゅう)(재판방청용어집) 
裁判(さいばん)を傍聴(ぼうちょう)する上(うえ)で知(し)っていたほうがいい言葉(ことば)や、このホームページをご利用(りよう)いただく上(うえ)でどうしても使(つか)わなければならなかった法律(ほうりつ)用語(ようご)があります。
それについてここで解説(かいせつ)していきます。かなり小(ちい)さな法律(ほうりつ)用語(ようご)辞典(じてん)」だと思(おも)ってください。もし明(あき)らかに違(ちが)うことが書(か)いてあったら、
ご指摘(してき)いただければ嬉(うれ)しいです。
科料(かりょう)
禁錮(きんこ)
刑事(けいじ)裁判(さいばん)
起訴(きそ)
原告(げんこく)
検察官(けんさつかん)
控訴(こうそ)
勾留(こうりゅう)
拘留(こうりゅう)
死刑(しけい)
執行(しっこう)猶予(ゆうよ)
主(しゅ)尋問(じんもん)
上告(じょうこく)
懲役(ちょうえき)
罰金(ばっきん)
反対(はんたい)尋問(じんもん)
被疑(ひぎ)者(しゃ)
被告(ひこく)
被告(ひこく)人(じん)
民事(みんじ)裁判(さいばん)
疑(うたが)わしきは被告(ひこく)人(じん)の有利(ゆうり)に
|
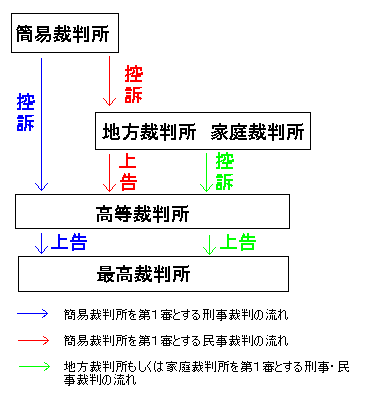 |
刑事(けいじ)裁判(さいばん)・民事(みんじ)裁判(さいばん)
裁判(さいばん)には大(おお)きく分(わ)けて2種類(しゅるい)ある。刑事(けいじ)裁判(さいばん)と民事(みんじ)裁判(さいばん)だ。刑事(けいじ)裁判(さいばん)では、「刑罰(けいばつ)を受(う)けるに値(あたい)するだけの犯罪(はんざい)」を犯(おか)した疑(うたが)いがある人(ひと)が裁(さば)かれる。
懲役(ちょうえき)○年(ねん)・科料(かりょう)などの有罪(ゆうざい)になるか、無罪(むざい)になるかの2つの結果(けっか)が出(で)てくる。
フジテレビ系(けい)で放送(ほうそう)中(ちゅう)の謎(なぞ)の番組(ばんぐみ)「ザ・ジャッジ」で「これって罪(つみ)じゃないの」みたいなことを扱(あつか)われているが、「罪(つみ)になる」というのはまさに「刑事(けいじ)裁判(さいばん)にかけられる可能(かのう)性(せい)がある」ということになる。
たまに勘違(かんちが)いしている人(ひと)がいるのだが、「これは犯罪(はんざい)ではない」といわれたものに「ああ、これはやってもいいんだ」と言(い)い出(だ)す。おまわりさんにつかまらないってだけで、相手(あいて)が受(う)けた損害(そんがい)に対(たい)する責任(せきにん)はある。
その責任(せきにん)をはっきりさせるのが民事(みんじ)裁判(さいばん)。いわば個人(こじん)と個人(こじん)が争(あらそ)う。これに出(で)てくるのは犯罪(はんざい)者(しゃ)ではなく、「貸(か)した金(かね)返(かえ)せ!」や「弁償(べんしょう)しろ!」などの話(はなし)。
個人(こじん)と個人(こじん)が出(で)てくるからって当事者(とうじしゃ)同士(どうし)が言(い)い合(あ)って判決(はんけつ)が出(で)るのではない。大抵(たいてい)の民事(みんじ)裁判(さいばん)には当事者(とうじしゃ)は出席(しゅっせき)せず、弁護士(べんごし)がなにやら書類(しょるい)を提出(ていしゅつ)して終(お)わってしまう。ドラマのように弁護士(べんごし)同士(どうし)が法廷(ほうてい)でもめるのはまれ。
だから あまりおもしろくない。初(はじ)めて裁判(さいばん)を傍聴(ぼうちょう)に行(い)くなら刑事(けいじ)裁判(さいばん)の方(ほう)がいい。
ある程度(ていど)中身(なかみ)のわかる民事(みんじ)裁判(さいばん)を見(み)たければ、証人(しょうにん)が出(で)てくる裁判(さいばん)を見(み)たほうがいい。
執行(しっこう)猶予(ゆうよ)
ある一定(いってい)の期間(きかん)その刑(けい)の執行(しっこう)を猶予(ゆうよ)するということ。
「懲役(ちょうえき)1年(ねん)執行(しっこう)猶予(ゆうよ)4年(ねん)」というと、4年間(ねんかん)悪(わる)いことをしなかったら1年(ねん)の懲役(ちょうえき)にはならないということ。つまり刑務所(けいむしょ)に入(はい)らなくていい。
しかし勘違(かんちが)いしてはいけない。立派(りっぱ)な有罪(ゆうざい)判決(はんけつ)です。犯罪(はんざい)者(しゃ)です。社会(しゃかい)生活(せいかつ)でも「執行(しっこう)猶予(ゆうよ)中(ちゅう)」ということでさまざまな不利益(ふりえき)がある。
被告(ひこく)・原告(げんこく)
被告(ひこく)は民事(みんじ)裁判(さいばん)で訴(うった)えられた人(ひと)。別(べつ)に悪(わる)い側(がわ)というわけではなく、民事(みんじ)裁判(さいばん)で訴(うった)えた側(がわ)が原告(げんこく)となり訴(うった)えられた側(がわ)が被告(ひこく)となる。
たとえば あなたがAくんに貸(か)した金(かね)を返(かえ)してほしい。しかし Aくんは返(かえ)してくれない。そのことであなたがAくんに貸(か)した金(かね)を返(かえ)すことを求(もと)め民事(みんじ)裁判(さいばん)を起(お)こす。
この場合(ばあい)あなたが原告(げんこく)でAくんが被告(ひこく)。
また、あなたが借(か)りてもいないお金(かね)をB会社(かいしゃ)が「返(かえ)せ」と言(い)ってきた。B会社(かいしゃ)はあなたにお金(かね)を返(かえ)すように民事(みんじ)裁判(さいばん)を起(お)こした。
この場合(ばあい)、原告(げんこく)がB会社(かいしゃ)で被告(ひこく)はあなた。
原告(げんこく)が正義(せいぎ)で被告(ひこく)が悪(あく)というわけではない。
被疑(ひぎ)者(しゃ)
犯罪(はんざい)の疑(うたが)いをかけられた人(ひと)。捜査(そうさ)が始(はじ)まった段階(だんかい)で被疑(ひぎ)者(しゃ)と呼(よ)ばれる。
検察官(けんさつかん)が起訴(きそ)するまで被疑(ひぎ)者(しゃ)と呼(よ)ばれ、起訴(きそ)されるとめでたく被告(ひこく)人(じん)と呼(よ)ばれる。
被告(ひこく)人(じん)
刑事(けいじ)裁判(さいばん)で犯罪(はんざい)を犯(おか)した疑(うたが)いをかけられている人(ひと)。起訴(きそ)されるまでは被疑(ひぎ)者(しゃ)とよばれ、起訴(きそ)されると被告(ひこく)人(じん)になる。刑事(けいじ)裁判(さいばん)ではこの人(ひと)が主人公(しゅじんこう)。
検察官(けんさつかん)
刑事(けいじ)裁判(さいばん)でやたらと被告(ひこく)人(じん)をいじめる人(ひと)。
被告(ひこく)人(じん)を有罪(ゆうざい)に導(みちび)く正義(せいぎ)の味方(みかた)?
とにかく被告(ひこく)人(じん)にとっては嫌(いや)な奴(やつ)なのだ。
その正体(しょうたい)は弁護士(べんごし)や裁判官(さいばんかん)と同(おな)じように司法(しほう)試験(しけん)に合格(ごうかく)した法律(ほうりつ)に詳(くわ)しいお人(ひと)。
刑事(けいじ)裁判(さいばん)では被告(ひこく)人(じん)と弁護(べんご)人(じん)の敵(てき)になり、
バンバン刑(けい)が重(おも)くなるように攻撃(こうげき)してくる。
法廷(ほうてい)では検察官(けんさつかん)はこのような仕事(しごと)をしているが、おまわりさんに捕(つか)まった後に被疑(ひぎ)者(しゃ)はこの人(ひと)たちのもとに送(おく)られてくる。検察官(けんさつかん)も証拠(しょうこ)調(しら)べなどの捜査(そうさ)をするのだ。捜査(そうさ)の結果(けっか)、裁判(さいばん)にかけることを決(き)めることができるのは検察官(けんさつかん)だけ。
捜査(そうさ)の結果(けっか)、犯罪(はんざい)の内容(ないよう)・周囲(しゅうい)の状況(じょうきょう)などを判断(はんだん)して、(本当(ほんとう)は悪(わる)いことをしたはずの)被疑(ひぎ)者(しゃ)を釈放(しゃくほう)する権限(けんげん)を持(も)っているのも検察官(けんさつかん)だ。
疑(うたが)わしきは被告(ひこく)人(じん)に有利(ゆうり)に
別(べつ)に裁判所(さいばんしょ)で出(で)てくる用語(ようご)と言(い)うわけではないが、これは知(し)っていて欲(ほ)しい。刑事(けいじ)裁判(さいばん)で必要(ひつよう)となる知識(ちしき)だが、たとえ被告(ひこく)人(じん)が極悪(ごくあく)人(じん)で被告(ひこく)人(じん)本人(ほんにん)も悪(わる)いことをしたと言(い)っていても、実際(じっさい)に悪(わる)いことをしたとしても、
その悪(わる)いことをした人(ひと)が被告(ひこく)人(じん)であるという証拠(しょうこ)がしっかりそろっていないとその悪(わる)いことはしなかったこととして扱(あつか)われる。これは何(なに)も悪(わる)いことをしていない人(ひと)が間違(まちが)えて刑務所(けいむしょ)に送(おく)られる(冤罪(えんざい)という)のを防(ふせ)ぐ目的(もくてき)がある。
冤罪(えんざい)を防(ふせ)ぐためならたとえ悪(わる)いことをした人(ひと)が無罪(むざい)放免(ほうめん)されても仕方(しかた)がないのだ。
簡単(かんたん)にいうと「ばれなきゃいい」ってこと。
死刑(しけい)・懲役(ちょうえき)・禁錮(きんこ)・拘留(こうりゅう)・罰金(ばっきん)・科料(かりょう)
日本での刑罰(けいばつ)。有罪(ゆうざい)となった被告(ひこく)人(じん)はいずれかの刑罰(けいばつ)を受(う)ける。 死刑(しけい) 絞首(こうしゅ)によって命(いのち)を奪(うば)われる。
日本での最高(さいこう)刑(けい)。この場合(ばあい)は死刑(しけい)そのものが刑罰(けいばつ)なので、執行(しっこう)されるまでは拘置(こうち)所(しょ)に入(い)れられる。懲役(ちょうえき)刑(けい)を受(う)けると所定(しょてい)の作業(さぎょう)をしなければならない。
懲役(ちょうえき)・禁錮(きんこ) 懲役(ちょうえき)は刑務所(けいむしょ)で所定(しょてい)の作業(さぎょう)をさせられる刑罰(けいばつ)。禁錮(きんこ)は所定(しょてい)の作業(さぎょう)がない。期間(きかん)は1ヵ月(かげつ)以上(いじょう)15年(ねん)以下(いか)が原則(げんそく)。無期(むき)の場合(ばあい)もある。
拘留(こうりゅう) 1日(にち)以上(いじょう)30日(にち)未満(みまん)拘置(こうち)所(しょ)にいなければならない。自由(じゆう)を拘束(こうそく)する刑罰(けいばつ)なので、懲役(ちょうえき)・禁錮(きんこ)と並(なら)んで「自由(じゆう)刑(けい)」といわれている。懲役(ちょうえき)のように所定(しょてい)の作業(さぎょう)はしない。
罰金(ばっきん)・科料(かりょう) 財産(ざいさん)を奪(うば)われる。罰金(ばっきん)と科料(かりょう)の違(ちが)いは金額(きんがく)で科料(かりょう)は1万(まん)円(えん)未満(みまん)。罰金(ばっきん)は1万(まん)円(えん)以上(いじょう)。
限度(げんど)は犯罪(はんざい)ごとに定(さだ)められている(たとえば刑法(けいほう)174条(じょう):公然(こうぜん)とわいせつな行為(こうい)をした者(もの)は、六月(ろくがつ)以下(いか)の懲役(ちょうえき)もしくは30万(まん)円(えん)以下(いか)の罰金(ばっきん)又(また)は拘留(こうりゅう)もしくは科料(かりょう)に処(しょ)する)。
勘違(かんちが)いしてはいけないのは、コレは刑罰(けいばつ)であるためこのお金(かね)は被害(ひがい)者(しゃ)に支払(しはら)われるものではない。
また「交通(こうつう)違反(いはん)で罰金(ばっきん)を取(と)られた」という人(ひと)がいるが、ほとんどの場合(ばあい)コレは間違(まちが)いで、交通(こうつう)違反(いはん)で警察(けいさつ)に納(おさ)めるのは罰金(ばっきん)ではなく過料(かりょう)である。
これは「危(あぶ)ないから悪(わる)いことするなよ」っていう制裁(せいさい)で、刑罰(けいばつ)ではない。だからもちろん前科(ぜんか)はつかないよね。
勾留(こうりゅう)
処分(しょぶん)が決(き)まっていない被疑(ひぎ)者(しゃ)もしくは被告(ひこく)人(じん)の身柄(みがら)を確保(かくほ)しておくこと。処分(しょぶん)が決(き)まっていないので当然(とうぜん)犯罪(はんざい)者(しゃ)ではない。逃亡(とうぼう)の恐(おそ)れや証拠(しょうこ)隠(かく)しの恐(おそ)れがある場合(ばあい)にできる。
刑罰(けいばつ)である拘留(こうりゅう)とは異(こと)なるので注意(ちゅうい)。
控訴(こうそ)・上告(じょうこく)
判決(はんけつ)に不服(ふふく)がある場合(ばあい)、上級(じょうきゅう)の裁判所(さいばんしょ)でもう一度(いちど)裁判(さいばん)を請求(せいきゅう)することができる。
裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)は3回(かい)まで。
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)で不服(ふふく)な場合(ばあい)は高等裁判所(こうとうさいばんしょ)に(これを控訴(こうそ)という)。高等裁判所(こうとうさいばんしょ)で不服(ふふく)な場合(ばあい)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)で裁判(さいばん)がおこなわれる(これを上告(じょうこく)という)。 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)で出(で)た判決(はんけつ)で確定(かくてい)となる。
しかし、裁判所(さいばんしょ)は忙(いそが)しい。
控訴(こうそ)・上告(じょうこく)した場合(ばあい)は、以前(いぜん)の裁判(さいばん)で述(の)べた発言(はつげん)と同(おな)じ発言(はつげん)は繰(く)り返(かえ)せない。
また、上告(じょうこく)をするためには、定(さだ)められた上告(じょうこく)理由(りゆう)がなければ認(みと)められない。たとえば、2回(かい)目(め)の裁判(さいばん)で決定(けってい)された事実(じじつ)関係(かんけい)が間違(まちが)っているという理由(りゆう)で上告(じょうこく)することは認(みと)められない。
上級(じょうきゅう)の裁判所(さいばんしょ)が前(まえ)の判決(はんけつ)と異(こと)なった判決(はんけつ)を出(だ)した場合(ばあい)、前(まえ)の判決(はんけつ)は無効(むこう)になる。
刑事(けいじ)裁判(さいばん)の場合(ばあい)、罪(つみ)が軽(かる)すぎる(もしくは無罪(むざい))だと思(おも)ったら検察官(けんさつかん)が控訴(こうそ)・上告(じょうこく)する。
被告(ひこく)人(じん)(弁護(べんご)人(じん))は無罪(むざい)の判決(はんけつ)が出(で)た場合(ばあい)、判決(はんけつ)の理由(りゆう)がどうであっても控訴(こうそ)・上告(じょうこく)することはできない。
起訴(きそ)
犯罪(はんざい)の疑(うたが)いが十分(じゅうぶん)に固(かた)まったので、裁判所(さいばんしょ)に裁判(さいばん)を始(はじ)めるようにお願(ねが)いすること。日本で起訴(きそ)することができるのは検察官(けんさつかん)だけ。
主(しゅ)尋問(じんもん)・反対(はんたい)尋問(じんもん)
証人(しょうにん)に対(たい)して裁判(さいばん)の証拠(しょうこ)となるようなことを質問(しつもん)すること。主(しゅ)尋問(じんもん)は証人(しょうにん)を請求(せいきゅう)した側(そく)がする質問(しつもん)。反対(はんたい)尋問(じんもん)はもう一方(いっぽう)の当事者(とうじしゃ)がする質問(しつもん)。
刑事(けいじ)裁判(さいばん)では検察官(けんさつかん)と被告(ひこく)人(じん)(弁護(べんご)人(じん))の争(あらそ)いになるので、検察官(けんさつかん)が請求(せいきゅう)した証人(しょうにん)にたいしては、検察官(けんさつかん)が主(しゅ)尋問(じんもん)で弁護(べんご)人(じん)が反対(はんたい)尋問(じんもん)をすることになる。
概要(がいよう)と特徴(とくちょう):活動(かつどう)の範囲(はんい)・対象(たいしょう)
設立(せつりつ)以来(いらい)、法人(ほうじん)、個人(こじん)からのあらゆる法的(ほうてき)な相談(そうだん)、事件(じけん)依頼(いらい)にお応(こた)えしたいという気持(きも)ちをモットーとして、それぞれのご依頼(いらい)者(しゃ)が望(のぞ)まれ、
必要(ひつよう)とされる法(ほう)分野(ぶんや)に対応(たいおう)させていただくことを基本(きほん)に、各(かく)法(ほう)分野(ぶんや)における知識(ちしき)と実務(じつむ)的(てき)な対応(たいおう)能力(のうりょく)の向上(こうじょう)に努(つと)めてまいりました。
大阪(おおさか)をはじめ関西(かんさい)地域(ちいき)は、歴史(れきし)的(てき)に古(ふる)くから各種(かくしゅ)製造(せいぞう)業(ぎょう)および商業(しょうぎょう)が活発(かっぱつ)で、活動(かつどう)範囲(はんい)も国際(こくさい)化(か)の進展(しんてん)にあわせてアメリカ、ヨーロッパ、
さらに近時(きんじ)はアジア諸国(しょこく)、とりわけ中国(ちゅうごく)へと拡大(かくだい)していきました。このような人(ひと)・物(もの)の流(なが)れとともに次々(つぎつぎ)と新(あたら)しい法律(ほうりつ)問題(もんだい)も経済(けいざい)活動(かつどう)から派生(はせい)し、
対応(たいおう)も事後(じご)的(てき)な解決(かいけつ)方法(ほうほう)から未然(みぜん)的(てき)防止(ぼうし)的(てき)な措置(そち)が要請(ようせい)されるようになりました。
当(とう)事務所(じむしょ)では、このような認識(にんしき)に立(た)って設立(せつりつ)当初(とうしょ)から国内(こくない)における法律(ほうりつ)問題(もんだい)のみならず、
国際(こくさい)的(てき)な法律(ほうりつ)問題(もんだい)、いわゆる渉外(しょうがい)業務(ぎょうむ)についてもさまざまなご依頼(いらい)にも応(こた)えられるよう積極(せっきょく)的(てき)に取(と)り組(く)んでまいりました。
今日(きょう)、世界(せかい)的(てき)視野(しや)で行(おこな)われている事業(じぎょう)・組織(そしき)の再編(さいへん)をはじめ、日(にち)米(べい)欧(おう)にまたがる独禁法(どっきんほう)を中心(ちゅうしん)とした経済(けいざい)法(ほう)関連(かんれん)の法律(ほうりつ)問題(もんだい)などが日常(にちじょう)的(てき)かつ広範囲(こうはんい)に生(しょう)じることとなり、
グローバルな活動(かつどう)を行(おこな)う企業(きぎょう)にとって、日本(にっぽん)と海外(かいがい)で同時(どうじ)発生(はっせい)する法的(ほうてき)課題(かだい)への統一(とういつ)的(てき)かつ迅速(じんそく)な解決(かいけつ)が求(もと)められています。
このようなニーズにお応(こた)えするために、初期(しょき)の段階(だんかい)から多(おお)くの弁護士(べんごし)をアメリカ、ヨーロッパ さらには中国(ちゅうごく)に研鑚(けんさん)のため留学生(りゅうがくせい)として派遣(はけん)するとともに、
外国(がいこく)法(ほう)有(ゆう)資格(しかく)者(しゃ)の研修生(けんしゅうせい)や外国(がいこく)法(ほう)事務(じむ)弁護士(べんごし)を受(う)け入(い)れるほか、
南米(なんべい)、アフリカを含(ふく)む世界(せかい)主要(しゅよう)地域(ちいき)の法律(ほうりつ)事務所(じむしょ)との不断(ふだん)の交流(こうりゅう)を通(つう)じて、
地球(ちきゅう)上(じょう)のいかなる国(くに)・地域(ちいき)で発生(はっせい)する法的(ほうてき)な要請(ようせい)にも問題(もんだい)の性格(せいかく)に応(おう)じた機動(きどう)的(てき)な対応(たいおう)ができるようにネットワークの構築(こうちく)にも力(ちから)を入(い)れています。
現在(げんざい)まで製造(せいぞう)業(ぎょう)はもとより、情報(じょうほう)、通信(つうしん)、建設(けんせつ)、不動産(ふどうさん)、エネルギー、ソフトウェア、マスコミ・報道(ほうどう)、流通(りゅうつう)・商社(しょうしゃ)、テーマパーク、エンターテインメント等の第(だい)三(さん)次(じ)産業(さんぎょう)に所属(しょぞく)の民間(みんかん)企業(きぎょう)のほか、
地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)および関連(かんれん)団体(だんたい)など、規模(きぼ)の大小(だいしょう)に関係(かんけい)なくすべての業種(ぎょうしゅ)、分野(ぶんや)の企業(きぎょう)・団体(だんたい)からのご依頼(いらい)に応(こた)えてきました。
また、銀行(ぎんこう)等の金融(きんゆう)機関(きかん)をはじめ証券(しょうけん)、保険(ほけん)、投資(とうし)ファンド、ベンチャーキャピタリスト等の金融(きんゆう)関係(かんけい)機関(きかん)からのご依頼(いらい)にもお応(こた)えしております。
各(かく)分野(ぶんや)のさまざまな企業(きぎょう)・団体(だんたい)に対(たい)して、新規(しんき)ビジネスの法的(ほうてき)側面(そくめん)での関与(かんよ)のほか、
日常(にちじょう)活動(かつどう)に伴(ともな)う法的(ほうてき)リスクへの予防(よぼう)的(てき)な関与(かんよ)などの指導(しどう)・相談(そうだん)業務(ぎょうむ)や実際(じっさい)に紛争(ふんそう)が発生(はっせい)したときの裁判(さいばん)上(じょう)・裁判(さいばん)外(がい)での紛争(ふんそう)解決(かいけつ)など、
あらゆる段階(だんかい)において的確(てきかく)に対応(たいおう)できる弁護士(べんごし)を擁(よう)しています。
 ■ 企業(きぎょう)法務(ほうむ) 活動(かつどう)分野(ぶんや)
(기업법무활동분야) ■ 企業(きぎょう)法務(ほうむ) 活動(かつどう)分野(ぶんや)
(기업법무활동분야)
1.会社(かいしゃ)法(ほう)・ コンプライアンス
2.独占(どくせん)禁止(きんし)法(ほう)
3.企業(きぎょう)再編(さいへん)・M&A
4.ベンチャー・ファイナンス
5.企業(きぎょう)再生(さいせい)・倒産(とうさん)法(ほう)
6.知的(ちてき)財産(ざいさん)権(けん)法(ほう)
7.IT、インターネット、情報(じょうほう)通信(つうしん)
8.エンターテインメント法(ほう)
9.証券(しょうけん)・金融(きんゆう)・保険(ほけん)
10.行政(ぎょうせい)法(ほう)、行政(ぎょうせい)規制(きせい)法(ほう)
11. 税法(ぜいほう)
12.環境(かんきょう)法(ほう)
13.製造(せいぞう)物(ぶつ)責任(せきにん)法(ほう)
14. 労働(ろうどう)法(ほう)
15.訴訟(そしょう)、仲裁(ちゅうさい)、その他(ほか)紛争(ふんそう)解決(かいけつ)
16. 国際(こくさい)・国内(こくない)商取引(しょうとりひき)、
契約(けいやく)作成(さくせい)・交渉(こうしょう)
17. 国際(こくさい)取引(とりひき)規制(きせい) (International Trade Regulation)
18. 中国(ちゅうごく)業務(ぎょうむ)
19. 企業(きぎょう)刑事(けいじ)事件(じけん)
1 概要(がいよう)
2 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)
3 下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)
(1) 高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
(2) 地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
(3) 家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)
(4) 簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
1. 概要(がいよう)
(1) 裁判所(さいばんしょ)の審(しん)級(きゅう)制度(せいど)
我(わ)が国(くに)は,正(ただ)しい裁判(さいばん)を実現(じつげん)するために三(さん)審(しん)制度(せいど),すなわち,第(だい)一(いち)審(しん),第(だい)二(に)審(しん),第(だい)三(さん)審(しん)の三(みっ)つの審(しん)級(きゅう)の裁判所(さいばんしょ)を設(もう)けて,当事者(とうじしゃ)が望(のぞ)めば,原則(げんそく)的(てき)に3回(かい)までの反復(はんぷく)審理(しんり)を受(う)けられるという制度(せいど)を採用(さいよう)しています。
第(だい)一(いち)審(しん)の裁判所(さいばんしょ)の判決(はんけつ)に不服(ふふく)のある当事者(とうじしゃ)は,第(だい)二(に)審(しん)の裁判所(さいばんしょ)に不服(ふふく)申(もう)し立(た)て(控訴(こうそ))をすることができ,第(だい)二(に)審(しん)の裁判所(さいばんしょ)の判決(はんけつ)にも不服(ふふく)のある当事者(とうじしゃ)は,更(さら)に第(だい)三(さん)審(しん)の裁判所(さいばんしょ)に不服(ふふく)申(もう)し立(た)て(上告(じょうこく))をすることができます。
この審(しん)級(きゅう)関係(かんけい)において上位(じょうい)にある裁判所(さいばんしょ)を上級(じょうきゅう)裁判所(さいばんしょ),下位(かい)にある裁判所(さいばんしょ)を下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)と呼(よ)び,不服(ふふく)申(もう)し立(た)ての控訴(こうそ)と上告(じょうこく)を併(あわ)せて上訴(じょうそ)といいます。
個々(ここ)の裁判所(さいばんしょ)は,それぞれ独立(どくりつ)して裁判(さいばん)権(けん)を行使(こうし)し,たとえ下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)であっても上級(じょうきゅう)裁判所(さいばんしょ)の指揮(しき)監督(かんとく)を受(う)けることはありませんが,
下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)の裁判(さいばん)に不服(ふふく)のある当事者(とうじしゃ)から上訴(じょうそ)があったときは,上級(じょうきゅう)裁判所(さいばんしょ)は,
下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)の裁判(さいばん)の当否(とうひ)を審査(しんさ)する権限(けんげん)を有(ゆう)し,当該(とうがい)事件(じけん)に関(かん)する限(かぎ)り,上級(じょうきゅう)裁判所(さいばんしょ)の判断(はんだん)が下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)の判断(はんだん)より優先(ゆうせん)し下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)を拘束(こうそく)するのです。このような制度(せいど)を審(しん)級(きゅう)制度(せいど)と呼(よ)んでいます。
(2) 裁判所(さいばんしょ)の配置(はいち)
憲法(けんぽう)第(だい)76条(じょう)第(だい)1項(こう)は,「すべて司法(しほう)権(けん)は,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)に属(ぞく)する。」と定(さだ)めています。
すなわち,憲法(けんぽう)は,最終(さいしゅう)審(しん),最上級(さいじょうきゅう)の裁判所(さいばんしょ)として最高裁判所(さいこうさいばんしょ)を設(もう)けるとともに,どのような下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)を設(もう)けるかについては法律(ほうりつ)にゆだねています。
この規定(きてい)を受(う)け,裁判所(さいばんしょ)法(ほう)が,下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)として高等裁判所(こうとうさいばんしょ),地方裁判所(ちほうさいばんしょ),家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)及(およ)び簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の4種類(しゅるい)の裁判所(さいばんしょ)を設(もう)け,それぞれの裁判所(さいばんしょ)が扱(あつか)う事件(じけん)を定(さだ)めています。
そして,具体(ぐたい)的(てき)な裁判所(さいばんしょ)の設立(せつりつ)及(およ)び管轄(かんかつ)区域(くいき)については,下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)の設立(せつりつ)及(およ)び管轄(かんかつ)区域(くいき)に関(かん)する法律(ほうりつ)がこれを定(さだ)めています。この関係(かんけい)を図示(ずし)すると,次(つぎ)のとおりです。

2. 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)
(1) 概説(がいせつ)
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は,憲法(けんぽう)によって設置(せっち)された我(わ)が国(くに)における唯一(ゆいいつ)かつ最高(さいこう)の裁判所(さいばんしょ)で,長官(ちょうかん)及(およ)び14人(にん)の最高裁判所(さいこうさいばんしょ)判事(はんじ)によって構成(こうせい)されています。最高裁判所(さいこうさいばんしょ)長官(ちょうかん)は,内閣(ないかく)の指名(しめい)に基(もと)づいて天皇(てんのう)によって任命(にんめい)されます。
また,14人(にん)の最高裁判所(さいこうさいばんしょ)判事(はんじ)は,内閣(ないかく)によって任命(にんめい)され,天皇(てんのう)の認証(にんしょう)を受(う)けます。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)における裁判(さいばん)は,全員(ぜんいん)で構成(こうせい)する大(だい)法廷(ほうてい)(定足数(ていそくすう)9)と,5人(にん)ずつで構成(こうせい)する三(みっ)つの小(しょう)法廷(ほうてい)(定足数(ていそくすう)3)とにおいて行(おこな)われます。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は,上告(じょうこく)及(およ)び訴訟(そしょう)法(ほう)において特(とく)に定(さだ)められた抗告(こうこく)について裁判(さいばん)権(けん)を持(も)つほか,人事(じんじ)官(かん)の弾劾(だんがい)に関(かん)する裁判(さいばん)について,第(だい)一(いち)審(しん)かつ終審(しゅうしん)としての裁判(さいばん)権(けん)を持(も)っています。
上告(じょうこく)には,まず①高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の第(だい)二(に)審(しん)又(また)は第(だい)一(いち)審(しん)の判決(はんけつ)に対(たい)する上告(じょうこく)があり,
これが上告(じょうこく)事件(じけん)の大(だい)部分(ぶぶん)を占(し)めますが,そのほかにも②地方裁判所(ちほうさいばんしょ)若(も)しくは家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)の第(だい)一(いち)審(しん)の判決(はんけつ)又(また)は簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の刑事(けいじ)の第(だい)一(いち)審(しん)の判決(はんけつ)に対(たい)するいわゆる飛躍(ひやく)上告(じょうこく),
③高等裁判所(こうとうさいばんしょ)に対(たい)する上告(じょうこく)又(また)は控訴(こうそ)で一定(いってい)の事由(じゆう)に基(もと)づき移送(いそう)されるもの,④高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の民事(みんじ)の上告(じょうこく)審(しん)の判決(はんけつ)に対(たい)するいわゆる特別(とくべつ)上告(じょうこく),⑤刑事(けいじ)の確定(かくてい)判決(はんけつ)に対(たい)する非常(ひじょう)上告(じょうこく)があります。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)に対(たい)する上告(じょうこく)の理由(りゆう)は,民事(みんじ)事件(じけん)及(およ)び行政(ぎょうせい)事件(じけん)においては,憲法(けんぽう)違反(いはん),法(ほう)が列挙(れっきょ)した重大(じゅうだい)な手続(てつづき)違反(いはん)に限(かぎ)られます。
もっとも最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は,原(げん)判決(はんけつ)に法令(ほうれい)の解釈(かいしゃく)に関(かん)する重要(じゅうよう)な事項(じこう)を含(ふく)むものと認(みと)められる事件(じけん)については,申(もう)し立(た)てにより,上告(じょうこく)審(しん)として事件(じけん)を受理(じゅり)することができます。
刑事(けいじ)事件(じけん)においては憲法(けんぽう)違反(いはん)又(また)は判例(はんれい)違反(いはん)に限(かぎ)られています。訴訟(そしょう)法(ほう)において特(とく)に定(さだ)める抗告(こうこく)には,
民事(みんじ)事件(じけん)において憲法(けんぽう)違反(いはん)を理由(りゆう)とする抗告(こうこく)や法令(ほうれい)の解釈(かいしゃく)に関(かん)する重要(じゅうよう)な事項(じこう)を含(ふく)む事件(じけん)について高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の許可(きょか)を得(え)てする抗告(こうこく)があり,
刑事(けいじ),少年(しょうねん),法廷(ほうてい)秩序(ちつじょ)維持(いじ)事件(じけん)等(など)において憲法(けんぽう)違反(いはん)又(また)は判例(はんれい)違反(いはん)を理由(りゆう)とする抗告(こうこく)等があります。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)には,我(わ)が国(くに)で唯一(ゆいいつ)の最高(さいこう)の裁判所(さいばんしょ)としての司法(しほう)裁判(さいばん)権(けん)が与(あた)えられています。さらに,憲法(けんぽう)は司法(しほう)権(けん)の完全(かんぜん)な独立(どくりつ)を守(まも)るために,
訴訟(そしょう)に関(かん)する手続(てつづき),弁護士(べんごし),裁判所(さいばんしょ)の内部(ないぶ)規律(きりつ)及(およ)び司法(しほう)事務(じむ)処理(しょり)に関(かん)する事項(じこう)について規則(きそく)を制定(せいてい)する規則(きそく)制定(せいてい)権(けん)を,
また,下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)に任命(にんめい)されるべき者(もの)の指名(しめい),裁判官(さいばんかん)以外(いがい)の裁判所(さいばんしょ)職員(しょくいん)の任命(にんめい)及(およ)び補職(ほしょく),裁判所(さいばんしょ)に関(かん)する予算(よさん)の編成(へんせい)への関与(かんよ)及(およ)び実施(じっし)等のいわゆる司法(しほう)行政(ぎょうせい)権(けん)を,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)に与(あた)えました。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)のこれらの権限(けんげん)の行使(こうし)のために,附属(ふぞく)機関(きかん)として事務(じむ)総局(そうきょく),司法研修所(しほうけんしゅうしょ),裁判所(さいばんしょ)職員(しょくいん)総合(そうごう)研修(けんしゅう)所(しょ)及(およ)び最高裁判所(さいこうさいばんしょ)図書館(としょかん)が設置(せっち)されています。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は,このようにして行政府(ぎょうせいふ)及(およ)び立法府(りっぽうふ)からの干渉(かんしょう)を排除(はいじょ)し,裁判所(さいばんしょ)の運営(うんえい)を自主(じしゅ)的(てき)に行(おこな)っています。
(2) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の日常(にちじょう)活動(かつどう)
ア 裁判(さいばん)事務(じむ)
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)における審理(しんり)及(およ)び裁判(さいばん)は,前(まえ)にも触(ふ)れたように,全(ぜん)裁判官(さいばんかん)で構成(こうせい)する大(だい)法廷(ほうてい)と,5人(にん)ずつの裁判官(さいばんかん)で構成(こうせい)する三(みっ)つの小(しょう)法廷(ほうてい)とで行(おこな)われます。
事件(じけん)は,原則(げんそく)として,高等裁判所(こうとうさいばんしょ)で行(おこな)われた裁判(さいばん)の結果(けっか)に不服(ふふく)な当事者(とうじしゃ)から提出(ていしゅつ)される上告(じょうこく)の申(もう)し立(た)てによって始(はじ)まります。最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は法律(ほうりつ)審(しん)ですから,審理(しんり)は通常(つうじょう)書面(しょめん)審理(しんり)により行(おこな)われます。
上告(じょうこく)理由(りゆう)がないと判断(はんだん)される事件(じけん)については,口頭(こうとう)弁論(べんろん)を経(へ)ないで上告(じょうこく)を棄却(ききゃく)することができます。
しかし,当事者(とうじしゃ)から不服(ふふく)のある点(てん)について直接(ちょくせつ)聴(き)いた方(ほう)がよい事件(じけん)については,口頭(こうとう)弁論(べんろん)を開(ひら)いて意見(いけん)を述(の)べる機会(きかい)を設(もう)けた後に判決(はんけつ)を言(い)い渡(わた)します。
事件(じけん)は,まず小(しょう)法廷(ほうてい)で審理(しんり)しますが,法律(ほうりつ),命令(めいれい),規則(きそく)又(また)は処分(しょぶん)が憲法(けんぽう)に適合(てきごう)するかしないかを判断(はんだん)するようなときは,大(だい)法廷(ほうてい)で審理(しんり)及(およ)び裁判(さいばん)をすることになります。
イ 司法(しほう)行政(ぎょうせい)事務(じむ)
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)には,規則(きそく)制定(せいてい)権(けん)と最高(さいこう)の司法(しほう)行政(ぎょうせい)機関(きかん)としての司法(しほう)行政(ぎょうせい)権(けん)が与(あた)えられています。
これらの権限(けんげん)は,長官(ちょうかん)と14人(にん)の裁判官(さいばんかん)によって構成(こうせい)される最高裁判所(さいこうさいばんしょ)裁判官(さいばんかん)会議(かいぎ)の議決(ぎけつ)に基(もと)づいて行使(こうし)しています。
重要(じゅうよう)な規則(きそく)の制定(せいてい)に当(あ)たっては,その制定(せいてい)を慎重(しんちょう)に行(おこな)うため,裁判官(さいばんかん),検察官(けんさつかん),弁護士(べんごし),関係(かんけい)機関(きかん)の職員(しょくいん)及(およ)び学識(がくしき)経験(けいけん)者(しゃ)から成(な)る規則(きそく)制定(せいてい)諮問(しもん)委員(いいん)会(かい)を設(もう)けて諮問(しもん)し,
その答申(とうしん)に基(もと)づいて作成(さくせい)された原案(げんあん)を,裁判官(さいばんかん)会議(かいぎ)で審議(しんぎ)し,決定(けってい)しています。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)が発足(ほっそく)以来(いらい),制定(せいてい)した規則(きそく)は100件(けん)を超(こ)えています。そのうち主(おも)なものは,民事(みんじ)訴訟(そしょう)規則(きそく),刑事(けいじ)訴訟(そしょう)規則(きそく),家事(かじ)審判(しんぱん)規則(きそく),少年(しょうねん)審判(しんぱん)規則(きそく)等です。
前述(ぜんじゅつ)のとおり,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)長官(ちょうかん)の指名(しめい)及(およ)びその他(ほか)の裁判官(さいばんかん)の任命(にんめい)は,内閣(ないかく)の権限(けんげん)に属(ぞく)しますが,裁判官(さいばんかん)の補職(ほしょく),転任(てんにん)等は,すべて最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の権限(けんげん)に属(ぞく)しており,裁判官(さいばんかん)会議(かいぎ)の議決(ぎけつ)を経(へ)て実施(じっし)しています。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)長官(ちょうかん)は,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)判事(はんじ)の任命(にんめい)について,内閣(ないかく)から意見(いけん)を求(もと)められるのが慣例(かんれい)となっています。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は,毎年(まいとし),次(つぎ)の年(とし)1年間(ねんかん)に必要(ひつよう)な経費(けいひ)の見積(みつもり)書(しょ)を,裁判官(さいばんかん)会議(かいぎ)の議(ぎ)を経(へ)て,直接(ちょくせつ),内閣(ないかく)に送付(そうふ)しますが,もし,これについて内閣(ないかく)との協議(きょうぎ)が調(ととの)わず減額(げんがく)されたときは,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は,
更(さら)にその減額(げんがく)された部分(ぶぶん)の増額(ぞうがく)を請求(せいきゅう)することができます。この場合(ばあい),内閣(ないかく)は,国(くに)の歳入(さいにゅう)歳出(さいしゅつ)予算(よさん)にその詳細(しょうさい)を付記(ふき)し,国会(こっかい)の審議(しんぎ)に供(きょう)することになっています。

3. 下級(かきゅう)裁判所(さいばんしょ)
(1) 高等裁判所(こうとうさいばんしょ)
高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は,日本(にっぽん)の8か所(しょ)の大都市(だいとし)(東京(とうきょう),大阪(おおさか),名古屋(なごや),広島(ひろしま),福岡(ふくおか),仙台(せんだい),札幌(さっぽろ),高松(たかまつ))に置(お)かれているほか,6か所(しょ)の都市(とし)に支部(しぶ)が設(もう)けられています。
また,特別(とくべつ)の支部(しぶ)として,東京(とうきょう)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)に知的(ちてき)財産(ざいさん)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)が設(もう)けられています。
高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は,高等裁判所(こうとうさいばんしょ)長官(ちょうかん)及(およ)び判事(はんじ)によって組織(そしき)されています。高等裁判所(こうとうさいばんしょ)長官(ちょうかん)は,内閣(ないかく)によって任命(にんめい)され,天皇(てんのう)の認証(にんしょう)を受(う)けます。
高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は,地方裁判所(ちほうさいばんしょ)若(も)しくは家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)の判決(はんけつ)又(また)は簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の刑事(けいじ)の判決(はんけつ)に対(たい)する控訴(こうそ),地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の民事(みんじ)の第(だい)二(に)審(しん)判決(はんけつ)に対(たい)する上告(じょうこく)及(およ)び簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の民事(みんじ)の判決(はんけつ)に対(たい)する飛躍(ひやく)上告(じょうこく),
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)又(また)は家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)の決定(けってい)に対(たい)する抗告(こうこく)について裁判(さいばん)権(けん)を持(も)っています。
そのほか,高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は,選挙(せんきょ)に関(かん)する行政(ぎょうせい)訴訟(そしょう),内乱(ないらん)罪(ざい)等に関(かん)する刑事(けいじ)事件(じけん)について,第(だい)一(いち)審(しん)裁判(さいばん)権(けん)を持(も)っており,東京(とうきょう)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は,
さらに,公正(こうせい)取引(とりひき)委員(いいん)会(かい)や特許庁(とっきょちょう)のような準(じゅん)司法(しほう)的(てき)機関(きかん)の審決(しんけつ)に対(たい)する取消(とりけし)訴訟(そしょう)について,第(だい)一(いち)審(しん)裁判(さいばん)権(けん)を持(も)っています。
知的(ちてき)財産(ざいさん)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は,東京(とうきょう)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の管轄(かんかつ)に属(ぞく)する事件(じけん)のうち,特許(とっきょ)権(けん)に関(かん)する地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の判決(はんけつ)に対(たい)する控訴(こうそ),
特許庁(とっきょちょう)が行(おこな)った審決(しんけつ)に対(たい)する取消(とりけし)訴訟(そしょう)など,一定(いってい)の知的(ちてき)財産(ざいさん)に関(かん)する事件(じけん)を取(と)り扱(あつか)います。
高等裁判所(こうとうさいばんしょ)における裁判(さいばん)は,原則(げんそく)として3人(にん)の裁判官(さいばんかん)から成(な)る合議(ごうぎ)体(たい)によって審理(しんり)されます。なお,内乱(ないらん)罪(ざい)及(およ)び公正(こうせい)取引(とりひき)委員(いいん)会(かい)の審決(しんけつ)の訴訟(そしょう)等(など)は,
5人(にん)の裁判官(さいばんかん)から成(な)る合議(ごうぎ)体(たい)によって審理(しんり)されることになっています。

東京(とうきょう)高等(こうとう),地方(ちほう),簡易(かんい)合同庁舎(ごうどうちょうしゃ)
旧(きゅう)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)跡地(あとち)に建設(けんせつ)され,昭和(しょうわ)59年(ねん)5月(ごがつ)に竣工(しゅんこう)しました。
(2) 地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)は,全国(ぜんこく)に50か所(しょ)あり,その管轄(かんかつ)区域(くいき)は北海道(ほっかいどう)が四(よっ)つに分(わ)かれているほか,各(かく)都府県(とふけん)と同(おな)じです。地方裁判所(ちほうさいばんしょ)に支部(しぶ)が設(もう)けられており,その総数(そうすう)は203です。
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)は,原則(げんそく)的(てき)な第(だい)一(いち)審(しん)裁判所(さいばんしょ)で,他(た)の裁判所(さいばんしょ)が第(だい)一(いち)審(しん)専属(せんぞく)管轄(かんかつ)権(けん)を持(も)つ特別(とくべつ)なものを除(のぞ)いて,
第(だい)一(いち)審(しん)事件(じけん)のすべてを裁判(さいばん)することができるものとされています。さらに,地方裁判所(ちほうさいばんしょ)は,簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の民事(みんじ)の判決(はんけつ)に対(たい)する控訴(こうそ)事件(じけん)についても裁判(さいばん)権(けん)を持(も)っています。
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の事件(じけん)は,単独(たんどく)裁判官(さいばんかん)又(また)は原則(げんそく)として3人(にん)の裁判官(さいばんかん)から成(な)る合議(ごうぎ)体(たい)のどちらかで取(と)り扱(あつか)われます。大(だい)多数(たすう)の事件(じけん)は,
単独(たんどく)裁判官(さいばんかん)によって処理(しょり)されていますが,次(つぎ)の事件(じけん)については,合議(ごうぎ)体(たい)による裁判(さいばん)が必要(ひつよう)とされています。
1. 「合議(ごうぎ)体(たい)で審理(しんり)及(およ)び裁判(さいばん)をする」旨(むね)を合議(ごうぎ)体(たい)で決定(けってい)した事件(じけん)
2. 死刑(しけい)又(また)は無期(むき)若(も)しくは短期(たんき)1年(ねん)以上(いじょう)の懲役(ちょうえき)若(も)しくは禁錮(きんこ)に当(あ)たる罪(つみ)の事件(じけん)(強盗(ごうとう)罪(ざい),準(じゅん)強盗(ごうとう)罪(ざい),これらの未遂(みすい)罪(ざい),盗犯(とうはん)防止(ぼうし)法(ほう)に規定(きてい)される常習(じょうしゅう)強(きょう)窃()罪(ざい)の事件(じけん)等(など)は例外(れいがい)とされています。)
3. 控訴(こうそ)事件(じけん)
4. その他(た)法律(ほうりつ)によって合議(ごうぎ)事件(じけん)と定(さだ)められたもの

大阪(おおさか)高等(こうとう),地方(ちほう),簡易裁判所(かんいさいばんしょ)合同庁舎(ごうどうちょしゃ)
(3) 家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)
家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)とその支部(しぶ)は,地方裁判所(ちほうさいばんしょ)とその支部(しぶ)の所在地(しょざいち)と同(おな)じ所(ところ)にあります。このほか,特(とく)に必要(ひつよう)性(せい)の高(たか)いところに家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)出張所(しゅっちょうしょ)が設(もう)けられています。
家庭(かてい)内(ない)の紛争(ふんそう)を通常(つうじょう)の訴訟(そしょう)の手続(てつづき)により審理(しんり)すると,公開(こうかい)の法廷(ほうてい)で夫婦(ふうふ),親子(おやこ)などの親族(しんぞく)が争(あらそ)うことになりますし,法律(ほうりつ)的(てき)判断(はんだん)が中心(ちゅうしん)になり,相互(そうご)の感情(かんじょう)的(てき)な対立(たいりつ)が十分(じゅうぶん)に解決(かいけつ)されないままで終(お)わるおそれがあります。
したがって,家庭(かてい)内(ない)の紛争(ふんそう)については,まず最初(さいしょ)に,訴訟(そしょう)の手続(てつづき)ではなく,それにふさわしい非公開(ひこうかい)の手続(てつづき)で情理(じょうり)を踏(ふ)まえた解決(かいけつ)を図(はか)る必要(ひつよう)があります。
また,非行(ひこう)を犯(おか)した少年(しょうねん)に対(たい)し,成人(せいじん)と同様(どうよう)に公開(こうかい)の法廷(ほうてい)で訴訟(そしょう)の手続(てつづき)によって刑罰(けいばつ)を科(か)すことは,少年(しょうねん)にとって必(かなら)ずしも好(この)ましい結果(けっか)をもたらすとは限(かぎ)りません。
人格(じんかく)が未熟(みじゅく)であり,教育(きょういく)によって改善(かいぜん)される可能(かのう)性(せい)の高(たか)い少年(しょうねん)に対(たい)しては,それにふさわしい非公開(ひこうかい)の手続(てつづき)で,保護(ほご)処分(しょぶん)や適切(てきせつ)な教育(きょういく)的(てき)措置(そち)を行(おこな)うことが大切(たいせつ)であると考(かんが)えられます。
このように,家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)は,法律(ほうりつ)的(てき)に白黒(しろくろ)をつけるというのではなく,紛争(ふんそう)や非行(ひこう)の背後(はいご)にある原因(げんいん)を探(さぐ)り,どのようにすれば,家庭(かてい)や親族(しんぞく)の間(あいだ)で起(お)きたいろいろな問題(もんだい)が円満(えんまん)に解決(かいけつ)され,
非行(ひこう)を犯(おか)した少年(しょうねん)が健全(けんぜん)に更生(こうせい)していくことができるのかということを第(だい)一(いち)に考(かんが)えて,
それぞれの事案(じあん)に応(おう)じた適切(てきせつ)妥当(だとう)な措置(そち)を講(こう)じ,将来(しょうらい)を展望(てんぼう)した解決(かいけつ)を図(はか)るという理念(りねん)に基(もと)づいた裁判所(さいばんしょ)です。
そのために家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)調査官(ちょうさかん)という職種(しょくしゅ)が置(お)かれ,
心理(しんり)学(がく),社会(しゃかい)学(がく),社会(しゃかい)福祉(ふくし)学(がく),教育(きょういく)学(がく)などの人間(にんげん)関係(かんけい)諸(しょ)科学(かがく)の知識(ちしき)や技法(ぎほう)を活用(かつよう)した事実(じじつ)の調査(ちょうさ)や人間(にんげん)関係(かんけい)の調整(ちょうせい)を行(おこな)うことになっています。
家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)においては,夫婦(ふうふ)関係(かんけい)や親子(おやこ)関係(かんけい)の紛争(ふんそう)など家事(かじ)事件(じけん)について調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)を,
非行(ひこう)を犯(おか)した少年(しょうねん)の事件(じけん)について審判(しんぱん)を行(おこな)うほか,少年(しょうねん)の福祉(ふくし)を害(がい)する成人(せいじん)の刑事(けいじ)事件(じけん)について裁判(さいばん)をします。
また,平成(へいせい)16年(ねん)4月(しがつ)1日(にち)からは,人事(じんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)の施行(しこう)に伴(ともな)い,夫婦(ふうふ),親子(おやこ)等の関係(かんけい)をめぐる訴訟(そしょう)についても取(と)り扱(あつか)うことになりました。それにより,利用(りよう)者(しゃ)である国民(こくみん)にとって,手続(てつづき)がより利用(りよう)しやすくなるとともに,
家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)が創設(そうせつ)以来(いらい)培(つちか)ってきた家庭(かてい)に関(かん)する紛争(ふんそう)の解決(かいけつ)についての知識(ちしき)や経験(けいけん)を,訴訟(そしょう)においても生(い)かすことができるようになりました。

京都(きょうと)家庭(かてい)裁判所(さいばんしょ)
(4) 簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)は,全国(ぜんこく)に438か所(しょ)あります。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)は,民事(みんじ)事件(じけん)については,訴訟(そしょう)の目的(もくてき)となる物(もの)の価額(かがく)が140万(まん)円(えん)を超(こ)えない請求(せいきゅう)事件(じけん)について,
また刑事(けいじ)事件(じけん)については,罰金(ばっきん)以下(いか)の刑(けい)に当(あ)たる罪(つみ)及(およ)び窃盗(せっとう),横領(おうりょう)などの比較的(ひかくてき)軽(かる)い罪(つみ)の訴訟(そしょう)事件(じけん)等について,第(だい)一(いち)審(しん)の裁判(さいばん)権(けん)を持(も)っています。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)は,その管轄(かんかつ)に属(ぞく)する事件(じけん)について,罰金(ばっきん)以下(いか)の刑(けい)又(また)は3年(ねん)以下(いか)の懲役(ちょうえき)刑(けい)しか科(か)することができません。
この制限(せいげん)を超(こ)える刑(けい)を科(か)するのを相当(そうとう)と認(みと)めるときは,事件(じけん)を地方裁判所(ちほうさいばんしょ)に移送(いそう)しなければなりません。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)においては,民事(みんじ)事件(じけん)又(また)は刑事(けいじ)事件(じけん)について,簡易(かんい)に処理(しょり)する特別(とくべつ)な手続(てつづき)を利用(りよう)することができます。民事(みんじ)事件(じけん)に関(かん)しては,
裁判所(さいばんしょ)は60万(まん)円(えん)以下(いか)の金銭(きんせん)の支払(しはらい)を求(もと)める事件(じけん)について,原告(げんこく)の申出(もうしで)があり,被告(ひこく)に異議(いぎ)がなければ,原則(げんそく)として1回(かい)の期日(きじつ)で審理(しんり)を終(お)えた上(うえ),
分割(ぶんかつ)払(ばら)い等の判決(はんけつ)をすることができますし,裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)は債権(さいけん)者(しゃ)の申(もう)し立(た)てによって,債務(さいむ)者(しゃ)を調(しら)べないで金銭(きんせん)の支払(しはらい)を命(めい)ずることができます。
また,刑事(けいじ)事件(じけん)に関(かん)しては,被告(ひこく)人(じん)に異議(いぎ)がないときに限(かぎ)り,検察官(けんさつかん)の請求(せいきゅう)により,
その管轄(かんかつ)に属(ぞく)する事件(じけん)について証拠(しょうこ)書類(しょるい)だけを調(しら)べて50万(まん)円(えん)以下(いか)の罰金(ばっきん)又(また)は科料(かりょう)を科(か)することができます。
以上(いじょう)の簡易(かんい)手続(てつづき)は,債務(さいむ)者(しゃ)又(また)は被告(ひこく)人(じん)の通常(つうじょう)の手続(てつづき)による裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)を奪(うば)うものではありません。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)には,身近(みぢか)な民事(みんじ)紛争(ふんそう)を話(はな)し合(あ)いで解決(かいけつ)するため調停(ちょうてい)という制度(せいど)もあります。民事(みんじ)調停(ちょうてい)は,費用(ひよう)も安(やす)く,
裁判官(さいばんかん)又(また)は民事(みんじ)調停(ちょうてい)官(かん)と2人(にん)以上(いじょう)の民事(みんじ)調停(ちょうてい)委員(いいん)によって構成(こうせい)された調停(ちょうてい)委員(いいん)会(かい)が当事者(とうじしゃ)双方(そうほう)の言(い)い分(いぶん)を十分(じゅうぶん)聴(き)いて双方(そうほう)の合意(ごうい)を目指(めざ)します。
調停(ちょうてい)で合意(ごうい)が成立(せいりつ)し,その内容(ないよう)が調書(ちょうしょ)に記載(きさい)されると,その調書(ちょうしょ)の記載(きさい)は,裁判所(さいばんしょ)がした判決(はんけつ)と同(おな)じ効力(こうりょく)を持(も)つことになります。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)に対(たい)する民事(みんじ)の訴訟(そしょう)や調停(ちょうてい)の申(もう)し立(た)ては口頭(こうとう)ですることもできますし,紛争(ふんそう)の内容(ないよう)によっては,簡単(かんたん)に申(もう)し立(た)てを行(おこな)うことができるように,窓口(まどぐち)には定型(ていけい)用紙(ようし)も用意(ようい)されています。
簡易裁判所(かんいさいばんしょ)におけるすべての事件(じけん)は,1人(にん)の簡易裁判所(かんいさいばんしょ)判事(はんじ)によって審理(しんり)及(およ)び裁判(さいばん)されます。

 民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)(민사소송법
1조~6조) 民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)(민사소송법
1조~6조)

--------------------------------------------------------------------------------
第(だい)1編(へん) 総則(そうそく)
--------------------------------------------------------------------------------
第(だい)1章(しょう) 通則(つうそく)
--------------------------------------------------------------------------------
(趣旨(しゅし))
第(だい)1条(じょう) 民事(みんじ)訴訟(そしょう)に関(かん)する手続(てつづき)については、他(ほか)の法令(ほうれい)に定(さだ)めるもののほか、この法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところによる。
--------------------------------------------------------------------------------
(裁判所(さいばんしょ)及(およ)び当事者(とうじしゃ)の責務(せきむ))
第(だい)2条(じょう) 裁判所(さいばんしょ)は、民事(みんじ)訴訟(そしょう)が公正(こうせい)かつ迅速(じんそく)に行(おこな)われるように努(つと)め、当事者(とうじしゃ)は、信義(しんぎ)に従(したが)い誠実(せいじつ)に民事(みんじ)訴訟(そしょう)を追(つい)行(こう)しなければならない。
--------------------------------------------------------------------------------
(最高裁判所(さいこうさいばんしょ)規則(きそく))
第(だい)3条(じょう) この法律(ほうりつ)に定(さだ)めるもののほか、民事(みんじ)訴訟(そしょう)に関(かん)する手続(てつづき)に関(かん)し必要(ひつよう)な事項(じこう)は、 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)規則(きそく) で定(さだ)める。
--------------------------------------------------------------------------------
第(だい)2章(しょう) 裁判所(さいばんしょ)
--------------------------------------------------------------------------------
第(だい)1節(せつ) 管轄(かんかつ)
--------------------------------------------------------------------------------
(普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)による管轄(かんかつ))
第(だい)4条(じょう) 訴(うった)えは、被告(ひこく)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)の所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)の管轄(かんかつ)に属(ぞく)する。
(2) 人(ひと)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)は、住所(じゅうしょ)により、日本(にっぽん)国内(こくない)に住所(じゅうしょ)がないとき又(また)は住所(じゅうしょ)が知(し)れないときは居所(いどころ)により、日本(にっぽん)国内(こくない)に居所(いどころ)がないとき又(また)は居所(いどころ)が知(し)れないときは最後(さいご)の住所(じゅうしょ)により定(さだ)まる。
(3) 大使(たいし)、公使(こうし)その他(ほか)外国(がいこく)に在(あ)ってその国(くに)の裁判(さいばん)権(けん)からの免除(めんじょ)を享有(きょうゆう)する日本人(にっぽんじん)が前項(ぜんこう)の規定(きてい)により普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)を有(ゆう)しないときは、その者(もの)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)は、 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)規則(きそく)で定(さだ)める地(ち)にあるものとする。
(4) 法人(ほうじん)その他(ほか)の社団(しゃだん)又(また)は財団(ざいだん)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)は、その主(しゅ)たる事務所(じむしょ)又(また)は営業(えいぎょう)所(しょ)により、事務所(じむしょ)又(また)は営業(えいぎょう)所(しょ)がないときは代表(だいひょう)者(しゃ)その他(ほか)の主(しゅ)たる業務(ぎょうむ)担当(たんとう)者(しゃ)の住所(じゅうしょ)により定(さだ)まる。
(5) 外国(がいこく)の社団(しゃだん)又(また)は財団(ざいだん)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)は、前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、日本(にっぽん)における主(しゅ)たる事務所(じむしょ)又(また)は営業(えいぎょう)所(しょ)により、日本(にっぽん)国内(こくない)に事務所(じむしょ)又(また)は営業(えいぎょう)所(しょ)がないときは日本(にっぽん)における代表(だいひょう)者(しゃ)その他(ほか)の主(しゅ)たる業務(ぎょうむ)担当(たんとう)者(しゃ)の住所(じゅうしょ)により定(さだ)まる。
(6) 国(くに)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)は、訴訟(そしょう)について国(くに)を代表(だいひょう)する官庁(かんちょう)の所在地(しょざいち)により定(さだ)まる。
--------------------------------------------------------------------------------
(財産(ざいさん)権(けん)上(じょう)の訴(うった)え等についての管轄(かんかつ))
第(だい)5条(じょう) 次(つぎ)の各(かく)号(ごう)に掲(かか)げる訴(うった)えは、それぞれ当該(とうがい)各(かく)号(ごう)に定(さだ)める地(ち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)に提起(ていき)することができる。
1 財産(ざいさん)権(けん)上(じょう)の訴(うった)え
|
義務(ぎむ)履行(りこう)地(ち)
|
2 手形(てがた)又(また)は小切手(こぎって)による金銭(きんせん)の支払(しはらい)の請求(せいきゅう)を目的(もくてき)とする訴(うった)え
|
手形(てがた)又(また)は小切手(こぎって)の支払(しはらい)地(ち)
|
3 船員(せんいん)に対(たい)する財産(ざいさん)権(けん)上(じょう)の訴(うった)え
|
船舶(せんぱく)の船籍(せんせき)の所在地(しょざいち)
|
4 日本(にっぽん)国内(こくない)に住所(じゅうしょ)(法人(ほうじん)にあっては、事務所(じむしょ)又(また)は営業(えいぎょう)所(しょ)。以下(いか)この号(ごう)において同(おな)じ。)がない者(もの)又(また)は住所(じゅうしょ)が知(し)れない者(もの)に対(たい)する財産(ざいさん)権(けん)上(じょう)の訴(うった)え
|
請求(せいきゅう)若(も)しくはその担保(たんぽ)の目的(もくてき)又(また)は差(さ)し押(お)さえることができる被告(ひこく)の財産(ざいさん)の所在地(しょざいち)
|
5 事務所(じむしょ)又(また)は営業(えいぎょう)所(しょ)を有(ゆう)する者(もの)に対(たい)する訴(うった)えでその事務所(じむしょ)又(また)は営業(えいぎょう)所(しょ)における業務(ぎょうむ)に関(かん)するもの
|
当該(とうがい)事務所(じむしょ)又(また)は営業(えいぎょう)所(しょ)の所在地(しょざいち)
|
6 船舶(せんぱく)所有(しょゆう)者(しゃ)その他(た)船舶(せんぱく)を利用(りよう)する者(もの)に対(たい)する船舶(せんぱく)又(また)は航海(こうかい)に関(かん)する訴(うった)え
|
船舶(せんぱく)の船籍(せんせき)の所在地(しょざいち)
|
7 船舶(せんぱく)債権(さいけん)その他(た)船舶(せんぱく)を担保(たんぽ)とする債権(さいけん)に基(もと)づく訴(うった)え
|
船舶(せんぱく)の所在地(しょざいち)
|
8 会社(かいしゃ)その他(ほか)の社団(しゃだん)又(また)は財団(ざいだん)に関(かん)する訴(うった)えで次(つぎ)に掲(かか)げるもの
イ 会社(かいしゃ)その他(た)の社団(しゃだん)からの社員(しゃいん)若(も)しくは社員(しゃいん)であった者(もの)に対(たい)する訴(うった)え、社員(しゃいん)からの社員(しゃいん)若(も)しくは社員(しゃいん)であった者(もの)に対(たい)する訴(うった)え又(また)は社員(しゃいん)であった者(もの)からの社員(しゃいん)に対(たい)する訴(うった)えで、社員(しゃいん)としての資格(しかく)に基(もと)づくもの
ロ 社団(しゃだん)又(また)は財団(ざいだん)からの役員(やくいん)又(また)は役員(やくいん)であった者(もの)に対(たい)する訴(うった)えで役員(やくいん)としての資格(しかく)に基(もと)づくもの
ハ 会社(かいしゃ)からの発起人(ほっきにん)若(も)しくは発起人(ほっきにん)であった者(もの)又(また)は検査(けんさ)役(やく)若(も)しくは検査(けんさ)役(やく)であった者(もの)に対(たい)する訴(うった)えで発起人(ほっきにん)又(また)は検査(けんさ)役(やく)としての資格(しかく)に基(もと)づくもの
ニ 会社(かいしゃ)その他(た)の社団(しゃだん)の債権(さいけん)者(しゃ)からの社員(しゃいん)又(また)は社員(しゃいん)であった者(もの)に対(たい)する訴(うった)えで社員(しゃいん)としての資格(しかく)に基(もと)づくもの
|
社団(しゃだん)又(また)は財団(ざいだん)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)の所在地(しょざいち)
|
9 不法(ふほう)行為(こうい)に関(かん)する訴(うった)え
|
不法(ふほう)行為(こうい)があった地(ち)
|
10 船舶(せんぱく)の衝突(しょうとつ)その他(た)海上(かいじょう)の事故(じこ)に基(もと)づく損害(そんがい)賠償(ばいしょう)の訴(うった)え
|
損害(そんがい)を受(う)けた船舶(せんぱく)が最初(さいしょ)に到達(とうたつ)した地(ち)
|
11 海難(かいなん)救助(きゅうじょ)に関(かん)する訴(うった)え
|
海難(かいなん)救助(きゅうじょ)があった地(ち)又(また)は救助(きゅうじょ)された船舶(せんぱく)が最初(さいしょ)に到達(とうたつ)した地(ち)
|
12 不動産(ふどうさん)に関(かん)する訴(うった)え
|
不動産(ふどうさん)の所在地(しょざいち)
|
13 登記(とうき)又(また)は登録(とうろく)に関(かん)する訴(うった)え
|
登記(とうき)又(また)は登録(とうろく)をすべき地(ち)
|
14 相続(そうぞく)権(けん)若(も)しくは遺留分(いりゅうぶん)に関(かん)する訴(うった)え又(また)は遺贈(いぞう)その他(ほか)死亡(しぼう)によって効力(こうりょく)を生(しょう)ずべき行為(こうい)に関(かん)する訴(うった)え
|
相続(そうぞく)開始(かいし)の時(とき)における被(ひ)相続(そうぞく)人(じん)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)の所在地(しょざいち)
|
15 相続(そうぞく)債権(さいけん)その他(た)相続(そうぞく)財産(ざいさん)の負担(ふたん)に関(かん)する訴(うった)えで
前号(ぜんごう)に掲(かか)げる訴(うった)えに該当(がいとう)しないもの(相続(そうぞく)財産(ざいさん)の全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)が同(どう)号(ごう)に定(さだ)める地(ち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)の管轄(かんかつ)区域(くいき)内(ない)にあるときに限(かぎ)る。)
|
同(どう)号(ごう)に定(さだ)める地(ち)
|
--------------------------------------------------------------------------------
(特許(とっきょ)権(けん)等に関(かん)する訴(うった)え等の管轄(かんかつ))
第(だい)6条(じょう) 特許(とっきょ)権(けん)、実用(じつよう)新案(しんあん)権(けん)、回路(かいろ)配置(はいち)利用(りよう)権(けん)又(また)はプログラムの著作(ちょさく)物(ぶつ)についての著作(ちょさく)者(しゃ)の権利(けんり)に関(かん)する訴(うった)え(以下(いか)「特許(とっきょ)権(けん)等に関(かん)する訴(うった)え」という。)について、前(まえ)2条(じょう)の規定(きてい)によれば次(つぎ)の各(かく)号(ごう)に掲(かか)げる裁判所(さいばんしょ)が管轄(かんかつ)権(けん)を有(ゆう)すべき場合(ばあい)には、
その訴(うった)えは、それぞれ当該(とうがい)各(かく)号(ごう)に定(さだ)める裁判所(さいばんしょ)の管轄(かんかつ)に専属(せんぞく)する。
1 東京(とうきょう)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)、名古屋(なごや)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)、仙台(せんだい)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)又(また)は札幌(さっぽろ)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の管轄(かんかつ)区域(くいき)内(ない)に所在(しょざい)する地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
|
東京(とうきょう)地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
|
2 大阪(おおさか)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)、広島(ひろしま)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)、福岡(ふくおか)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)又(また)は高松(たかまつ)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の管轄(かんかつ)区域(くいき)内(ない)に所在(しょざい)する地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
|
大阪(おおさか)地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
|
(2) 特許(とっきょ)権(けん)等(など)に関(かん)する訴(うった)えについて、前(まえ)2条(じょう)の規定(きてい)により前項(ぜんこう)各(かく)号(ごう)に掲(かか)げる裁判所(さいばんしょ)の管轄(かんかつ)区域(くいき)内(ない)に所在(しょざい)する簡易裁判所(かんいさいばんしょ)が管轄(かんかつ)権(けん)を有(ゆう)する場合(ばあい)には、それぞれ当該(とうがい)各(かく)号(ごう)に定(さだ)める裁判所(さいばんしょ)にも、その訴(うった)えを提起(ていき)することができる。
(3) 第(だい)1項(こう)第(だい)2号(ごう)に定(さだ)める裁判所(さいばんしょ)が第(だい)一(いち)審(しん)としてした特許(とっきょ)権(けん)等(など)に関(かん)する訴(うった)えについての終局(しゅうきょく)判決(はんけつ)に対(たい)する控訴(こうそ)は、
東京(とうきょう)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の管轄(かんかつ)に専属(せんぞく)する。ただし、第(だい)20条(じょう)の2第(だい)1項(こう)の規定(きてい)により移送(いそう)された訴訟(そしょう)に係(かか)る訴(うった)えについての終局(しゅうきょく)判決(はんけつ)に対(たい)する控訴(こうそ)については、この限(かぎ)りでない。
--------------------------------------------------------------------------------
 第(だい)1 民事(みんじ)訴訟(そしょう)とその手続(てつづき) 第(だい)1 民事(みんじ)訴訟(そしょう)とその手続(てつづき)

1 民事(みんじ)訴訟(そしょう)の種類(しゅるい)
(1) 通常(つうじょう)訴訟(そしょう)
(2) 手形(てがた)小切手(こぎって)訴訟(そしょう)
(3) 少額(しょうがく)訴訟(そしょう)
(4) その他(ほか)
2 民事(みんじ)訴訟(そしょう)の審理(しんり)手続(てつづき)
(1) 手続(てつづき)の開始(かいし) -訴(うった)えの提起(ていき)
ア 訴(うった)えの提起(ていき)
イ 管轄(かんかつ)
(2) 口頭(こうとう)弁論(べんろん)等(など)
ア 訴状(そじょう)の審査(しんさ)等
イ 口頭(こうとう)弁論(べんろん)
ウ 争点(そうてん)及(およ)び証拠(しょうこ)の整理(せいり)手続(てつづき)
エ 証拠(しょうこ)調(しら)べ
オ 口頭(こうとう)弁論(べんろん)調書(ちょうしょ)
(3) 訴訟(そしょう)の終了(しゅうりょう)
(4) 判決(はんけつ)に対(たい)する上訴(じょうそ) -控訴(こうそ)と上告(じょうこく)
3 訴訟(そしょう)費用(ひよう)及(およ)びその補助(ほじょ)
(1) 訴訟(そしょう)費用(ひよう)の負担(ふたん)
(2) 補助(ほじょ)の種類(しゅるい)
第(だい)2 その他(ほか)の民事(みんじ)事件(じけん)とその手続(てつづき)
1 民事(みんじ)執行(しっこう)手続(てつづき)
(1) 強制(きょうせい)執行(しっこう)手続(てつづき)と
担保(たんぽ)権(けん)の実行(じっこう)としての競売(きょうばい)手続(てつづき)
(2) 不動産(ふどうさん)執行(しっこう)手続(てつづき)と債権(さいけん)執行(しっこう)手続(てつづき)
2 倒産(とうさん)手続(てつづき)
(1) 破産(はさん)手続(てつづき)について
(2) 民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)について
ア 通常(つうじょう)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)
イ 個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)
第(だい)3 近時(きんじ)の民事(みんじ)訴訟(そしょう)の状況(じょうきょう)と問題(もんだい)
第(だい))1 民事(みんじ)訴訟(そしょう)とその手続(てつづき)
1 民事(みんじ)訴訟(そしょう)の種類(しゅるい)
民事(みんじ)訴訟(そしょう)の種類(しゅるい)は大(おお)きく次(つぎ)のように分類(ぶんるい)することができます。
(1) 通常(つうじょう)訴訟(そしょう)
個人(こじん)の間(あいだ)の法的(ほうてき)な紛争(ふんそう),主(しゅ)として財産(ざいさん)権(けん)に関(かん)する紛争(ふんそう)の解決(かいけつ)を求(もと)める訴訟(そしょう)です。例(たと)えば,貸金(かしきん)の返還(へんかん),不動産(ふどうさん)の明(あけ)渡(わた)し,
人身(じんしん)損害(そんがい)に対(たい)する損害(そんがい)賠償(ばいしょう)を求(もと)める訴(うった)えは,この類型(るいけい)に入(はい)ります。この類型(るいけい)の訴訟(そしょう)は「通常(つうじょう)訴訟(そしょう)」と呼(よ)ばれ,民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)に従(したが)って審理(しんり)が行(おこな)われます。
(2) 手形(てがた)小切手(こぎって)訴訟(そしょう)
民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)の特別(とくべつ)の規定(きてい)によって審理(しんり)される手形(てがた)・小切手(こぎって)金(きん)の支払(しはらい)を求(もと)める訴訟(そしょう)です。
この類型(るいけい)の訴訟(そしょう)は,「手形(てがた)小切手(こぎって)訴訟(そしょう)」と呼(よ)ばれます。この訴訟(そしょう)では,判決(はんけつ)を早期(そうき)に言(い)い渡(いわた)すことができるようにするため,
証拠(しょうこ)は書証(しょしょう)と当事者(とうじしゃ)尋問(じんもん)に限(かぎ)られます。もっとも,第(だい)一(いち)審(しん)の通常(つうじょう)訴訟(そしょう)の手続(てつづき)による再(さい)審理(しんり)を要求(ようきゅう)する機会(きかい)は保障(ほしょう)されています。
手形(てがた)・小切手(こぎって)金(きん)の支払(しはらい)を求(もと)める原告(げんこく)は,この類型(るいけい)の訴訟(そしょう)を提起(ていき)するか,通常(つうじょう)訴訟(そしょう)を提起(ていき)するかを選択(せんたく)することができます。
(3) 少額(しょうがく)訴訟(そしょう)
簡易(かんい)迅速(じんそく)な手続(てつづき)により60万(まん)円(えん)以下(いか)の金銭(きんせん)の支払(しはらい)を求(もと)める訴訟(そしょう)です。この類型(るいけい)の訴訟(そしょう)は,「少額(しょうがく)訴訟(そしょう)」と呼(よ)ばれます。この訴訟(そしょう)については,簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の民事(みんじ)手続(てつづき)をご覧(らん)ください。
(4) その他(た)
その他(た)の類型(るいけい)としては,離婚(りこん)や認知(にんち)の訴(うった)えなどの家族(かぞく)関係(かんけい)についての紛争(ふんそう)に関(かん)する訴訟(そしょう)である「人事(じんじ)訴訟(そしょう)」(詳(くわ)しくは,「裁判(さいばん)手続(てつづき):家事(かじ)事件(じけん)について」の「第(だい)4 人事(じんじ)訴訟(そしょう)手続(てつづき)」を御覧(ごらん)ください。)と,公権力(こうけんりょく)の行使(こうし)に当(あ)たる行政(ぎょうせい)庁(ちょう)の行為(こうい)の取消(とりけ)しを求(もと)める訴訟(そしょう)などの「行政(ぎょうせい)訴訟(そしょう)」があります。

2 民事(みんじ)訴訟(そしょう)の審理(しんり)手続(てつづき)
(1) 手続(てつづき)の開始(かいし)-訴(うった)えの提起(ていき)
ア 訴(うった)えの提起(ていき)
訴(うった)えを提起(ていき)するには,原告(げんこく)又(また)はその訴訟(そしょう)代理人(だいりにん)が裁判所(さいばんしょ)に訴状(そじょう)を提出(ていしゅつ)しなければなりません。原告(げんこく)は,訴状(そじょう)に請求(せいきゅう)の趣旨(しゅし)及(およ)び原因(げんいん)を記載(きさい)し,
訴(うった)え提起(ていき)の手数料(てすうりょう)として,法律(ほうりつ)で定(さだ)められた金額(きんがく)の収入(しゅうにゅう)印紙(いんし)を貼付(てんぷ)することなどが必要(ひつよう)となります。
イ 管轄(かんかつ)
裁判所(さいばんしょ)法(ほう)及(およ)び民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)等が定(さだ)めるところにより,土地(とち)管轄(かんかつ)と事物(じぶつ)管轄(かんかつ)を有(ゆう)する裁判所(さいばんしょ)が管轄(かんかつ)裁判所(さいばんしょ)になります。
裁判所(さいばんしょ)法(ほう)によれば,
最(もっと)も下位(かい)の裁判所(さいばんしょ)は簡易裁判所(かんいさいばんしょ)で,140万(まん)円(えん)以下(いか)の請求(せいきゅう)に係(かか)る事件(じけん)について管轄(かんかつ)を有(ゆう)します。その上(うえ)の裁判所(さいばんしょ)が地方裁判所(ちほうさいばんしょ)で,一般(いっぱん)的(てき)な第(だい)一(いち)審(しん)裁判所(さいばんしょ)となります。
一方(いっぽう),民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)では,原告(げんこく)は,原則(げんそく)として,被告(ひこく)の住所(じゅうしょ)地(ち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)に訴(うった)えを提起(ていき)すべきこととされています。もっとも,付加(ふか)的(てき)な管轄(かんかつ)裁判所(さいばんしょ)も定(さだ)められています。
例(たと)えば,不法(ふほう)行為(こうい)に基(もと)づく損害(そんがい)賠償(ばいしょう)請求(せいきゅう)訴訟(そしょう)では,不法(ふほう)行為(こうい)地(ち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)に対(たい)しても訴(うった)えを提起(ていき)することができますし,
不動産(ふどうさん)に関(かん)する訴訟(そしょう)では,問題(もんだい)となる不動産(ふどうさん)の所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)にも訴(うった)えを提起(ていき)することができます。
(2) 口頭(こうとう)弁論(べんろん)等(など)
ア 訴状(そじょう)の審査(しんさ)等(など)
事件(じけん)の配(はい)てんを受(う)けた裁判官(さいばんかん)(合議(ごうぎ)体(たい)で審理(しんり)される事件(じけん)については裁判(さいばん)長(ちょう))は訴状(そじょう)を審査(しんさ)し,形式(けいしき)的(てき)に不備(ふび)がなければ,
口頭(こうとう)弁論(べんろん)期日(きじつ)を指定(してい)して当事者(とうじしゃ)を呼(よ)び出(だ)します。訴状(そじょう)に不備(ふび)があれば,裁判官(さいばんかん)(裁判(さいばん)長(ちょう))は,原告(げんこく)に対(たい)して補正(ほせい)を命(めい)じます。
イ 口頭(こうとう)弁論(べんろん)
口頭(こうとう)弁論(べんろん)は,公開(こうかい)法廷(ほうてい)において,簡易裁判所(かんいさいばんしょ)では1人(にん)の裁判官(さいばんかん)により,地方裁判所(ちほうさいばんしょ)では1人(にん)の裁判官(さいばんかん)又(また)は3人(にん)の裁判官(さいばんかん)の合議(ごうぎ)体(たい)により,高等裁判所(こうとうさいばんしょ)では原則(げんそく)として3人(にん)の裁判官(さいばんかん)の合議(ごうぎ)体(たい)により,それぞれ開(ひら)かれます。
地方裁判所(ちほうさいばんしょ)については,法律(ほうりつ)に特別(とくべつ)の規定(きてい)がない限(かぎ)り1人(にん)の裁判官(さいばんかん)が審理(しんり)することができます。もっとも,簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の裁判(さいばん)に対(たい)する控訴(こうそ)事件(じけん)は合議(ごうぎ)体(たい)で審理(しんり)しなければなりませんし,
事案(じあん)が複雑(ふくざつ)困難(こんなん)である等(など)の理由(りゆう)で合議(ごうぎ)体(たい)で審理(しんり)する旨(むね)決定(けってい)された事件(じけん)についても,合議(ごうぎ)体(たい)で審理(しんり)することになります。
口頭(こうとう)弁論(べんろん)期日(きじつ)においては,裁判(さいばん)長(ちょう)の指揮(しき)の下(した)に,公開(こうかい)法廷(ほうてい)で手続(てつづき)が行(おこな)われます。
原(げん),被告(ひこく)本人(ほんにん)又(また)はその訴訟(そしょう)代理人(だいりにん)が出頭(しゅっとう)した上(うえ),事前(じぜん)に裁判所(さいばんしょ)に提出(ていしゅつ)した準備(じゅんび)書面(しょめん)に基(もと)づいて主張(しゅちょう)を述(の)べ,主張(しゅちょう)を裏付(うらづ)けるために証拠(しょうこ)を提出(ていしゅつ)することが要求(ようきゅう)されます。
被告(ひこく)が欠席(けっせき)した場合(ばあい)には,被告(ひこく)が答弁(とうべん)書(しょ)等において原告(げんこく)の請求(せいきゅう)を争(あらそ)う意図(いと)を明(あき)らかにしていない限(かぎ)り,不利(ふり)な内容(ないよう)の判決(はんけつ)が言(い)い渡(わた)される可能(かのう)性(せい)があります。
裁判(さいばん)長(ちょう)は,当事者(とうじしゃ)の主張(しゅちょう)や立証(りっしょう)に矛盾(むじゅん)や不明確(ふめいかく)な点(てん)があれば,質問(しつもん)をしたり,次回(じかい)期日(きじつ)にその点(てん)を明(あき)らかにするよう準備(じゅんび)することを命(めい)ずることができます。
この権限(けんげん)は釈明(しゃくめい)権(けん)と呼(よ)ばれます。

民事(みんじ)合議(ごうぎ)法廷(ほうてい)
1 裁判官(さいばんかん) 2 裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)
3 裁判所(さいばんしょ)速記(そっき)官(かん) 4 廷吏(ていり)
5 原告(げんこく)代理人(だいりにん) 6 被告(ひこく)代理人(だいりにん)
ウ 争点(そうてん)及(およ)び証拠(しょうこ)の整理(せいり)手続(てつづき)
判断(はんだん)に必要(ひつよう)な事実(じじつ)関係(かんけい)について当事者(とうじしゃ)間(かん)に争(あらそ)いがあり,争点(そうてん)及(およ)び証拠(しょうこ)の整理(せいり)を行(おこな)う必要(ひつよう)がある事件(じけん)については,
裁判所(さいばんしょ)は,証人(しょうにん)尋問(じんもん)等の証拠(しょうこ)調(しら)べを争点(そうてん)に絞(しぼ)って効率(こうりつ)的(てき)かつ集中(しゅうちゅう)的(てき)に行(おこな)えるように準備(じゅんび)するため,争点(そうてん)及(およ)び証拠(しょうこ)の整理(せいり)手続(てつづき)を実施(じっし)することができます。
この手続(てつづき)としては,準備(じゅんび)的(てき)口頭(こうとう)弁論(べんろん),弁論(べんろん)準備(じゅんび)手続(てつづき),書面(しょめん)による準備(じゅんび)手続(てつづき)の3種類(しゅるい)があり,裁判所(さいばんしょ)は,事件(じけん)の性質(せいしつ)や内容(ないよう)に応(おう)じて最(もっと)も適切(てきせつ)な手続(てつづき)を選択(せんたく)することになります。準備(じゅんび)的(てき)口頭(こうとう)弁論(べんろん)は,
公開(こうかい)の法廷(ほうてい)において行(おこな)われ,争点(そうてん)等(とう)の整理(せいり)に必要(ひつよう)なあらゆる行為(こうい)をすることができる点(てん)に特色(とくしょく)があります。
弁論(べんろん)準備(じゅんび)手続(てつづき)は,法廷(ほうてい)以外(いがい)の準備(じゅんび)室(しつ)等において行(おこな)われる必(かなら)ずしも公開(こうかい)を要(よう)しない手続(てつづき)で,争点(そうてん)等の整理(せいり)のために証人(しょうにん)尋問(じんもん)をできないなどの制約(せいやく)がありますが,
一方(いっぽう)の当事者(とうじしゃ)が遠隔(えんかく)地(ち)に居住(きょじゅう)している場合(ばあい)などには,電話(でんわ)会議(かいぎ)システムによって手続(てつづき)を進(すす)めることもできます。
書面(しょめん)による準備(じゅんび)手続(てつづき)は,当事者(とうじしゃ)が遠隔(えんかく)地(ち)に居住(きょじゅう)しているときなどに,両方(りょうほう)の当事者(とうじしゃ)の出頭(しゅっとう)なしに準備(じゅんび)書面(しょめん)の提出(ていしゅつ)等(など)により争点(そうてん)等を整理(せいり)する手続(てつづき)で,必要(ひつよう)がある場合(ばあい)には電話(でんわ)会議(かいぎ)システムにより争点(そうてん)等について協議(きょうぎ)することができます。
これらの手続(てつづき)を終了(しゅうりょう)するに当(あ)たっては,裁判所(さいばんしょ)と当事者(とうじしゃ)との間(あいだ)で,その後(ご)の証拠(しょうこ)調(しら)べによって証明(しょうめい)すべき事実(じじつ)を確認(かくにん)するものとされています。
エ 証拠(しょうこ)調(しら)べ
口頭(こうとう)弁論(べんろん)又(また)は争点(そうてん)及(およ)び証拠(しょうこ)の整理(せいり)手続(てつづき)において,当事者(とうじしゃ)間(かん)の争点(そうてん)が明(あき)らかになれば,その争点(そうてん)について判断(はんだん)するために,
裁判所(さいばんしょ)は書証(しょしょう)の取調(とりしら)べ,証人(しょうにん)尋問(じんもん),当事者(とうじしゃ)尋問(じんもん)等の証拠(しょうこ)調(しら)べの手続(てつづき)を行(おこな)います。
証人(しょうにん)は,原則(げんそく)として尋問(じんもん)を申(もう)し出(で)た当事者(とうじしゃ)が最初(さいしょ)に尋問(じんもん)し,その後(ご)に相手方(あいてがた)が尋問(じんもん)することになっています。
裁判所(さいばんしょ)は,通常(つうじょう)は当事者(とうじしゃ)が尋問(じんもん)を終(お)えた後に尋問(じんもん)を行(おこな)います。もっとも,裁判(さいばん)長(ちょう)は,必要(ひつよう)があると考(かんが)えたときは,いつでも質問(しつもん)することができます。
証人(しょうにん)等(とう)の尋問(じんもん)の順序(じゅんじょ),誘導(ゆうどう)尋問(じんもん)に対(たい)する制限(せいげん)その他(ほか)の尋問(じんもん)のルールは民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)及(およ)び民事(みんじ)訴訟(そしょう)規則(きそく)に定(さだ)められていますが,
一般(いっぱん)的(てき)に言(い)って,英(えい)米(べい)法(ほう)に見(み)られるような広範(こうはん)で厳格(げんかく)な証拠(しょうこ)法則(ほうそく)は,日本(にっぽん)の制度(せいど)には存在(そんざい)しません。証拠(しょうこ)能力(のうりょく)に関(かん)する判断(はんだん)は裁判所(さいばんしょ)の裁量(さいりょう)にゆだねられていますが,
裁判所(さいばんしょ)は,基本(きほん)的(てき)に,職権(しょっけん)で証拠(しょうこ)調(しら)べをすることはできません。職権(しょっけん)で行(おこな)うことができる当事者(とうじしゃ)尋問(じんもん)はその例外(れいがい)です。
証拠(しょうこ)調(しら)べの結果(けっか)から事実(じじつ)の存否(そんぴ)を認定(にんてい)する事実(じじつ)認定(にんてい)の過程(かてい)では,証拠(しょうこ)の証明(しょうめい)力(りょく)の評価(ひょうか)は,裁判所(さいばんしょ)の裁量(さいりょう)にゆだねられています。
オ 口頭(こうとう)弁論(べんろん)調書(ちょうしょ)
口頭(こうとう)弁論(べんろん)については,立(た)ち会(あ)った裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)が調書(ちょうしょ)を作成(さくせい)しなければなりません。調書(ちょうしょ)には,法廷(ほうてい)で行(おこな)われた証人(しょうにん),鑑定(かんてい)人(じん),当事者(とうじしゃ)本人(ほんにん)の陳述(ちんじゅつ)のほか,
当事者(とうじしゃ)の主張(しゅちょう)や証拠(しょうこ)の提出(ていしゅつ)を記載(きさい)し,裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)が記名(きめい)押印(おういん)し,裁判(さいばん)長(ちょう)が認印(みとめいん)をしなければなりません。
また,裁判所(さいばんしょ)には裁判所(さいばんしょ)速記(そっき)官(かん)がおり,裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)とともに口頭(こうとう)弁論(べんろん)に立(た)ち会(あ)うことがあります。裁判所(さいばんしょ)速記(そっき)官(かん)の作成(さくせい)する速記(そっき)録(ろく)は,調書(ちょうしょ)の一部(いちぶ)として引用(いんよう)されます
(3) 訴訟(そしょう)の終了(しゅうりょう)
訴状(そじょう)の提出(ていしゅつ)により開始(かいし)された訴訟(そしょう)手続(てつづき)は,様々(さまざま)な事由(じゆう)に基(もと)づき終了(しゅうりょう)します。 最(もっと)も典型(てんけい)的(てき)な手続(てつづき)の終了(しゅうりょう)事由(じゆう)は,言(い)うまでもなく判決(はんけつ)です。
裁判所(さいばんしょ)が,証拠(しょうこ)調(しら)べを行(おこな)った後,原告(げんこく)の請求(せいきゅう)が認(みと)められる,又(また)は認(みと)められないとの心証(しんしょう)を得(え)たときは,口頭(こうとう)弁論(べんろん)を終結(しゅうけつ)して判断(はんだん)を下(くだ)します。
判断(はんだん)は,法廷(ほうてい)において,原則(げんそく)として判決(はんけつ)書(しょ)の原本(げんぽん)に基(もと)づいて言(い)い渡(わた)されます。判決(はんけつ)書(しょ)には,主文(しゅぶん),当事者(とうじしゃ)の主張(しゅちょう),判断(はんだん)の理由(りゆう)等が記載(きさい)され,言(い)い渡(わた)し後
速(すみ)やかに当事者(とうじしゃ)双方(そうほう)に送達(そうたつ)されます。
ただし,被告(ひこく)が原告(げんこく)の主張(しゅちょう)した事実(じじつ)を争(あらそ)わない場合(ばあい)など,実質(じっしつ)的(てき)に争(あらそ)いがない事件(じけん)については,判決(はんけつ)書(しょ)の原本(げんぽん)に基(もと)づかない簡易(かんい)な言(い)い渡(わた)しが可能(かのう)であり,
この場合(ばあい)には,判決(はんけつ)書(しょ)の作成(さくせい)に代(か)えて,裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)が主文(しゅぶん)等を記載(きさい)した調書(ちょうしょ)を作成(さくせい)することになります。
言(い)い渡(わた)された判決(はんけつ)は,仮(かり)執行(しっこう)宣言(せんげん)が付(ふ)された場合(ばあい)を除(のぞ)き,確定(かくてい)するまで強制(きょうせい)執行(しっこう)の手続(てつづき)をとることはできません。
訴訟(そしょう)手続(てつづき)は,訴(うった)えの取下(とりさ)げ,請求(せいきゅう)の放棄(ほうき)・認諾(にんだく),裁判(さいばん)上(じょう)の和解(わかい)によっても終了(しゅうりょう)します。これらの中(なか)で,訴(うった)えの取下(とりさ)げは基本(きほん)的(てき)に将来(しょうらい)の再(さい)訴(うた)え禁止(きんし)の効力(こうりょく)を生(しょう)じませんが,
その他(ほか)のものについては,これらの事項(じこう)を記載(きさい)した調書(ちょうしょ)は確定(かくてい)判決(はんけつ)と同一(どういつ)の効力(こうりょく)を有(ゆう)することになります。
(4) 判決(はんけつ)に対(たい)する上訴(じょうそ)ー控訴(こうそ)と上告(じょうこく)
第(だい)一(いち)審(しん)裁判所(さいばんしょ)の判決(はんけつ)に不服(ふふく)のある当事者(とうじしゃ)は,判決(はんけつ)送達(そうたつ)日(び)から2週間(しゅうかん)以内(いない)に上級(じょうきゅう)裁判所(さいばんしょ)に対(たい)して控訴(こうそ)をすることができ,第(だい)二(に)審(しん)(控訴(こうそ)審(しん))裁判所(さいばんしょ)の判決(はんけつ)に不服(ふふく)のある当事者(とうじしゃ)は,上告(じょうこく)をすることができます。
つまり,第(だい)一(いち)審(しん)の地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の判決(はんけつ)に対(たい)しては,管轄(かんかつ)を有(ゆう)する高等裁判所(こうとうさいばんしょ)に対(たい)して控訴(こうそ)することができ,第(だい)二(に)審(しん)の高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の判決(はんけつ)に対(たい)しては,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)に上告(じょうこく)することができます。
第(だい)一(いち)審(しん)の簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の判決(はんけつ)に対(たい)しては,地方裁判所(ちほうさいばんしょ)に対(たい)して控訴(こうそ)することができ,第(だい)二(に)審(しん)の地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の判決(はんけつ)に対(たい)しては,高等裁判所(こうとうさいばんしょ)に上告(じょうこく)することができます。第(だい)三(さん)審(しん)の高等裁判所(こうとうさいばんしょ)の判決(はんけつ)に対(たい)しては,
例外(れいがい)的(てき)に,憲法(けんぽう)問題(もんだい)がある場合(ばあい)には,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)に上訴(じょうそ)することができます。この上訴(じょうそ)は,「特別(とくべつ)上告(じょうこく)」と呼(よ)ばれています。
当事者(とうじしゃ)は,第(だい)一(いち)審(しん)の裁判所(さいばんしょ)の判決(はんけつ)の法律(ほうりつ)問題(もんだい)についてのみ不服(ふふく)がある場合(ばあい)には,相手方(あいてがた)の同意(どうい)を得(え)て,直接(ちょくせつ)に上告(じょうこく)をすることができます。これは,「飛躍(ひやく)上告(じょうこく)」と呼(よ)ばれています。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)においては,事件(じけん)は通常(つうじょう)5人(にん)の最高裁判所(さいこうさいばんしょ)判事(はんじ)で構成(こうせい)される小(しょう)法廷(ほうてい)で審理(しんり)されます。
しかし,憲法(けんぽう)問題(もんだい)を含(ふく)むような事件(じけん)(一定(いってい)の例外(れいがい)もあり得(え)る。)については,15人(にん)全員(ぜんいん)の最高裁判所(さいこうさいばんしょ)判事(はんじ)で構成(こうせい)される大(だい)法廷(ほうてい)で審理(しんり)されます。
控訴(こうそ)及(およ)び上告(じょうこく)については,次(つぎ)の点(てん)が特徴(とくちょう)として挙(あ)げられます。
控訴(こうそ)については,原(げん)判決(はんけつ)に不服(ふふく)がある当事者(とうじしゃ)は,常(つね)に提起(ていき)することができます。
控訴(こうそ)審(しん)では,裁判所(さいばんしょ)は第(だい)一(いち)審(しん)と同様(どうよう)の方法(ほうほう)により,事実(じじつ)認定(にんてい)を行(おこな)います。控訴(こうそ)審(しん)は,第(だい)一(いち)審(しん)裁判所(さいばんしょ)の判決(はんけつ)に対(たい)する当事者(とうじしゃ)の不服(ふふく)の限度(げんど)で,
事実(じじつ)と法律(ほうりつ)の適用(てきよう)を再度(さいど)審査(しんさ)します。口頭(こうとう)弁論(べんろん)の性格(せいかく)としては,第(だい)一(いち)審(しん)の審理(しんり)がそのまま継続(けいぞく)したものであり,第(だい)一(いち)審(しん)の審理(しんり)で行(おこな)われた手続(てつづき)は,控訴(こうそ)審(しん)でも効力(こうりょく)を有(ゆう)します。
第(だい)一(いち)審(しん)で提出(ていしゅつ)された資料(しりょう)と,控訴(こうそ)審(しん)で新(あら)たに加(くわ)えられた資料(しりょう)が,控訴(こうそ)審(しん)の判決(はんけつ)の基礎(きそ)となります。
上告(じょうこく)審(しん)は,法律(ほうりつ)問題(もんだい)に関(かん)する審理(しんり)を行(おこな)い,上告(じょうこく)審(しん)の裁判所(さいばんしょ)は,原則(げんそく)として原(げん)判決(はんけつ)で認定(にんてい)された事実(じじつ)に拘束(こうそく)されます。上告(じょうこく)審(しん)の裁判所(さいばんしょ)が最高裁判所(さいこうさいばんしょ)である場合(ばあい)には,
原(げん)判決(はんけつ)に,1.憲法(けんぽう)解釈(かいしゃく)の誤(あやま)りがあることと,2.法律(ほうりつ)に定(さだ)められた重大(じゅうだい)な訴訟(そしょう)手続(てつづき)の違反(いはん)事由(じゆう)があることが上告(じょうこく)の理由(りゆう)となります。
もっとも,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は,原(げん)判決(はんけつ)に判例(はんれい)に反(はん)する判断(はんだん)がある事件(じけん)その他(た)の法令(ほうれい)の解釈(かいしゃく)に関(かん)する重要(じゅうよう)な事項(じこう)を含(ふく)む事件(じけん)については,当事者(とうじしゃ)の上告(じょうこく)受理(じゅり)の申(もう)し立(た)てにより,上告(じょうこく)審(しん)として事件(じけん)を受理(じゅり)することができます。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は,上記(じょうき)1,2の場合(ばあい)には原(げん)判決(はんけつ)を破棄(はき)しなければならず,さらに,判決(はんけつ)に影響(えいきょう)を及(およ)ぼすことが明(あき)らかな法令(ほうれい)違反(いはん)があるときは原(げん)判決(はんけつ)を破棄(はき)することができます。
これに対(たい)し,上告(じょうこく)審(しん)の裁判所(さいばんしょ)が高等裁判所(こうとうさいばんしょ)である場合(ばあい)には,上記(じょうき)1,2の場合(ばあい)のほかに,判決(はんけつ)に影響(えいきょう)を及(およ)ぼすことが明(あき)らかな法令(ほうれい)の違反(いはん)があることも上告(じょうこく)の理由(りゆう)とされており,上告(じょうこく)の理由(りゆう)がある場合(ばあい)には原(げん)判決(はんけつ)を破棄(はき)しなければなりません。
3 訴訟(そしょう)費用(ひよう)及(およ)びその補助(ほじょ)
(1) 訴訟(そしょう)費用(ひよう)の負担(ふたん)
法律(ほうりつ)で定(さだ)められている訴訟(そしょう)費用(ひよう)は,基本(きほん)的(てき)には敗訴(はいそ)者(しゃ)が負担(ふたん)することになります。訴訟(そしょう)費用(ひよう)には,訴状(そじょう)やその他(た)の申立(もうしたて)書(しょ)に収入(しゅうにゅう)印紙(いんし)を貼付(てんぷ)して支払(しはら)われる手数料(てすうりょう)のような費用(ひよう),証人(しょうにん)の旅費(りょひ)日当(にっとう)等(など)があります。
ここでいう訴訟(そしょう)費用(ひよう)は,訴訟(そしょう)を追(つい)行(ぎょう)するのに必要(ひつよう)な全(すべ)ての費用(ひよう)を含(ふく)むわけではなく,例(たと)えば,弁護士(べんごし)費用(ひよう)は訴訟(そしょう)費用(ひよう)に含(ふく)まれません。
(2) 補助(ほじょ)の種類(しゅるい)
資力(しりょく)の乏(とぼ)しい者(もの)に対(たい)する補助(ほじょ)としては,裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)を満(み)たすため,「訴訟(そしょう)上(じょう)の救助(きゅうじょ)」に関(かん)する規定(きてい)が民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)に設(もう)けられています。この救助(きゅうじょ)は,勝訴(しょうそ)の見込(みこ)みがないとはいえない当事者(とうじしゃ)に対(たい)して適用(てきよう)されます。
それ以外(いがい)にも,財団(ざいだん)法人(ほうじん)法律(ほうりつ)扶助(ふじょ)協会(きょうかい)が実施(じっし)する「法律(ほうりつ)扶助(ふじょ)」の制度(せいど)があります。
法律(ほうりつ)扶助(ふじょ)の内容(ないよう)として訴訟(そしょう)費用(ひよう)及(およ)び弁護士(べんごし)費用(ひよう)の立替(たてかえ)等の補助(ほじょ)が行(おこな)われています。
第(だい)2 その他(ほか)の民事(みんじ)事件(じけん)とその手続(てつづき)
1 民事(みんじ)執行(しっこう)手続(てつづき)
民事(みんじ)執行(しっこう)手続(てつづき)とは,お金(かね)を貸(か)した人(ひと)(債権(さいけん)者(しゃ))の申(もう)し立(た)てによって,裁判所(さいばんしょ)がお金(かね)を返(かえ)せない人(ひと)(債務(さいむ)者(しゃ))の財産(ざいさん)を差(さ)し押(おさ)えてお金(かね)に換(か)え(換価(かんか)),債権(さいけん)者(しゃ)に分配(ぶんぱい)する(配当(はいとう))などして,債権(さいけん)者(しゃ)に債権(さいけん)を回収(かいしゅう)させる手続(てつづき)です。
民事(みんじ)執行(しっこう)手続(てつづき)には,強制(きょうせい)執行(しっこう)手続(てつづき)や担保(たんぽ)権(けん)の実行(じっこう)手続(てつづき)などがあります。
ここではまず強制(きょうせい)執行(しっこう)手続(てつづき)と担保(たんぽ)権(けん)の実行(じっこう)手続(てつづき)の違(ちが)いを説明(せつめい)し,
次(つぎ)に,民事(みんじ)執行(しっこう)手続(てつづき)の中(なか)で最(もっと)もよく利用(りよう)されている不動産(ふどうさん)執行(しっこう)手続(てつづき)と債権(さいけん)執行(しっこう)手続(てつづき)について説明(せつめい)します。

(1) 強制(きょうせい)執行(しっこう)手続(てつづき)と担保(たんぽ)権(けん)の実行(じっこう)手続(てつづき)
ア 強制(きょうせい)執行(しっこう)手続(てつづき)
強制(きょうせい)執行(しっこう)手続(てつづき)は,勝訴(しょうそ)判決(はんけつ)を得(え)たり,相手方(あいてがた)との間(あいだ)で裁判(さいばん)上(じょう)の和解(わかい)が成立(せいりつ)したにもかかわらず,
相手方(あいてがた)がお金(かね)を支払(しはら)ってくれなかったり,明(あきら)渡(わた)しをしてくれなかったりする場合(ばあい)に,
判決(はんけつ)などの債務(さいむ)名義(めいぎ)を得(え)た人(ひと)(債権(さいけん)者(しゃ))の申(もう)し立(た)てに基(もと)づいて,相手方(あいてがた)(債務(さいむ)者(しゃ))に対(たい)する請求(せいきゅう)権(けん)を,裁判所(さいばんしょ)が強制(きょうせい)的(てき)に実現(じつげん)する手続(てつづき)です。
イ 担保(たんぽ)権(けん)の実行(じっこう)手続(てつづき)
担保(たんぽ)権(けん)の実行(じっこう)手続(てつづき)は,債権(さいけん)者(しゃ)が債務(さいむ)者(しゃ)の財産(ざいさん)について抵当(ていとう)権(けん)などの担保(たんぽ)権(けん)を有(ゆう)しているときに,これを実行(じっこう)して当該(とうがい)財産(ざいさん)から満足(まんぞく)を得(え)る手続(てつづき)です。
この場合(ばあい),判決(はんけつ)などの債務(さいむ)名義(めいぎ)は不要(ふよう)であり,担保(たんぽ)権(けん)が登記(とうき)されている登記(とうき)簿(ぼ)謄本(とうほん)などが提出(ていしゅつ)されれば,裁判所(さいばんしょ)は手続(てつづき)を開始(かいし)することとなります。
なお,担保(たんぽ)権(けん)の実行(じっこう)手続(てつづき)も,強制(きょうせい)執行(しっこう)手続(てつづき)と比較(ひかく)すると,債務(さいむ)名義(めいぎ)を必要(ひつよう)とするか否(いな)かの違(ちが)いはありますが,それ以外(いがい)の手続(てつづき)はほぼ同(おな)じです。
(2) 不動産(ふどうさん)執行(しっこう)手続(てつづき)と債権(さいけん)執行(しっこう)手続(てつづき)
ア 不動産(ふどうさん)執行(しっこう)手続(てつづき)(以下(いか)は平成(へいせい)17年(ねん)4月(しがつ)1日(にち)からの手続(てつづき)です。)

申立(もうした)て
不動産(ふどうさん)執行(しっこう)の申立(もうした)て
は,書面(しょめん)でしなければなりません。申立(もうした)ては,目的(もくてき)不動産(ふどうさん)の所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する地方裁判所(ちほうさいばんしょ)(支部(しぶ)を含(ふく)む。)にします。
(wー) 開始(かいし)決定(けってい)・差押(さしおさ)え
申立(もうした)て
が適法(てきほう)にされていると認(みと)められた場合(ばあい)は,裁判所(さいばんしょ)は,不動産(ふどうさん)執行(しっこう)を始(はじ)める旨(むね)及(およ)び目的(もくてき)不動産(ふどうさん)を差(さ)し押(お)さえる旨(むね)を宣言(せんげん)する開始(かいし)決定(けってい)を行(おこな)います。
開始(かいし)決定(けってい)がされると,裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)が,管轄(かんかつ)法務局(ほうむきょく)に対(たい)して目的(もくてき)不動産(ふどうさん)の登記(とうき)簿(ぼ)に「差押(さしおさえ)」の登記(とうき)をするように嘱託(しょくたく)をします。また,債務(さいむ)者(しゃ)及(およ)び所有(しょゆう)者(しゃ)に開始(かいし)決定(けってい)正本(せいほん)を送達(そうたつ)します。
(wア) 売却(ばいきゃく)の準備(じゅんび)
裁判所(さいばんしょ)は,執行官(しっこうかん)や評価(ひょうか)人(じん)に調査(ちょうさ)を命(めい)じ,目的(もくてき)不動産(ふどうさん)について詳細(しょうさい)な調査(ちょうさ)を行(おこな)い,
買受(かいう)け希望(きぼう)者(しゃ)に閲覧(えつらん)してもらうための三(さん)点(てん)セットを作成(さくせい)します。三(さん)点(てん)セットについては,後で説明(せつめい)します。
さらに,裁判所(さいばんしょ)は,評価(ひょうか)人(じん)の評価(ひょうか)に基(もと)づいて売却(ばいきゃく)基準(きじゅん)価額(かがく)(従来(じゅうらい)の最低(さいてい)売却(ばいきゃく)価額(かがく)に相当(そうとう)するもの)を定(さだ)めます。売却(ばいきゃく)基準(きじゅん)価額(かがく)は,不動産(ふどうさん)の売却(ばいきゃく)の基準(きじゅん)となるべき価額(かがく)です。
入札(にゅうさつ)は,売却(ばいきゃく)基準(きじゅん)価額(かがく)から,その10分(ぶん)の2に相当(そうとう)する額(がく)を差(さ)し引(ひ)いた価額(かがく)(買(がい)受()可能(かのう)価額(かがく))以上(いじょう)の金額(きんがく)でしなければなりません。
(wイ) 売却(ばいきゃく)実施(じっし)
売却(ばいきゃく)の準備(じゅんび)が終(お)わると,裁判所(さいばんしょ)書記官(しょきかん)は,売却(ばいきゃく)の日時(にちじ),場所(ばしょ)のほか,売却(ばいきゃく)の方法(ほうほう)を定(さだ)めます。売却(ばいきゃく)の方法(ほうほう)はいろいろありますが,
第(だい)1回(かい)目(め)の売却(ばいきゃく)方法(ほうほう)としては,定(さだ)められた期間(きかん)内(ない)に入札(にゅうさつ)をする期間(きかん)入札(にゅうさつ)が行(おこな)われています。
売却(ばいきゃく)の情報(じょうほう)を広(ひろ)く提供(ていきょう)するため,大(だい)多数(たすう)の地方裁判所(ちほうさいばんしょ)では日刊(にっかん)新聞(しんぶん)や住宅(じゅうたく)情報(じょうほう)誌(し)などに広告(こうこく)を出(だ)しています。
また,ファクシミリサービスやインターネット上(じょう)の不動産(ふどうさん)競売(きょうばい)物件(ぶっけん)情報(じょうほう)サイトBIT等でも売却(ばいきゃく)物件(ぶっけん)の情報(じょうほう)を提供(ていきょう)しています(裁判所(さいばんしょ)により方法(ほうほう)は異(こと)なります。)。
買受(かいう)けを希望(きぼう)する方(ほう)は,広告(こうこく)などで興味(きょうみ)のある物件(ぶっけん)を見(み)つけたら,裁判所(さいばんしょ)の閲覧(えつらん)室(しつ)やBITで三(さん)点(てん)セットの閲覧(えつらん)をしてください。
三(さん)点(てん)セットとは,土地(とち)の現況(げんきょう)地目(ちもく),建物(たてもの)の種類(しゅるい)・構造(こうぞう)など,不動産(ふどうさん)の現在(げんざい)の状況(じょうきょう)のほか,
不動産(ふどうさん)を占有(せんゆう)している者(もの)やその者(もの)が占有(せんゆう)する権原(けんげん)を有(ゆう)しているかどうかなどが記載(きさい)され,
不動産(ふどうさん)の写真(しゃしん)などが添付(てんぷ)された現況(げんきょう)調査(ちょうさ)報告(ほうこく)書(しょ),競売(きょうばい)物件(ぶっけん)の周辺(しゅうへん)の環境(かんきょう)や評価(ひょうか)額(がく)が記載(きさい)され,
不動産(ふどうさん)の図面(ずめん)などが添付(てんぷ)された評価(ひょうか)書(しょ),そのまま引(ひ)き継(つ)がなければならない賃借(ちんしゃく)権(けん)などの権利(けんり)があるかどうか,
土地(とち)又(また)は建物(たてもの)だけを買(か)い受(う)けた時(とき)に建物(たてもの)のために底(そこ)地(ち)を使用(しよう)する権利(けんり)が成立(せいりつ)するかどうかなどが記載(きさい)された物件(ぶっけん)明細(めいさい)書(しょ)のそれぞれの写(うつ)しのことをいいます。
競売(きょうばい)物件(ぶっけん)の買受(かいう)けのための重要(じゅうよう)な内容(ないよう)が記載(きさい)されていますから,その内容(ないよう)をよく理解(りかい)して吟味(ぎんみ)する必要(ひつよう)があります。
さらに,現地(げんち)で不動産(ふどうさん)を,法務局(ほうむきょく)で権利(けんり)関係(かんけい)を確(たし)かめるなど,必(かなら)ず十分(じゅうぶん)な調査(ちょうさ),確認(かくにん)をするようにしてください(不動産(ふどうさん)によっては,内覧(ないらん)(見学(けんがく))が実施(じっし)されることがあります。)。
(wウ) 入札(にゅうさつ)から所有(しょゆう)権(けん)移転(いてん)まで
入札(にゅうさつ)は,公告(こうこく)書(しょ)に記載(きさい)されている保証(ほしょう)金(きん)を納付(のうふ)し,売却(ばいきゃく)基準(きじゅん)価額(かがく)から,その10分(ぶん)の2に相当(そうとう)する額(がく)を差(さ)し引(ひ)いた価額(かがく)(買受(かいう)け可能(かのう)価額(かがく))以上(いじょう)の金額(きんがく)でしなければなりません。
最高(さいこう)価(か)で落札(らくさつ)し,売却(ばいきゃく)許可(きょか)がされた買受(かいう)け人(じん)は,裁判所(さいばんしょ)が通知(つうち)する期限(きげん)までに,入札(にゅうさつ)金額(きんがく)から保証(ほしょう)金額(きんがく)を引(ひ)いた代金(だいきん)を納付(のうふ)してください。
所有(しょゆう)権(けん)移転(いてん)などの登記(とうき)の手続(てつづき)は裁判所(さいばんしょ)が行(おこな)います。ただし,手続(てつづき)に要(よう)する登録(とうろく)免許(めんきょ)税(ぜい)などの費用(ひよう)は入札(にゅうさつ)者(しゃ)の負担(ふたん)となります。
(wエ) 不動産(ふどうさん)の引渡(ひきわた)し
引(ひ)き続(つづ)いて居住(きょじゅう)する権利(けんり)を有(ゆう)する人(ひと)が住(す)んでいる場合(ばあい)には,すぐに引(ひ)き渡(わた)してもらうことはできません。
こうした権利(けんり)を主張(しゅちょう)することができない人が居住(きょじゅう)している場合(ばあい)には,この人(ひと)に明(あけ)渡(わた)しを求(もと)めることができます。この求(もと)めに応(おう)じないとしても,代金(だいきん)を納付(のうふ)してから6か月(げつ)※以内(いない)であれば,
裁判所(さいばんしょ)に申(もう)し立(た)てて,明(あけ)渡(わた)しを命(めい)じる引(ひ)き渡(わた)す命令(めいれい)を出(だ)してもらうことができます。この引(ひ)き渡(わた)す命令(めいれい)があれば,執行官(しっこうかん)に対(たい)し強制(きょうせい)的(てき)な明(あけ)渡(わた)しの手続(てつづき)をとるように申(もう)し立(た)てることもできます。
※ 買受(かいう)けの時(とき)に民法(みんぽう)395条(じょう)1項(こう)に規定(きてい)する建物(たてもの)使用(しよう)者(しゃ)が占有(せんゆう)していた建物(たてもの)の買受(かいう)け人(じん)にあっては9か月(げつ)
(wオ) 配当(はいとう)
裁判所(さいばんしょ)が,差押(さしおさえ)債権(さいけん)者(しゃ)や配当(はいとう)の要求(ようきゅう)をした他(ほか)の債権(さいけん)者(しゃ)に対(たい)し,法律(ほうりつ)上(じょう)優先(ゆうせん)する債権(さいけん)の順番(じゅんばん)に従(したが)って売却(ばいきゃく)代金(だいきん)を配(くば)る手続(てつづき)です。
原則(げんそく)として,抵当(ていとう)権(けん)を有(ゆう)している債権(さいけん)と,債務(さいむ)名義(めいぎ)しか有(ゆう)していない債権(さいけん)とでは,抵当(ていとう)権(けん)を有(ゆう)している債権(さいけん)が優先(ゆうせん)します。
また,抵当(ていとう)権(けん)を有(ゆう)している債権(さいけん)の間(あいだ)では,抵当(ていとう)権(けん)が設定(せってい)された日(ひ)の順(じゅん)に優先(ゆうせん)し,債務(さいむ)名義(めいぎ)しか有(ゆう)していない債権(さいけん)の間(あいだ)では,優先(ゆうせん)関係(かんけい)はなく,平等(びょうどう)に扱(あつか)われます。
イ 債権(さいけん)執行(しっこう)手続(てつづき)
債権(さいけん)者(しゃ)が,債務(さいむ)者(しゃ)の勤務(きんむ)する会社(かいしゃ)を第(だい)三(さん)債務(さいむ)者(しゃ)として給料(きゅうりょう)を差(さ)し押(お)さえたり,債務(さいむ)者(しゃ)の預金(よきん)のある銀行(ぎんこう)を第(だい)三(さん)債務(さいむ)者(しゃ)として銀行(ぎんこう)預金(よきん)を差(さ)し押(お)さえ,
それを直接(ちょくせつ)取(と)り立(た)てることにより,債権(さいけん)の回収(かいしゅう)をはかる手続(てつづき)です。

申(もう)し立(た)て
申(もう)し立(た)てる裁判所(さいばんしょ)は,債務(さいむ)者(しゃ)の住所(じゅうしょ)地(ち)を管轄(かんかつ)する地方裁判所(ちほうさいばんしょ)(支部(しぶ)を含(ふく)む。)ですが,
債務(さいむ)者(しゃ)の住所(じゅうしょ)地(ち)が分(わ)からないときは,差(さ)し押(お)さえたい債権(さいけん)の住所(じゅうしょ)地(ち)(例(たと)えば給料(きゅうりょう)を差(さ)し押(お)さえる場合(ばあい)は債務(さいむ)者(しゃ)の勤務(きんむ)先(さき),
銀行(ぎんこう)預金(よきん)を差(さ)し押(お)さえる場合(ばあい)はその銀行(ぎんこう)の所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する地方裁判所(ちほうさいばんしょ)(支部(しぶ)を含(ふく)む。)となります。
なお,差押(さしおさ)えの対象(たいしょう)となる債権(さいけん)が現実(げんじつ)に存在(そんざい)するかどうか,存在(そんざい)するとしてその程度(ていど)を知(し)りたい場合(ばあい)には,陳述(ちんじゅつ)催告(さいこく)の申(もう)し立(た)て(第(だい)三(さん)債務(さいむ)者(しゃ)に対(たい)して,差押(さしおさえ)債権(さいけん)の有無(うむ)などにつき回答(かいとう)を求(もと)める申(もう)し立(た)て
をすることができます。
陳述(ちんじゅつ)催告(さいこく)の申(もう)し立(た)ては,債権(さいけん)差押(さしおさえ)命令(めいれい)いと同時(どうじ)にしてください。
(wー) 差押(さしおさえ)命令(めいれい)
裁判所(さいばんしょ)は,債権(さいけん)差押(さしおさえ)命令(めいれい)申(もう)し立(た)てに理由(りゆう)があると認(みと)めるときは,差押(さしおさえ)命令(めいれい)を発(はっ)し,債務(さいむ)者(しゃ)と第(だい)三(さん)債務(さいむ)者(しゃ)に送達(そうたつ)します。
(wア) 差押(さしおさ)え
例(たと)えば給料(きゅうりょう)差押(さしおさ)えの場合(ばあい),原則(げんそく)として相手方(あいてがた)の給料(きゅうりょう)の4分(ぶん)の1(月給(げっきゅう)で44万(まん)円(えん)を超(こ)える場合(ばあい)には,33万(まん)円(えん)を除(のぞ)いた金額(きんがく))※を差(さ)し押(お)さえることができます。ただし,相手方(あいてがた)が既(すで)に退職(たいしょく)している場合(ばあい)などには,差押(さしおさ)えはできません。
(wイ) 取立(とりた)て(又(また)は配当(はいとう))
債権(さいけん)差押(さしおさえ)命令(めいれい)が債務(さいむ)者(しゃ)に送達(そうたつ)された日(ひ)から1週間(しゅうかん)を経過(けいか)したときは,債権(さいけん)者(しゃ)はその債権(さいけん)を自(みずか)ら取(と)り立(た)てることができます(ただし,第(だい)三(さん)債務(さいむ)者(しゃ)が供託(きょうたく)をした場合(ばあい)は,
裁判所(さいばんしょ)が配当(はいとう)を行(おこな)うので,直接(ちょくせつ)取(と)り立(た)てることはできません。)。
第(だい)三(さん)債務(さいむ)者(しゃ)から支払(しはらい)を受(う)けたときには,直(ただ)ちにその旨(むね)を裁判所(さいばんしょ)に届(とど)け出(で)てください。
※ 簡易裁判所(かんいさいばんしょ)の少額(しょうがく)訴訟(そしょう)手続(てつづき)で債務(さいむ)名義(めいぎ)(少額(しょうがく)訴訟(そしょう)判決(はんけつ)等(とう))を得(え)たときに限(かぎ)り,地方裁判所(ちほうさいばんしょ)以外(いがい)に,
その簡易裁判所(かんいさいばんしょ)においても金銭(きんせん)債権(さいけん)(給料(きゅうりょう),預金(よきん)等に対(たい)する強制(きょうせい)執行(しっこう)(少額(しょうがく)訴訟(そしょう)債権(さいけん)執行(しっこう))を申(もう)し立(た)てることができます。少額(しょうがく)訴訟(そしょう)債権(さいけん)執行(しっこう)の基本(きほん)的(てき)な手続(てつづき)の流(なが)れは,上記(じょうき)と同様(どうよう)です。
2 倒産(とうさん)手続(てつづき)
債務(さいむ)を負(お)った人(ひと)が経済(けいざい)的(てき)に苦(くる)しい状況(じょうきょう)になり,債権(さいけん)者(しゃ)に対(たい)する返済(へんさい)が事実(じじつ)上(じょう)できなくなったときに,債務(さいむ)者(しゃ)が立(た)ち直(なお)るための裁判(さいばん)上(じょう)の倒産(とうさん)手続(てつづき)として「破産(はさん)手続(てつづき)」や「民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)」があります。
各(かく)手続(てつづき)の内容(ないよう)については,このホームページに掲載(けいさい)されていますが,より多(おお)くの方(ほう)に知(し)っていただくため,地方裁判所(ちほうさいばんしょ)の窓口(まどぐち)に,「自己(じこ)破産(はさん)の申(もう)し立(た)てをされる方(ほう)のために」,
「再生(さいせい)手続(てつづき)開始(かいし)の申(もう)し立(た)てをされる方(ほう)のために(個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)用(よう))」というリーフレットを備(そな)え置(お)いていますので,利用(りよう)してください。また,これらの倒産(とうさん)手続(てつづき)の申(もう)し立(た)ての際(さい)には,
申立(もうしたて)書(しょ)のほかにいろいろな資料(しりょう)の提出(ていしゅつ)が必要(ひつよう)となります。必要(ひつよう)な書類(しょるい)など御(ご)不明(ふめい)な点(てん)がある場合(ばあい)には,お近(ちか)くの地方裁判所(ちほうさいばんしょ)まで気軽(きがる)にお問(と)い合(あ)わせください。
※1 平成(へいせい)16年(ねん)6月(ろくがつ)2日(にち)に新(あたら)しい破産(はさん)法(ほう)が公布(こうふ)されました。平成(へいせい)17年(ねん)1月(いちがつ)以降(いこう)の破産(はさん)手続(てつづき)の申立(もうしたて)てには,この新(あたら)しい破産(はさん)法(ほう)が適用(てきよう)されます。その主(おも)な改正(かいせい)点(てん)は以下(いか)のとおりです。
① 管轄(かんかつ)裁判所(さいばんしょ)の拡大(かくだい)
住所(じゅうしょ)が異(こと)なっていても,夫婦(ふうふ)や連帯(れんたい)債務(さいむ)者(しゃ),保証人(ほしょうにん)についての破産(はさん)事件(じけん)は,同(おな)じ裁判所(さいばんしょ)で行(おこな)えるようになりました。
② 免責(めんせき)許可(きょか)のみなし申(もう)し立(た)て
破産(はさん)手続(てつづき)の申(もう)し立(た)てがあれば,原則(げんそく)として免責(めんせき)許可(きょか)の申立(もうしたて)てもあったものとみなされるようになりました。
③ 財産(ざいさん)保全(ほぜん)制度(せいど)の拡充(かくじゅう)
破産(はさん)手続(てつづき)が開始(かいし)される前(まえ)でも,債権(さいけん)者(しゃ)からの強制(きょうせい)執行(しっこう)等を一律(いちりつ)に禁止(きんし)することもできるようになりました。
④ 配当(はいとう)までの手続(てつづき)の迅速(じんそく)化(か)
破産(はさん)管財(かんざい)人(じん)が,破産(はさん)者(しゃ)の財産(ざいさん)を処分(しょぶん)する際(さい)に必要(ひつよう)な許可(きょか)の手続(てつづき)を簡素(かんそ)化(か)したり,官報(かんぽう)公告(こうこく)のいらない簡易(かんい)な配当(はいとう)手続(てつづき)を設(もう)けることによって,迅速(じんそく)に債権(さいけん)者(しゃ)へ配当(はいとう)金(きん)を分配(ぶんぱい)できるようになりました。
⑤ 免責(めんせき)手続(てつづき)中(ちゅう)の強制(きょうせい)執行(しっこう)等の禁止(きんし)
破産(はさん)手続(てつづき)が終了(しゅうりょう)した場合(ばあい)でも,免責(めんせき)手続(てつづき)が続(つづ)いている間(あいだ)は強制(きょうせい)執行(しっこう)等(など)が禁止(きんし)されることになりました。
⑥ 名称(めいしょう)の変更(へんこう)
改正(かいせい)前(まえ)の破産(はさん)法(ほう)では「破産(はさん)の宣告(せんこく)」とされていたものが「破産(はさん)手続(てつづき)開始(かいし)の決定(けってい)」と,改正(かいせい)により名称(めいしょう)が変(か)わりました。同様(どうよう)に,「免責(めんせき)の決定(けってい)」が「免責(めんせき)許可(きょか)の決定(けってい)」と,名称(めいしょう)が変(か)わりました。
※2 この破産(はさん)法(ほう)の改正(かいせい)に伴(ともな)い,個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)の申(もう)し立(た)てができる無(む)担保(たんぽ)債務(さいむ)の総額(そうがく)が3000万(まん)円(えん)から5000万(まん)円(えん)に引(ひ)き上(あ)げられるなど,
民事(みんじ)再生(さいせい)法(ほう)の一部(いちぶ)も改正(かいせい)されました。平成(へいせい)17年(ねん)1月(いちがつ)以降(いこう)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)の申立(もうしたて)てには,この改正(かいせい)部分(ぶぶん)が適用(てきよう)されます。
(1) 破産(はさん)手続(てつづき)について
破産(はさん)手続(てつづき)は,裁判所(さいばんしょ)が破産(はさん)手続(てつづき)の開始(かいし)を決定(けってい)し,破産(はさん)管財(かんざい)人(じん)を選任(せんにん)して,その破産(はさん)管財(かんざい)人(じん)が債務(さいむ)者(しゃ)の財産(ざいさん)を金銭(きんせん)に換(か)えて債権(さいけん)者(しゃ)に配当(はいとう)する手続(てつづき)です。
通常(つうじょう)は,破産(はさん)手続(てつづき)開始(かいし)の決定(けってい)時点(じてん)の債務(さいむ)者(しゃ)の全(すべ)ての財産(ざいさん)を提出(ていしゅつ)してもらい,金銭(きんせん)に換(か)えた上(うえ)で配当(はいとう)することになります。なお,債務(さいむ)者(しゃ)の財産(ざいさん)が極(きわ)めて少(すく)ない場合(ばあい)には,破産(はさん)管財(かんざい)人(じん)を選任(せんにん)しないまま破産(はさん)手続(てつづき)を廃止(はいし)することもあります。
破産(はさん)手続(てつづき)開始(かいし)の決定(けってい)時点(じてん)の債務(さいむ)は,破産(はさん)手続(てつづき)の開始(かいし)が決定(けってい)されても,当然(とうぜん)に返済(へんさい)を免(まぬか)れるのではなく,
そのためには別(べつ)に免責(めんせき)許可(きょか)の申(もう)し立(た)てを行(おこな)い,免責(めんせき)の許可(きょか)を受(う)ける必要(ひつよう)があります。なお,破産(はさん)をすることになった事情(じじょう)に浪費(ろうひ)や詐欺(さぎ)行為(こうい)などがある場合(ばあい)には免責(めんせき)の許可(きょか)が受(う)けられないこともあります。

(2) 民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)について
民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)には,主(おも)に法人(ほうじん)事業(じぎょう)者(しゃ)を利用(りよう)対象(たいしょう)者(しゃ)とする手続(てつづき)(通常(つうじょう)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき))と,
個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)のみを利用(りよう)対象(たいしょう)者(しゃ)とする民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)(個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき))とがあります。個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)は,通常(つうじょう)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)と比(くら)べると,手続(てつづき)や費用(ひよう)等(など)について関係(かんけい)者(しゃ)の負担(ふたん)が軽(かる)くなっています。
ア 通常(つうじょう)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)
経済(けいざい)的(てき)に苦(くる)しい状況(じょうきょう)にある法人(ほうじん)や個人(こじん)(債務(さいむ)者(しゃ))が,自(みずか)ら立(た)てた再建(さいけん)計画(けいかく)(再生(さいせい)計画(けいかく))案(あん)について,債権(さいけん)者(しゃ)の多数(たすう)が同意(どうい)し,
裁判所(さいばんしょ)もその計画(けいかく)案(あん)を認(みと)めることにより,債務(さいむ)者(しゃ)の事業(じぎょう)や経済(けいざい)生活(せいかつ)の再建(さいけん)(再生(さいせい))を図(はか)ることを目的(もくてき)とした手続(てつづき)です。
債務(さいむ)者(しゃ)は,事業(じぎょう)を継続(けいぞく)しながら,再生(さいせい)計画(けいかく)のとおりに返済(へんさい)し,残(のこ)りの債務(さいむ)の免除(めんじょ)を受(う)けることになります。
また,この手続(てつづき)では,債権(さいけん)者(しゃ)等(など)の関係(かんけい)者(しゃ)にとって公平(こうへい)で透明(とうめい)なものとするために,
債務(さいむ)者(しゃ)から,財産(ざいさん)の状況(じょうきょう)などについて情報(じょうほう)の提供(ていきょう)を受(う)けたり,必要(ひつよう)に応(おう)じて債務(さいむ)者(しゃ)を監督(かんとく)する監督(かんとく)委員(いいん)や債務(さいむ)者(しゃ)に代(か)わって事業(じぎょう)経営(けいえい)を行(おこ)なう管財(かんざい)人(じん)が選任(せんにん)されたりします。
返済(へんさい)の段階(だんかい)でも,一定(いってい)の期間(きかん)は返済(へんさい)の監督(かんとく)又(また)は管理(かんり)が続(つづ)けられるほか,返済(へんさい)しなかった場合(ばあい)には,債権(さいけん)者(しゃ)が債務(さいむ)者(しゃ)の財産(ざいさん)に対(たい)して強制(きょうせい)執行(しっこう)をすることができます。

イ 個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)
個人(こじん)債務(さいむ)者(しゃ)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)は,通常(つうじょう)の民事(みんじ)再生(さいせい)手続(てつづき)を簡素(かんそ)化(か)した手続(てつづき)ですが,(1)将来(しょうらい)において継続(けいぞく)的(てき)に収入(しゅうにゅう)を得(え)る見込(みこ)みがあって,
無(む)担保(たんぽ)債務(さいむ)の総額(そうがく)が5000万(まん)円(えん)以下(いか)の人(ひと)(小規模(しょうきぼ)個人(こじん)再生(さいせい))や,(2)その中(なか)でも,サラリーマンなど将来(しょうらい)の収入(しゅうにゅう)を確実(かくじつ)かつ容易(ようい)に把握(はあく)することが可能(かのう)な人(ひと)(給与(きゅうよ)所得(しょとく)者(しゃ)等 再生(さいせい)が申(もう)し立(た)てをすることができます。
この手続(てつづき)において,債務(さいむ)者(しゃ)は,働(はたら)きながら,再生(さいせい)計画(けいかく)のとおりに返済(へんさい)し,残(のこ)りの債務(さいむ)の免除(めんじょ)を受(う)けることになります。
ただし,その再生(さいせい)計画(けいかく)の内容(ないよう)は,原則(げんそく)として3年間(ねんかん)で分割(ぶんかつ)して返済(へんさい)し,その返済(へんさい)する総額(そうがく)が,債務(さいむ)者(しゃ)が破産(はさん)手続(てつづき)を選(えら)んだ場合(ばあい)に配当(はいとう)される額(がく)を上回(うわまわ)らなければなりません。
また,無(む)担保(たんぽ)債務(さいむ)の総額(そうがく)が3000万(まん)円(えん)以下(いか)の場合(ばあい)には,
返済(へんさい)する総額(そうがく)は借金(しゃっきん)等の合計(ごうけい)額(がく)の5分(ぶん)の1(ただし,100万(まん)円(えん)以上(いじょう)300万(まん)円(えん)以下(いか)の範囲(はんい)内(ない))以上(いじょう),無(む)担保(たんぽ)債務(さいむ)の総額(そうがく)が3000万(まん)円(えん)を超(こ)え,
5000万(まん)円(えん)以下(いか)の場合(ばあい)には,返済(へんさい)する総額(そうがく)は無(む)担保(たんぽ)債務(さいむ)の総額(そうがく)の10分(ぶん)の1以上(いじょう)でなければなりません。
さらに,給与(きゅうよ)所得(しょとく)者(しゃ)等 再生(さいせい)では,それに加(くわ)えて債務(さいむ)者(しゃ)の手取(てどり)収入(しゅうにゅう)額(がく)から生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な費用(ひよう)を控除(こうじょ)した額(がく)(いわゆる可処分(かしょぶん)所得(しょとく)額(がく)。
政令(せいれい)の定(さだ)めに従(したが)って計算(けいさん)される額(がく)です。)の2年(ねん)分(ぶん)以上(いじょう)である必要(ひつよう)があります。

第(だい)3 近時(きんじ)の民事(みんじ)訴訟(そしょう)の状況(じょうきょう)と問題(もんだい)
一般(いっぱん)的(てき)に,民事(みんじ)事件(じけん)の数(かず)は社会(しゃかい)の発展(はってん)と多様(たよう)化(か)に従(したが)って増加(ぞうか)していくということができます。民事(みんじ)事件(じけん)の数(かず)は昭和(しょうわ)60年(ねん)(1985年(ねん))までは年々(ねんねん)増加(ぞうか)し,
昭和(しょうわ)62年(ねん)(1987年(ねん))ころから減少(げんしょう)傾向(けいこう)にあったものの,平成(へいせい)3年(ねん)(1991年(ねん))からは再度(さいど)増加(ぞうか)傾向(けいこう)に転(てん)じています。
それに加(くわ)え,民事(みんじ)事件(じけん)は,その数(かず)が増加(ぞうか)しているだけでなく,その内容(ないよう)も複雑(ふくざつ)化(か)しています。
近時(きんじ)裁判所(さいばんしょ)に持(も)ち込(こ)まれる事件(じけん)は,表面(ひょうめん)上(じょう)は従来(じゅうらい)のものと同(おな)じように見(み)えても,複雑(ふくざつ)に込(こ)み入(い)った最近(さいきん)の社会(しゃかい)的(てき)経済(けいざい)的(てき)な問題(もんだい)や相互(そうご)関係(かんけい)を反映(はんえい)して,多数(たすう)の微妙(びみょう)で困難(こんなん)な争点(そうてん)を含(ふく)んでいます。
このような多数(たすう)の困難(こんなん)な事件(じけん)を適正(てきせい)迅速(じんそく)に処理(しょり)することは容易(ようい)ではありませんが,このような状況(じょうきょう)を克服(こくふく)して,民事(みんじ)手続(てつづき)の促進(そくしん)を図(はか)るために,裁判官(さいばんかん)や弁護士(べんごし)が多(おお)くの努力(どりょく)をしてきました。
その結果(けっか),証拠(しょうこ)調(しら)べの前(まえ)の段階(だんかい)で当事者(とうじしゃ)間(かん)の議論(ぎろん)を通(つう)じて争点(そうてん)と証拠(しょうこ)の整理(せいり)を行(おこな)うことや,争点(そうてん)に即(そく)して集中(しゅうちゅう)的(てき)に証人(しょうにん)や当事者(とうじしゃ)の尋問(じんもん)を行(おこな)うことといった運用(うんよう)が定着(ていちゃく)しつつあります。
さらに,平成(へいせい)8年(ねん)(1996年(ねん))の6月(ろくがつ)には,民事(みんじ)訴訟(そしょう)を分(わ)かりやすく利用(りよう)しやすいものとするために,民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)が大(おお)きく改正(かいせい)され,改正(かいせい)法(ほう)は,平成(へいせい)10年(ねん)(1998年(ねん))の1月(いちがつ)に施行(しこう)されました。
平成(へいせい)13年(ねん)6月(ろくがつ)には,21世紀(せいき)における司法(しほう)のあるべき姿(すがた)を検討(けんとう)するために設置(せっち)された政府(せいふ)の司法(しほう)制度(せいど)改革(かいかく)審議(しんぎ)会(かい)が,その意見(いけん)書(しょ)において,
民事(みんじ)裁判(さいばん)制度(せいど)については,民事(みんじ)裁判(さいばん)を充実(じゅうじつ)・迅速(じんそく)化(か)すること,専門(せんもん)的(てき)知見(ちけん)を要(よう)する事件(じけん),労働(ろうどう)関係(かんけい)事件(じけん)への対応(たいおう)を強化(きょうか)することなどが課題(かだい)であるとの提言(ていげん)をしています。
同年(どうねん)7月(しちがつ),最高裁判所(さいこうさいばんしょ)に医事(いじ)関係(かんけい)訴訟(そしょう)委員(いいん)会(かい),建築(けんちく)関係(かんけい)訴訟(そしょう)委員(いいん)会(かい)が設置(せっち)されたのは,こうした提言(ていげん)に沿(そ)ったものです。
いずれにせよ,民事(みんじ)裁判(さいばん)がより適切(てきせつ)かつ効率(こうりつ)的(てき)に機能(きのう)し,変革(へんかく)する社会(しゃかい)の要請(ようせい)を満(み)たすためには,制度(せいど)を改善(かいぜん)するための絶(た)え間(ま)ない努力(どりょく)を続(つづ)ける必要(ひつよう)があるでしょう。
 ■ 意見書(いけんしょ) ■ 意見書(いけんしょ)

当会(とうかい)は,以下(いか)のとおり,貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)施行(しこう)規則(きそく)17条(じょう)1項(こう)の改正(かいせい)を求(もと)めるとともに,金融(きんゆう)庁(ちょう)が本年(ほんねん)8月(はちがつ)12日(にち)付(づ)けで公表(こうひょう)し,意見(いけん)募集(ぼしゅう)を行(おこな)っている事務(じむ)ガイドライン(第(だい)三(さん)分冊(ぶんさつ):金融(きんゆう)会社(かいしゃ)関係(かんけい))の一部(いちぶ)改正(かいせい)について,意見(いけん)を述(の)べる。
第(だい)1 意見(いけん)の趣旨(しゅし)
1 貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)施行(しこう)規則(きそく)17条(じょう)1項(こう)の改正(かいせい)について
同(どう)条項(じょうこう)を改正(かいせい)して,「貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)は,貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)19条(じょう)の帳簿(ちょうぼ)(当該(とうがい)債務(さいむ)者(しゃ)と最初(さいしょ)に貸付(かしつけ)をした時点(じてん)から全(すべ)て)を当該(とうがい)債務(さいむ)者(しゃ)が最後(さいご)に弁済(べんさい)した日(ひ)から少(すく)なくとも10年間(ねんかん)は保存(ほぞん)しなければならない。」とすべきである。
2 ガイドライン3-2-2関係(かんけい)について
(1) 同(どう)(6)の改正(かいせい)案(あん)として,「顧客(こきゃく),・・・(中略(ちゅうりゃく))・・・又(また)は顧客(こきゃく)等の代理人(だいりにん)が,弁(べん) 済(すみ)計画(けいかく)の策定(さくてい),債務(さいむ)整理(せいり)その他(た)正当(せいとう)な理由(りゆう)を示(しめ)した上(うえ)で貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に取引(とりひき)履歴(りれき)の開示(かいじ)を求(もと)めた場合(ばあい)において,これを拒(こば)むこと又(また)は虚偽(きょぎ)の回答(かいとう)を行(おこ)なうこと」が示(しめ)されているが,
「債務(さいむ)整理(せいり)」と「その他(た)正当(せいとう)な理由(りゆう)」との間(あいだ)に「,不当(ふとう)利得(りとく)返還(へんかん)請求(せいきゅう)」との文言(もんごん)を追加(ついか)すべきである。
(2) 新(あら)たに同(どう)(9)として,「顧客(こきゃく)等(とう)から受(う)けた弁済(べんさい)について貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)43条(じょう)1項(こう)の適用(てきよう)がない場合(ばあい)に,顧客(こきゃく)等(など)に対(たい)し,利息(りそく)制限(せいげん)法(ほう)所定(しょてい)の制限(せいげん)利率(りりつ)による充当(じゅうとう)計算(けいさん)を行(おこ)なった後(のち)の残存(ざんそん)債務(さいむ)額(がく)よりも過大(かだい)な請求(せいきゅう)をし,あるいは,不当(ふとう)利得(りとく)返還(へんかん)債務(さいむ)の履行(りこう)をしないこと」を追加(ついか)すべきである。
3 ガイドライン3-2-8(1)関係(かんけい)について
顧客(こきゃく)等(など)の代理人(だいりにん)である弁護士(べんごし)が開示(かいじ)の求(もと)めをする場合(ばあい)には,「債務(さいむ)者(しゃ)が債務(さいむ)の処理(しょり)を弁護士(べんごし)に委託(いたく)した旨(むね)の弁護士(べんごし)からの書面(しょめん)による通知(つうち)」(貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)21条(じょう)1項(こう)6号(ごう)参照(さんしょう))が送付(そうふ)されていれば(ファクシミリによる場合(ばあい)を含(ふく)む),本人(ほんにん)であること及(およ)び本人(ほんにん)との委任(いにん)関係(かんけい)の確認(かくにん)として十分(じゅうぶん)かつ適切(てきせつ)であるとすべきである。
第(だい)2 意見(いけん)の理由(りゆう)
1 貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)施行(しこう)規則(きそく)17条(じょう)1項(こう)改正(かいせい)について
(1) 貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が保存(ほぞん)している帳簿(ちょうぼ)は,顧客(こきゃく)の貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に対(たい)する残存(ざんそん)債務(さいむ)額(がく)や不当(ふとう)利得(りとく)返還(へんかん)請求(せいきゅう)額(がく)を確定(かくてい)するために最(もっと)も重要(じゅうよう)な証拠(しょうこ)資料(しりょう)である。
そして,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が正確(せいかく)な帳簿(ちょうぼ)に基(もと)づいて正(ただ)しく取引(とりひき)履歴(りれき)を開示(かいじ)することは,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)と顧客(こきゃく)との紛争(ふんそう)の予防(よぼう)・解決(かいけつ)に必要(ひつよう)不可欠(ふかけつ)の前提(ぜんてい)であって,顧客(こきゃく)の利益(りえき)保護(ほご)に適(かな)うものである。
そればかりか,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が正(ただ)しく取引(とりひき)履歴(りれき)を開示(かいじ)することによって,短期(たんき)的(てき)には不当(ふとう)利得(りとく)返還(へんかん)債務(さいむ)額(がく)の増大(ぞうだい)などの不利益(ふりえき)を被(こうむ)ったとしても,
全(すべ)ての取引(とりひき)履歴(りれき)を正(ただ)しく開示(かいじ)する公正(こうせい)な態度(たいど)によって国民(こくみん)の貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に対(たい)する評価(ひょうか)が高(たか)まれば,貸金(かしきん)業界(ぎょうかい)の健全(けんぜん)な発展(はってん)に資(し)するものと考(かんが)えられる。
(2) 最高裁判所(さいこうさいばんしょ)第(だい)三(さん)小(しょう)法廷(ほうてい)平成(へいせい)17年(ねん)7月(しちがつ)19日(にち)判決(はんけつ)は,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が「貸金(かしきん)業法(ぎょうほう)の適用(てきよう)を受(う)ける金銭(きんせん)消費(しょうひ)貸借(たいしゃく)契約(けいやく)の付随(ふずい)義務(ぎむ)として,
信義(しんぎ)則(そく)上(じょう),保存(ほぞん)している業務(ぎょうむ)帳簿(ちょうぼ)に基(もと)づいて取引(とりひき)履歴(りれき)を開示(かいじ)すべき義務(ぎむ)を負(お)う」との判断(はんだん)を示(しめ)したが,
このような判断(はんだん)がなされたのは,前述(ぜんじゅつ)したとおり,帳簿(ちょうぼ)及(およ)びこれに基(もと)づく取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)が貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)と顧客(こきゃく)との紛争(ふんそう)の予防(よぼう)・解決(かいけつ)にきわめて重要(じゅうよう)な役割(やくわり)を果(は)たしているからであるのは言(い)うまでもない。
ところが,遺憾(いかん)ながら,一部(いちぶ)の貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)は,現行(げんこう)の貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)施行(しこう)規則(きそく)17条(じょう)1項(こう)に基(もと)づく3年間(ねんかん)の帳簿(ちょうぼ)保存(ほぞん)期間(きかん)を自己(じこ)に有利(ゆうり)に限定(げんてい)的(てき)に解(かい)した上(うえ),
個別(こべつ)の貸付(かしつけ)債権(さいけん)が消滅(しょうめつ)してから3年間(ねんかん)が経過(けいか)すれば,次々(つぎつぎ)に帳簿(ちょうぼ)を廃棄(はいき)したり,
あるいは,廃棄(はいき)してしまったと主張(しゅちょう)したりして,顧客(こきゃく)との取引(とりひき)履歴(りれき)を不明朗(ふめいろう)化(か)することにより,利息(りそく)制限(せいげん)法(ほう)に基(もと)づく残存(ざんそん)債務(さいむ)額(がく)の確定(かくてい)や不当(ふとう)利得(りとく)返還(へんかん)請求(せいきゅう)権(けん)の行使(こうし)を困難(こんなん)にしようとしている。
しかし,最高裁(さいこうさい)は,帳簿(ちょうぼ)に基(もと)づく取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)義務(ぎむ)は保存(ほぞん)期間(きかん)を経過(けいか)した帳簿(ちょうぼ)にも及(およ)ぶものと判断(はんだん)している。貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)施行(しこう)規則(きそく)17条(じょう)1項(こう)や商法(しょうほう)上(じょう)の帳簿(ちょうぼ)保存(ほぞん)期間(きかん)を経過(けいか)していたとしても,
貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)と当該(とうがい)顧客(こきゃく)との間(あいだ)の取引(とりひき)の全(すべ)てが明(あき)らかにならなければ,当該(とうがい)紛争(ふんそう)が適正(てきせい)に解決(かいけつ)できないことからすると,当然(とうぜん)の判断(はんだん)である。
そうすると帳簿(ちょうぼ)の保存(ほぞん)期間(きかん)については,現行(げんこう)規則(きそく)の3年間(ねんかん)では短(みじか)きに失(しっ)しており,少(すく)なくとも顧客(こきゃく)の業者(ぎょうしゃ)に対(たい)する最後(さいご)の弁済(べんさい)の日(ひ)から10年間(ねんかん)(不当(ふとう)利得(りとく)返還(へんかん)請求(せいきゅう)権(けん)の消滅(しょうめつ)時効(じこう)期間(きかん))としておくことが妥当(だとう)である。
(3) また,帳簿(ちょうぼ)の保存(ほぞん)期間(きかん)の起算(きさん)点(てん)は,個別(こべつ)の債権(さいけん)が消滅(しょうめつ)した日(ひ)とするのではなく,顧客(こきゃく)が最後(さいご)の弁済(べんさい)をした日(ひ)からとすべきである。
この点(てん),包括(ほうかつ)契約(けいやく)に基(もと)づき貸付(かしつけ)及(およ)び弁済(べんさい)が複数(ふくすう)回(かい)反復(はんぷく)される場合(ばあい),借換(かりか)えが何(なん)度(ど)もなされる場合(ばあい),貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)と顧客(こきゃく)との長年(ながねん)にわたる取引(とりひき)の間(あいだ)で数日(すうじつ)から数(すう)年間(ねんかん)も取引(とりひき)が中断(ちゅうだん)する場合(ばあい)については,個別(こべつ)の貸付(かしつけ)ごとに帳簿(ちょうぼ)の保存(ほぞん)義務(ぎむ)や期間(きかん)を考慮(こうりょ)するとの考(かんが)え方(かた)もありうる。
しかし,裁判(さいばん)実務(じつむ)上(じょう)は,包括(ほうかつ)契約(けいやく)に基(もと)づく貸付(かしつけ)はリボルビング契約(けいやく)であれば一(いち)個(こ)の契約(けいやく)とみなされているし,複数(ふくすう)の契約(けいやく)と判断(はんだん)される場合(ばあい)も利息(りそく)制限(せいげん)法(ほう)上(じょう)の計算(けいさん)は一体(いったい)として取(と)り扱(あつか)う例(れい)が多(おお)い。
また,借換(かりか)えについては借換(かりか)えの前後(ぜんご)を通(つう)じて一(いち)個(こ)の契約(けいやく)と判断(はんだん)されている。
取引(とりひき)が中断(ちゅうだん)した場合(ばあい)でも,中断(ちゅうだん)前(まえ)の取引(とりひき)で発生(はっせい)した過払(かばら)い金(きん)を中断(ちゅうだん)後(ご)の貸付(かしつけ)に充当(じゅうとう)するなどして通算(つうさん)して過払(かばら)い金(きん)を計算(けいさん)する取(と)り扱(あつか)いが多(おお)い。
このような裁判(さいばん)実務(じつむ)上(じょう)の取(と)り扱(あつか)いからすると,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)と顧客(こきゃく)との紛争(ふんそう)を解決(かいけつ)するためには,
当該(とうがい)顧客(こきゃく)が最終(さいしゅう)弁済(べんさい)をした日(ひ)から10年間(ねんかん)(不当(ふとう)利得(りとく)返還(へんかん)請求(せいきゅう)権(けん)の消滅(しょうめつ)時効(じこう)期間(きかん))が経過(けいか)していない限(かぎ)り,
貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が当該(とうがい)顧客(こきゃく)と最初(さいしょ)に取引(とりひき)をしたときからの全(すべ)ての帳簿(ちょうぼ)を保存(ほぞん)しておく必要(ひつよう)性(せい)が顕著(けんちょ)である。
このように帳簿(ちょうぼ)の保存(ほぞん)期間(きかん)の起算(きさん)点(てん)を個別(こべつ)の債権(さいけん)が消滅(しょうめつ)した日(ひ)ではなく,顧客(こきゃく)が最後(さいご)に弁済(べんさい)した日(ひ)からを基準(きじゅん)にし,
かつ,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)をして当該(とうがい)顧客(こきゃく)と最初(さいしょ)に取引(とりひき)をしたときからの全(すべ)ての帳簿(ちょうぼ)を保存(ほぞん)させておくことは,
貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)19条(じょう)が貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に対(たい)し顧客(こきゃく)ごとに所定(しょてい)の事項(じこう)を記載(きさい)した帳簿(ちょうぼ)を備(そな)え付(つ)けることを求(もと)めている法(ほう)の趣旨(しゅし)にも適(かな)う。
2 取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)義務(ぎむ)違反(いはん)が行政(ぎょうせい)処分(しょぶん)の対象(たいしょう)となることの明確(めいかく)化(か)(ガイドライン3-2-2関係(かんけい))について
(1) 「貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に取引(とりひき)履歴(りれき)の開示(かいじ)義務(ぎむ)があり,正当(せいとう)な理由(りゆう)に基(もと)づく開示(かいじ)請求(せいきゅう)を拒否(きょひ)した場合(ばあい)には行政(ぎょうせい)処分(しょぶん)の対象(たいしょう)となり得(え)ることを明確(めいかく)化(か)する」との改正(かいせい)の趣旨(しゅし)には賛成(さんせい)である。
最高裁判所(さいこうさいばんしょ)第(だい)三(さん)小(しょう)法廷(ほうてい)平成(へいせい)17年(ねん)7月(しちがつ)19日(にち)判決(はんけつ)は,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が「貸金(かしきん)業法(ぎょうほう)の適用(てきよう)を受(う)ける金銭(きんせん)消費(しょうひ)貸借(たいしゃく)契約(けいやく)の付随(ふずい)義務(ぎむ)として,
信義(しんぎ)則(そく)上(じょう),保存(ほぞん)している業務(ぎょうむ)帳簿(ちょうぼ)に基(もと)づいて取引(とりひき)履歴(りれき)を開示(かいじ)すべき義務(ぎむ)を負(お)う」との判断(はんだん)を示(しめ)した。
この最高裁(さいこうさい)判決(はんけつ)を受(う)けて,金融(きんゆう)庁(ちょう)がこのたびガイドラインを改正(かいせい)して貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)義務(ぎむ)に違反(いはん)して開示(かいじ)請求(せいきゅう)を拒否(きょひ)した場合(ばあい)には行政(ぎょうせい)処分(しょぶん)の対象(たいしょう)となり得(え)ることを明確(めいかく)化(か)することは,妥当(だとう)である。
しかし,上記(じょうき)最高裁(さいこうさい)判決(はんけつ)は,債務(さいむ)者(しゃ)が債務(さいむ)内容(ないよう)を正確(せいかく)に把握(はあく)出来(でき)ない場合(ばあい)には,「弁済(べんさい)計画(けいかく)を立(た)てることが困難(こんなん)になったり,
過(か)払(ぶつ)金(きん)があるのにその返還(へんかん)を請求(せいきゅう)できないばかりか,更(さら)に弁済(べんさい)を求(もと)められてこれに応(おう)ずることを余儀(よぎ)なくされるなど,大(おお)きな不利益(ふりえき)を被(こうむ)る」ことなどに鑑(かんが)みて,取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)義務(ぎむ)が存在(そんざい)するとの結論(けつろん)を導(みちび)いている。
そうである以上(いじょう),改正(かいせい)案(あん)のうち,事務(じむ)ガイドライン3-2-2にいう取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)請求(せいきゅう)の「正当(せいとう)な理由(りゆう)」として「弁済(べんさい)計画(けいかく)の策定(さくてい),債務(さいむ)整理(せいり)」だけを例示(れいじ)し,
「過(か)払(ぶつ)金(きん)の返還(へんかん)請求(せいきゅう)」について殊更(ことさら)に言及(げんきゅう)を避(さ)けているのは,不適切(ふてきせつ)である。「過(か)払(ぶつ)金(きん)の返還(へんかん)請求(せいきゅう)」も,取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)請求(せいきゅう)の正当(せいとう)理由(りゆう)のうちに含(ふく)まれることを明記(めいき)すべきである。
(2) また,最高裁(さいこうさい)第(だい)二(に)小(しょう)法廷(ほうてい)平成(へいせい)16年(ねん)2月(にがつ)20日(にち)判決(はんけつ)は,貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)43条(じょう)が適用(てきよう)される要件(ようけん)を厳格(げんかく)に解釈(かいしゃく)し,例(たと)えば,貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)17条(じょう)1項(こう)に規定(きてい)する書面(しょめん)に該当(がいとう)するためには,当該(とうがい)書面(しょめん)に同(どう)項(こう)所定(しょてい)の事項(じこう)のすべてが記載(きさい)されていなければならないとするなど,
明確(めいかく)な判断(はんだん)を下(くだ)している。貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)においては,当該(とうがい)顧客(こきゃく)から受(う)けた弁済(べんさい)について,貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)43条(じょう)の適用(てきよう)条件(じょうけん)を満(み)たしているかどうかは,容易(ようい)に判断(はんだん)できるものであり,現(げん)に,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が顧客(こきゃく)に対(たい)し裁判(さいばん)上(じょう)の請求(せいきゅう)をする場合(ばあい)には,
利息(りそく)制限(せいげん)法(ほう)所定(しょてい)の制限(せいげん)利率(りりつ)により充当(じゅうとう)計算(けいさん)をした後の残存(ざんそん)債務(さいむ)額(がく)を訴状(そじょう)の請求(せいきゅう)の趣旨(しゅし)に記載(きさい)している実情(じつじょう)にある。
ところが,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が裁判(さいばん)外(がい)で顧客(こきゃく)等(とう)に対(たい)し支払(しはらい)を求(もと)める場合(ばあい)は,貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)43条(じょう)が適用(てきよう)されないことを承知(しょうち)であっても,
利息(りそく)制限(せいげん)法(ほう)所定(しょてい)の制限(せいげん)利率(りりつ)により充当(じゅうとう)計算(けいさん)した後の残存(ざんそん)債務(さいむ)額(がく)よりも過大(かだい)な請求(せいきゅう)をしており,
ひどい場合(ばあい)には,利息(りそく)制限(せいげん)法(ほう)上(じょう)過払(かばら)いであることを承知(しょうち)の上(うえ)で顧客(こきゃく)等に対(たい)し返済(へんさい)を求(もと)めることが常態(じょうたい)化(か)している。
利息(りそく)制限(せいげん)法(ほう)所定(しょてい)の制限(せいげん)を超過(ちょうか)した支払(しはらい)は,そもそも無効(むこう)であって,貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)43条(じょう)が適用(てきよう)される場合(ばあい)に限(かぎ)って事後(じご)的(てき)に有効(ゆうこう)とされる場合(ばあい)があるが,
同(どう)条(じょう)のみなし弁済(べんさい)が適用(てきよう)されることの主張(しゅちょう)立証(りっしょう)責任(せきにん)が貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に課(か)されていることからしても,
貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)には,同(どう)条(じょう)のみなし弁済(べんさい)が適用(てきよう)されるかどうかを的確(てきかく)に判断(はんだん)した上(うえ),もし適用(てきよう)されない場合(ばあい)には,利息(りそく)制限(せいげん)法(ほう)の範囲(はんい)内(ない)の請求(せいきゅう)に止(と)めておき,
過払(かばら)いとなった場合(ばあい)は速(すみ)やかにこれを顧客(こきゃく)に返還(へんかん)しなければならない。これを怠(おこた)った場合(ばあい)には,債権(さいけん)の管理(かんり)若(も)しくは取立(とりた)ての業務(ぎょうむ)を行(おこな)うに当(あ)たり,
偽(いつわ)りその他(た)不正(ふせい)又(また)は著(いちじる)しく不当(ふとう)な手段(しゅだん)を用(もち)いたものに該当(がいとう)するおそれが大(おお)きいものと例示(れいじ)すべきである。
3 取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)請求(せいきゅう)の際(さい)の本人(ほんにん)確認(かくにん)手続(てつづ)きの明確(めいかく)化(か)(ガイドライン3-2-8関係(かんけい))について
(1) ガイドライン改正(かいせい)案(あん)は,本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)及(およ)び委任(いにん)関係(かんけい)を示(しめ)す書類(しょるい)について,①金融(きんゆう)機関(きかん)等(とう)による顧客(こきゃく)等の本人(ほんにん)確認(かくにん)及(およ)び預金(よきん)口座(こうざ)等(とう)の不正(ふせい)な利用(りよう)の防止(ぼうし)に関(かん)する法律(ほうりつ)(以下(いか),「本人(ほんにん)確認(かくにん)法(ほう)」という)が規定(きてい)する本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)や②当該(とうがい)顧客(こきゃく)等の署名(しょめい)及(およ)び捺印(なついん)により委任(いにん)関係(かんけい)が示(しめ)されている書類(しょるい)等の提示(ていじ)を要求(ようきゅう)している。
これを現実(げんじつ)に当(あ)てはめてみると,弁護士(べんごし)が顧客(こきゃく)等から債務(さいむ)整理(せいり)の委任(いにん)を受(う)けた場合(ばあい),通常(つうじょう),数(すう)社(しゃ)から数(すう)十(じゅう)社(しゃ)の貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が相手方(あいてがた)となるが,
全国(ぜんこく)各地(かくち)に散在(さんざい)する多数(たすう)の貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に対(たい)し,本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)として運転(うんてん)免許(めんきょ)証(しょう)等の原本(げんぽん)を提示(ていじ)することは不可能(ふかのう)であり,
運転(うんてん)免許(めんきょ)証(しょう)等(とう)の写(うつ)しを送付(そうふ)することになる。この場合(ばあい),貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)として印鑑(いんかん)登録(とうろく)証明(しょうめい)書(しょ)を送付(そうふ)などすれば,どのように悪用(あくよう)されるか不安(ふあん)があり,そのようなリスクを冒(おか)すことはとてもできないであろう。
次(つぎ)に当該(とうがい)顧客(こきゃく)等の署名(しょめい)及(およ)び捺印(なついん)により委任(いにん)関係(かんけい)が示(しめ)されている書類(しょるい)を提示(ていじ)することになるが,前述(ぜんじゅつ)のように本人(ほんにん)確認(かくにん)書類(しょるい)を写(うつ)しで提出(ていしゅつ)した場合(ばあい),
印鑑(いんかん)登録(とうろく)された印鑑(いんかん)か契約(けいやく)書(しょ)に捺印(なついん)した印鑑(いんかん)により委任(いにん)状(じょう)等(とう)に捺印(なついん)する必要(ひつよう)があることになる。しかし,通常(つうじょう),
顧客(こきゃく)は多数(たすう)の貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)との取引(とりひき)をしているので,契約(けいやく)書(しょ)に捺印(なついん)した印鑑(いんかん)がどれか記憶(きおく)がないことが多(おお)く,その場合(ばあい)は,印鑑(いんかん)登録(とうろく)された印鑑(いんかん)で捺印(なついん)することになる。
結局(けっきょく)のところ,その印鑑(いんかん)が印鑑(いんかん)登録(とうろく)されていることを証明(しょうめい)するためには印鑑(いんかん)登録(とうろく)証明(しょうめい)書(しょ)を添付(てんぷ)せざるを得(え)ないことになるが,
貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)の中(なか)には添付(てんぷ)した印鑑(いんかん)登録(とうろく)証明(しょうめい)書(しょ)を悪用(あくよう)する者(もの)がないとは言(い)えないので,安易(あんい)に印鑑(いんかん)登録(とうろく)証明(しょうめい)書(しょ)を貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に送付(そうふ)することはできない。
また,このような手続(てつづき)が現実(げんじつ)になれば,印鑑(いんかん)登録(とうろく)証明(しょうめい)書(しょ)等の申請(しんせい)費用(ひよう)と手間(てま)が必要(ひつよう)になる。債務(さいむ)整理(せいり)を必要(ひつよう)とする多重(たじゅう)債務(さいむ)者(しゃ)はそもそも経済(けいざい)的(てき)に困窮(こんきゅう)している状態(じょうたい)にあり,
このような書類(しょるい)の入手(にゅうしゅ)手続(てつづき)などに不慣(ふな)れであることが多(おお)い。このため,それらの費用(ひよう)負担(ふたん)が履歴(りれき)開示(かいじ)請求(せいきゅう)の意思(いし)を挫()くことにもなりかねない。
また債権(さいけん)者(しゃ)数(すう)に応(おう)じて何(なん)枚(まい)もの委任(いにん)状(じょう)に署名(しょめい)を求(もと)めるのは,迅速(じんそく)な事務(じむ)処理(しょり)が必要(ひつよう)とされる債務(さいむ)整理(せいり)の実情(じつじょう)に合(あ)わない。
このようにガイドライン改正(かいせい)案(あん)が例示(れいじ)する手続(てつづき)は,煩雑(はんざつ)な書類(しょるい)の提示(ていじ)を条件(じょうけん)とするものであり,現在(げんざい)の実務(じつむ)慣行(かんこう)とかけ離(はな)れており,妥当(だとう)ではない。
その結果(けっか),顧客(こきゃく)等がこのように煩雑(はんざつ)な手続(てつづき)に応(おう)じられないことをもって,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)を拒否(きょひ)する口実(こうじつ)となりかねない。
むしろ,取引(とりひき)履歴(りれき)の開示(かいじ)を求(もと)めることは顧客(こきゃく)等の権利(けんり)であって,本人(ほんにん)確認(かくにん)の手続(てつづき)に伴(ともな)う負担(ふたん)が顧客(こきゃく)等による開示(かいじ)請求(せいきゅう)権(けん)の行使(こうし)を妨(さまた)げることのないよう,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)に対(たい)して注意(ちゅうい)を喚起(かんき)すべきである。
(2) ガイドライン改正(かいせい)案(あん)は,本人(ほんにん)確認(かくにん)等の方法(ほうほう)として本人(ほんにん)確認(かくにん)法(ほう)による手続(てつづき)に準拠(じゅんきょ)しており,同(どう)法(ほう)は,テロ及(およ)び組織(そしき)犯罪(はんざい)等の悪質(あくしつ)な犯罪(はんざい)行為(こうい)に対(たい)する資金(しきん)提供(ていきょう)のために
金融(きんゆう)機関(きかん)等の預金(よきん)口座(こうざ)が不正(ふせい)利用(りよう)されることを防止(ぼうし)する目的(もくてき)で,厳格(げんかく)な本人(ほんにん)確認(かくにん)の手続(てつづき)を定(さだ)めたものである(同(どう)法(ほう)1条(じょう))。
しかし,取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)請求(せいきゅう)や過(か)払()金(きん)返還(へんかん)請求(せいきゅう)が「テロ及(およ)び組織(そしき)犯罪(はんざい)等の悪質(あくしつ)な犯罪(はんざい)行為(こうい)に対(たい)する資金(しきん)提供(ていきょう)のために」悪用(あくよう)されているという社会(しゃかい)的(てき)事実(じじつ)は,およそ存在(そんざい)していない。
したがって,規制(きせい)の目的(もくてき)・対象(たいしょう)がまったく異(こと)なる本人(ほんにん)確認(かくにん)法(ほう)の定(さだ)める確認(かくにん)方法(ほうほう)を持(も)ち込(こ)むことは,誤(あやま)りであるといわざるを得(え)ない。
他方(たほう),貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が本人(ほんにん)確認(かくにん)を十分(じゅうぶん)に行(おこな)わず取引(とりひき)履歴(りれき)を第三者(だいさんしゃ)に開示(かいじ)して過(か)払(ぶつ)金(きん)を払(はら)ってしまい,このために顧客(こきゃく)等以外(いがい)の権利(けんり)が侵害(しんがい)されているというような弊害(へいがい)は,起(お)こる余地(よち)もないことである。
金融(きんゆう)機関(きかん)が保有(ほゆう)する顧客(こきゃく)情報(じょうほう)が大量(たいりょう)に盗(ぬす)まれるという近時(きんじ)多発(たはつ)するトラブルとも別(べつ)問題(もんだい)であることはいうまでもない。したがって,現在(げんざい)必要(ひつよう)なのは,
取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)に応(おう)じる際(さい)の本人(ほんにん)確認(かくにん)手続(てつづき)の「厳格(げんかく)化(か)」ではない。現在(げんざい)起(お)きているトラブルは,ごく一部(いちぶ)の貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が,
「個人(こじん)情報(じょうほう)保護(ほご)法(ほう)に基(もと)づく本人(ほんにん)確認(かくにん)手続(てつづき)」に名(な)を借(か)りて,自(みずか)らが一方(いっぽう)的(てき)に定(さだ)めた確認(かくにん)手続(てつづき)に応(おう)じなければ取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)ができないとして開示(かいじ)を拒否(きょひ)する口実(こうじつ)にしようとしている,ということである。
したがって,現在(げんざい)必要(ひつよう)なのは,取引(とりひき)履歴(りれき)の開示(かいじ)請求(せいきゅう)権(けん)は顧客(こきゃく)等(とう)の権利(けんり)であって,取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)を回避(かいひ)するための口実(こうじつ)として本人(ほんにん)確認(かくにん)手続(てつづき)を利用(りよう)してはならないことを「明確(めいかく)化(か)」することである。
(3) 個人(こじん)情報(じょうほう)保護(ほご)法(ほう)は,個人(こじん)情報(じょうほう)取扱(とりあつかい)事業(じぎょう)者(しゃ)が本人(ほんにん)からの保有(ほゆう)個人(こじん)データの開示(かいじ)の求(もと)めに応(おう)ずる手続(てつづき)を定(さだ)めることができる(同(どう)法(ほう)25条(じょう)1項(こう),29条(じょう)1項(こう)・3項(こう)・4項(こう))とするが,
「他(ほか)の法令(ほうれい)の規定(きてい)により開示(かいじ)することとされている場合(ばあい)」(同(どう)法(ほう)25条(じょう)3項(こう))を除外(じょがい)している。
しかるに前掲(ぜんけい)最高裁(さいこうさい)判決(はんけつ)は,取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)義務(ぎむ)の法的(ほうてき)根拠(こんきょ)が信義(しんぎ)則(そく)(民法(みんぽう)1条(じょう)2項(こう))にあることを明(あき)らかにした。したがって,個人(こじん)情報(じょうほう)保護(ほご)法(ほう)25条(じょう)3項(こう)により,
貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が定(さだ)めた本人(ほんにん)確認(かくにん)の手続(てつづき)によって顧客(こきゃく)等を一方(いっぽう)的(てき)に拘束(こうそく)することはできず,この手続(てつづき)に応(おう)じないことをもって取引(とりひき)履歴(りれき)開示(かいじ)請求(せいきゅう)を拒(こば)む正当(せいとう)理由(りゆう)とすることはできない。
また,個人(こじん)情報(じょうほう)保護(ほご)法(ほう)は,同(どう)法(ほう)に基(もと)づき個人(こじん)情報(じょうほう)取扱(とりあつかい)事業(じぎょう)者(しゃ)が開示(かいじ)等(とう)の求(もと)めに応(おう)じる手続(てつづき)を定(さだ)め得(え)る場合(ばあい)についても,
「本人(ほんにん)に過重(かじゅう)な負担(ふたん)を課(か)するものとならないよう配慮(はいりょ)しなければならない」(同(どう)法(ほう)29条(じょう)4項(こう))と定(さだ)めている。
個人(こじん)情報(じょうほう)保護(ほご)法(ほう)の存在(そんざい)が,自己(じこ)に関(かん)する情報(じょうほう)にアクセスする個人(こじん)の権利(けんり)を阻害(そがい)する結果(けっか)を招(まね)いてしまうのでは,本末転倒(ほんまつてんとう)だからである。
(4) 債務(さいむ)整理(せいり)の実務(じつむ)においては,「債務(さいむ)者(しゃ)が債務(さいむ)の処理(しょり)を弁護士(べんごし)に委託(いたく)した旨(むね)の弁護士(べんごし)からの書面(しょめん)による通知(つうち)」(貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)21条(じょう)1項(こう)6号(ごう)参照(さんしょう)。以下(いか),「受任(じゅにん)通知(つうち)書(しょ)」という)が債務(さいむ)者(しゃ)の代理人(だいりにん)であることの十分(じゅうぶん)かつ適切(てきせつ)な確認(かくにん)資料(しりょう)として確立(かくりつ)している。
実際(じっさい),多(おお)くの貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)は,個人(こじん)情報(じょうほう)保護(ほご)法(ほう)が施行(しこう)された現在(げんざい)においても,弁護士(べんごし)が作成(さくせい)名義(めいぎ)人(じん)である「受任(じゅにん)通知(つうち)書(しょ)」の送付(そうふ)をもって代理(だいり)権(けん)確認(かくにん)の方法(ほうほう)とすることを,従前(じゅうぜん)通(どお)り異議(いぎ)なく認(みと)めている。
弁護士(べんごし)に依頼(いらい)する多重(たじゅう)債務(さいむ)者(しゃ)は一(いち)日(にち)も早(はや)く受任(じゅにん)通知(つうち)書(しょ)を送付(そうふ)して,貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)からの直接(ちょくせつ)の取立(とりたて)行為(こうい)がない状態(じょうたい)にする必要(ひつよう)に迫(せま)られていることがほとんどであり,
受任(じゅにん)通知(つうち)書(しょ)の送付(そうふ)による実効(じっこう)性(せい)の発揮(はっき)は極(きわ)めて重要(じゅうよう)である。
弁護士(べんごし)名(めい)の「受任(じゅにん)通知(つうち)書(しょ)」を信頼(しんらい)したために貸金(かしきん)業者(ぎょうしゃ)が不正(ふせい)な開示(かいじ)請求(せいきゅう)に応(おう)じてしまったというトラブルが発生(はっせい)しているわけでもない。
あたかも弁護士(べんごし)と顧客(こきゃく)等との委任(いにん)関係(かんけい)の存在(そんざい)が疑(うたが)われる状況(じょうきょう)が広(ひろ)く存在(そんざい)していることを前提(ぜんてい)とするかのように,厳格(げんかく)な手続(てつづき)を課(か)するのは正当(せいとう)ではない。
万(まん)一(いち),弁護士(べんごし)が受任(じゅにん)通知(つうち)書(しょ)で自(みずか)らの氏名(しめい)を明(あき)らかにした上(うえ)で自(みずか)ら不正(ふせい)な開示(かいじ)請求(せいきゅう)などを行(おこな)ったりすれば,
弁護士(べんごし)職務(しょくむ)基本(きほん)規程(きてい)違反(いはん)行為(こうい)として懲戒(ちょうかい)処分(しょぶん)を受(う)けるという重大(じゅうだい)な不利益(ふりえき)を受(う)けることになるのである。
(5) 以上(いじょう)により,顧客(こきゃく)等の代理人(だいりにん)である弁護士(べんごし)が開示(かいじ)の求(もと)めをする場合(ばあい)には,「債務(さいむ)者(しゃ)が債務(さいむ)の処理(しょり)を弁護士(べんごし)に委託(いたく)した旨(むね)の弁護士(べんごし)からの書面(しょめん)による通知(つうち)」(貸金(かしきん)業(ぎょう)規制(きせい)法(ほう)21条(じょう)1項(こう)6号(ごう)参照(さんしょう))が送付(そうふ)されていれば(ファクシミリによる場合(ばあい)を含(ふく)む),
本人(ほんにん)であること及(およ)び本人(ほんにん)との委任(いにん)関係(かんけい)の確認(かくにん)として十分(じゅうぶん)かつ適切(てきせつ)であるとすべきである。
以上(いじょう)
--------------------------------------------------------------------------------
秋田(あきた)弁護士(べんごし)会(かい)
秋田(あきた)市(し)山王(さんのう)6-2-7 TEL 018(862)3770
業務(ぎょうむ)時間(じかん) 平日(へいじつ)午前(ごぜん)9時(じ)~午後(ごご)5時(じ)
 意見(いけん)書(しょ)
意見(いけん)書(しょ)

【金融(きんゆう)審議(しんぎ)会(かい)金融(きんゆう)分科(ぶんか)会(かい)第(だい)一(いち)部会(ぶかい)の「投資(とうし)サービス法(ほう)」制定(せいてい)に関(かん)する中間(ちゅうかん)整理(せいり)に対(たい)する意見(いけん)書(しょ)】
2005年(ねん)8月(はちがつ)25日(にち)
秋(あき) 田(た) 弁(べん) 護(まもる) 士(し) 会(かい)
金融(きんゆう)審議(しんぎ)会(かい)金融(きんゆう)分科(ぶんか)会(かい)第(だい)一(いち)部(ぶ)会(かい)(以下(いか)、分科(ぶんか)会(かい)という)は、本年(ほんねん)7月(しちがつ)7日(にち)、金融(きんゆう)商品(しょうひん)に関(かん)する横断(おうだん)的(てき)な規制(きせい)を内容(ないよう)とする「投資(とうし)サービス法(ほう)」制定(せいてい)に関(かん)する「中間(ちゅうかん)整理(せいり)」を公表(こうひょう)した。分科(ぶんか)会(かい)の「投資(とうし)サービス法(ほう)」制定(せいてい)に関(かん)する中間(ちゅうかん)整理(せいり)に対(たい)して、以下(いか)のとおり意見(いけん)を述(の)べる。
意見(いけん)書(しょ)の趣旨(しゅし)
1 投資(とうし)サービス法(ほう)の適用(てきよう)対象(たいしょう)(中間(ちゅうかん)整理(せいり)3~7頁(ぺーじ))
投資(とうし)サービス法(ほう)は、全(すべ)ての金融(きんゆう)商品(しょうひん)を適用(てきよう)対象(たいしょう)とすべきである。特(とく)に、国内(こくない) 公設(こうせつ)の商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)、オプションを含(ふく)む全(すべ)ての海外(かいがい)先物(さきもの)取引(とりひき)等(など)を同(どう)法(ほう)の適用(てきよう) 対象(たいしょう)とすることは不可欠(ふかけつ)である。
2 規制(きせい)内容(ないよう)について(中間(ちゅうかん)整理(せいり)10~16頁(ぺーじ))
投資(とうし)サービス法(ほう)には、最低限(さいていげん)、次(つぎ)の行為(こうい)規制(きせい)を盛(も)り込(こ)むべきである。
(1)不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)
(2)適合(てきごう)性(せい)原則(げんそく)
(3)説明(せつめい)義務(ぎむ)
3 実効(じっこう)性(せい)ある法(ほう)規制(きせい)(中間(ちゅうかん)整理(せいり)22~27頁(ぺーじ))
不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)等の前記(ぜんき)行為(こうい)規制(きせい)違反(いはん)に対(たい)しては取消(とりけし)、損害(そんがい)賠償(ばいしょう)、業務(ぎょうむ)停止(ていし)等(など)の処分(しょぶん)を盛(も)り込(こ)み、これらの実効(じっこう)性(せい)を担保(たんぽ)すべきである。
意見(いけん)の理由(りゆう)
1 上記(じょうき)1について
(1)「中間(ちゅうかん)整理(せいり)」では「利用(りよう)者(しゃ)保護(ほご)を前提(ぜんてい)に、活力(かつりょく)ある金融(きんゆう)市場(いちば)を構築(こうちく)すべく、現在(げんざい)の縦(たて)割(わ)り業法(ぎょうほう)を見直(みなお)し、幅広(はばひろ)い金融(きんゆう)商品(しょうひん)を対象(たいしょう)とした法制(ほうせい)を目指(めざ)すことが必要(ひつよう)である。」とし、
「可能(かのう)な限(かぎ)り幅広(はばひろ)い金融(きんゆう)商品(しょうひん)を対象(たいしょう)とすべきである。」としているものの、金融(きんゆう)商品(しょうひん)のなかで最(もっと)も深刻(しんこく)な消費(しょうひ)者(しゃ)被害(ひがい)を引(ひ)き起(お)こしている商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)については、投資(とうし)サービス法(ほう)の適用(てきよう)対象(たいしょう)になるのかどうか明(あき)らかでない。
同(どう)分科(ぶんか)会(かい)では、商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)の規制(きせい)官庁(かんちょう)である、経(けい)産(さん)省(しょう)、農水省(のうすいしょう)が商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)について、投資(とうし)サービス法(ほう)の適用(てきよう)対象(たいしょう)とすることに反対(はんたい)する旨(むね)表明(ひょうめい)している。
(2)商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)については、国民(こくみん)生活(せいかつ)センターによれば、年間(ねんかん)苦情(くじょう)件数(けんすう)が7000件(けん)を超(こ)えており、10年(ねん)前(まえ)の4倍(ばい)もの被害(ひがい)が引(ひ)き起(お)こされている極(きわ)めて深刻(しんこく)な事態(じたい)にあるという。
先物(さきもの)取引(とりひき)被害(ひがい)の発端(ほったん)は、業者(ぎょうしゃ)の電話(でんわ)、訪問(ほうもん)勧誘(かんゆう)など、いわゆる不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)によるものが大半(たいはん)であることが明(あき)らかになっている。従(したが)って、これを禁止(きんし)すれば、被害(ひがい)が減少(げんしょう)することは明(あき)らかである。
にもかかわらず、昨年(さくねん)行(おこな)われた商品(しょうひん)取引(とりひき)所(しょ)法(ほう)の改正(かいせい)では、不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)すら同(どう)法(ほう)に盛(も)り込(こ)むことができなかった。これに比(くら)べ、被害(ひがい)では後発(こうはつ)というべき外国(がいこく)為替(かわせ)証拠(しょうこ)金(きん)取引(とりひき)被害(ひがい)では、
外国(がいこく)為替(かわせ)証拠(しょうこ)金(きん)取引(とりひき)を適用(てきよう)対象(たいしょう)とし、不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)も盛(も)り込(こ)んだ金融(きんゆう)先物(さきもの)取引(とりひき)法(ほう)の改正(かいせい)がなされたが、その結果(けっか)、外国(がいこく)為替(かわせ)証拠(しょうこ)金(きん)取引(とりひき)被害(ひがい)はものの見事(みごと)に減少(げんしょう)していった。
また、海外(かいがい)先物(さきもの)取引(とりひき)被害(ひがい)についても、同(どう)法(ほう)はもともと政令(せいれい)指定(してい)制(せい)で、しかも先物(さきもの)取引(とりひき)以外(いがい)のオプション取引(とりひき)は適用(てきよう)対象(たいしょう)となっていないことから、同(どう)法(ほう)を潜(せん)脱(だっ)することは容易(ようい)なことであった。実際(じっさい)に、
海外(かいがい)先物(さきもの)関連(かんれん)では海外(かいがい)オプション取引(とりひき)被害(ひがい)が多(おお)く発生(はっせい)していたが、主務(しゅむ)省(しょう)である経(けい)産(さん)省(しょう)、農水省(のうすいしょう)は、海外(かいがい)先物(さきもの)規制(きせい)法(ほう)を改正(かいせい)するなどしないまま放置(ほうち)してきた。
こうした例(れい)を見(み)ると、消費(しょうひ)者(しゃ)被害(ひがい)が深刻(しんこく)な商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)、海外(かいがい)先物(さきもの)取引(とりひき)の分野(ぶんや)では、これまでの商品(しょうひん)取引(とりひき)所(しょ)法(ほう)、海外(かいがい)先物(さきもの)規制(きせい)法(ほう)及(およ)びこれらを所管(しょかん)する経(けい)産(さん)省(しょう)、
農水省(のうすいしょう)の下(した)では対処(たいしょ)できないことが明(あき)らかになり、同(どう)法(ほう)、同省(どうしょう)の規制(きせい)のやり方(かた)は破綻(はたん)していると言(い)わなければならない。
(3)現在(げんざい)投資(とうし)サービス法(ほう)が検討(けんとう)され、同(どう)法(ほう)はできるだけ金融(きんゆう)商品(しょうひん)全般(ぜんぱん)を対象(たいしょう)にし、不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)や違反(いはん)行為(こうい)に対(たい)する制裁(せいさい)を盛(も)り込(こ)もうと検討(けんとう)されているのであれば、
商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)、海外(かいがい)先物(さきもの)、オプション取引(とりひき)など全(すべ)ての金融(きんゆう)商品(しょうひん)を同(どう)法(ほう)の適用(てきよう)対象(たいしょう)とすることが、これらの被害(ひがい)を防止(ぼうし)するうえで期待(きたい)される。
(4)今回(こんかい)の中間(ちゅうかん)整理(せいり)には、被害(ひがい)が深刻(しんこく)な商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)、海外(かいがい)先物(さきもの)、海外(かいがい)商品(しょうひん)先物(さきもの)オプション取引(とりひき)について、規制(きせい)対象(たいしょう)にするのかどうか曖昧(あいまい)な表現(ひょうげん)になっている。
しかし、現(げん)に深刻(しんこく)な被害(ひがい)を引(ひ)き起(お)こしている商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)、海外(かいがい)オプション取引(とりひき)を規制(きせい)対象(たいしょう)としない法(ほう)は、「現在(げんざい)の縦(たて)割(わ)り業法(ぎょうほう)を見直(みなお)し、
幅広(はばひろ)い金融(きんゆう)商品(しょうひん)を対象(たいしょう)とした法制(ほうせい)を目指(めざ)す」投資(とうし)サービス法(ほう)の名(な)に値(あたい)しないと言(い)わなければならない。
2 上記(じょうき)2について
(1)金融(きんゆう)商品(しょうひん)の勧誘(かんゆう)にあたっては、電話(でんわ)・ファックス、訪問(ほうもん)、電子(でんし)メールによるいわゆるオプトイン型(がた)不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)を禁止(きんし)すべきである。
オプトイン型(がた)不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)は、現在(げんざい)、金融(きんゆう)先物(さきもの)取引(とりひき)法(ほう)で規定(きてい)するのみであるが、投資(とうし)に関(かん)する苦情(くじょう)、被害(ひがい)の多(おお)くは、
不(ふ)招請(しょうせい)の勧誘(かんゆう)に端(たん)を発(はっ)しているのであり、広(ひろ)く金融(きんゆう)商品(しょうひん)一般(いっぱん)について、オプトイン型(がた)不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)を採用(さいよう)すべきである。
なお、金融(きんゆう)先物(さきもの)取引(とりひき)法(ほう)においては、電話(でんわ)、訪問(ほうもん)だけが禁止(きんし)されているが、不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)には、これに加(くわ)えファックス、電子(でんし)メールも加(くわ)えるべきものであるから、投資(とうし)サービス法(ほう)の不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)にはこれらも盛(も)り込(こ)むべきである。
(2)適合(てきごう)性(せい)原則(げんそく)
知識(ちしき)、経験(けいけん)、資産(しさん)が十分(じゅうぶん)でない者(もの)に対(たい)して、金融(きんゆう)商品(しょうひん)取引(とりひき)を行(おこな)わせてはならない。既(すで)に商品(しょうひん)先物(さきもの)取引(とりひき)、
証券(しょうけん)取引(とりひき)などの分野(ぶんや)では制度(せいど)として認(みと)められているところであるが、これは、投資(とうし)取引(とりひき)一般(いっぱん)に当(あ)てはまることである。
(3)説明(せつめい)義務(ぎむ)
投資(とうし)取引(とりひき)の内容(ないよう)を十分(じゅうぶん)説明(せつめい)する必要(ひつよう)があることは言(い)うまでもないが、重要(じゅうよう)なことは、元金(がんきん)保証(ほしょう)があるのかどうか、危険(きけん)性(せい)とりわけ損(そん)をする確率(かくりつ)がどの程度(ていど)なのかなどを、顧客(こきゃく)の理解(りかい)度(ど)に応(おう)じ、わかりやすく説明(せつめい)することである。
3 上記(じょうき)3について
(1)不(ふ)招請(しょうせい)勧誘(かんゆう)禁止(きんし)等の行為(こうい)規制(きせい)を設(もう)けても、違反(いはん)に対(たい)する制裁(せいさい)等(とう)が無(な)ければ目的(もくてき)を達(たっ)しない。
(2)実効(じっこう)性(せい)を担保(たんぽ)するためには、行為(こうい)規制(きせい)違反(いはん)に対(たい)して、取消(とりけし)、損害(そんがい)賠償(ばいしょう)、 罰則(ばっそく)、行政(ぎょうせい)処分(しょぶん)等の制裁(せいさい)をそれぞれの目的(もくてき)に応(おう)じ課(か)す必要(ひつよう)がある。
 意見(いけん)書(しょ) 意見(いけん)書(しょ) 
--------------------------------------------------------------------------------
「消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)の在(あ)り方(かた)について」に対(たい)する意見(いけん)書(しょ)
2005年(ねん)(平成(へいせい)17年(ねん))8月(はちがつ)18日(にち)
自由民主党(じゆうみんしゅとう) 御中(おんちゅう)
公明党(こうめいとう) 御中(おんちゅう)
民主党(みんしゅとう) 御中(おんちゅう)
日本共産党(にほんきょうさんとう) 御中(おんちゅう)
社会民主党(しゃかいみんしゅとう) 御中(おんちゅう)
内閣(ないかく)府(ふ)国民(こくみん)生活(せいかつ)局(きょく) 御中(おんちゅう)
経済(けいざい)産業(さんぎょう)省(しょう)商務(しょうむ)流通(りゅうつう)グループ消費(しょうひ)経済(けいざい)部(ぶ)消費(しょうひ)経済(けいざい)政策(せいさく)課(か) 御中(おんちゅう)
公正(こうせい)取引(とりひき)委員(いいん)会(かい) 御中(おんちゅう)
京都(きょうと)弁護士(べんごし)会(かい)
「消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)の在(あ)り方(かた)について」に対(たい)する意見(いけん)書(しょ)
国民(こくみん)生活(せいかつ)審議(しんぎ)会(かい)消費(しょうひ)者(しゃ)政策(せいさく)部会(ぶかい)及(およ)び同(どう)部会(ぶかい)に設置(せっち)された消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)検討(けんとう)委員(いいん)会(かい)は,2005年(ねん)6月(ろくがつ)23日(にち)に,「消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)の在(あ)り方(かた)について」と題(だい)する報告(ほうこく)書(しょ)をとりまとめた。
当会(とうかい)は,同(どう)制度(せいど)の在(あ)り方(かた)について,既(すで)に2004年(ねん)3月(さんがつ)19日(にち)付(づけ)「実効(じっこう)性(せい)のある消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)の早期(そうき)実現(じつげん)を求(もと)める意見(いけん)書(しょ)」において,損害(そんがい)賠償(ばいしょう)制度(せいど)を含(ふく)めて提言(ていげん)し,
さらに,2005年(ねん)4月(しがつ)5日(にち)付(づけ)「実効(じっこう)性(せい)ある消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)に関(かん)する意見(いけん)書(しょ)」において同(どう)検討(けんとう)委員(いいん)会(かい)の議論(ぎろん)状況(じょうきょう)に基(もと)づき再度(さいど)提言(ていげん)したところである。
上記(じょうき)報告(ほうこく)書(しょ)には,当会(とうかい)が上記(じょうき)2005年(ねん)4月(しがつ)5日(にち)付(づけ)意見(いけん)書(しょ)で提言(ていげん)した内容(ないよう)が取(と)り入(い)れられていない点(てん)がある。来年(らいねん)通常(つうじょう)国会(こっかい)を目指(めざ)した立法(りっぽう)が具体(ぐたい)的(てき)に検討(けんとう)されるにあたり,
政府(せいふ)及(およ)び政党(せいとう)に対(たい)し,下記(かき)のとおり意見(いけん)を述(の)べ,消費(しょうひ)者(しゃ)被害(ひがい)の未然(みぜん)防止(ぼうし)・拡大(かくだい)防止(ぼうし)のために実効(じっこう)性(せい)ある消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)が早期(そうき)に実現(じつげん)されることを重(かさ)ねて求(もと)めるものである。
意見(いけん)の趣旨(しゅし)
1 国民(こくみん)生活(せいかつ)審議(しんぎ)会(かい)消費(しょうひ)者(しゃ)政策(せいさく)部会(ぶかい)・同(どう)消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)検討(けんとう)委員(いいん)会(かい)の2005年(ねん)6月(ろくがつ)23日(にち)付(づけ)「消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)の在(あ)り方(かた)について」と題(だい)する報告(ほうこく)書(しょ)(以下(いか),「報告(ほうこく)書(しょ)」という。)が,
消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)の導入(どうにゅう)を提言(ていげん)している点(てん)は評価(ひょうか)できるものである。
しかし,消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)が実効(じっこう)的(てき)に運用(うんよう)され,消費(しょうひ)者(しゃ)被害(ひがい)の未然(みぜん)防止(ぼうし)・拡大(かくだい)防止(ぼうし)のために機能(きのう)するには,具体(ぐたい)的(てき)内容(ないよう)において不十分(ふじゅうぶん)な点(てん)がある。
特(とく)に,下記(かき)の点(てん)は極(きわ)めて不十分(ふじゅうぶん)であり,本(ほん)制度(せいど)の実効(じっこう)性(せい)を著(いちじる)しく損(そこ)なうおそれが強(つよ)いので,法制(ほうせい)化(か)にあたって強(つよ)くその是正(ぜせい)を求(もと)める。
(1) 裁判(さいばん)管轄(かんかつ)について,事業(じぎょう)者(しゃ)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)に限(かぎ)ることなく,事業(じぎょう)者(しゃ)の不当(ふとう)な行為(こうい)がなされた地(ち),ないし,なされるおそれがある地(ち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)にも裁判(さいばん)管轄(かんかつ)を認(みと)めるべきである。
また,事業(じぎょう)者(しゃ)の営業(えいぎょう)所(しょ)の所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)にも裁判(さいばん)管轄(かんかつ)を認(みと)めるべきである。
(2) 不当(ふとう)条項(じょうこう)の「推奨(すいしょう)行為(こうい)」を差(さ)止(とめ)・撤回(てっかい)請求(せいきゅう)の対象(たいしょう)とすべきである。
(3) 差止(さしど)めの対象(たいしょう)となる実体(じったい)法規(ほうき)として,民法(みんぽう)96条(じょう),90条(じょう),借地(しゃくち)借家(しゃくや)法(ほう)の強行(きょうこう)規定(きてい)を含(ふく)めるべきである。
2 消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)以外(いがい)の法規(ほうき)に該当(がいとう)する行為(こうい)の差(さ)止(とめ)制度(せいど),損害(そんがい)賠償(ばいしょう)請求(せいきゅう)制度(せいど)についても早急(そうきゅう)に導入(どうにゅう)の検討(けんとう)をすべきである。
意見(いけん)に理由(りゆう)
1 総論(そうろん)
報告(ほうこく)書(しょ)は,消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)の導入(どうにゅう)の必要(ひつよう)性(せい)を認(みと)め,早急(そうきゅう)にこれを立法(りっぽう)することを前提(ぜんてい)に制度(せいど)設計(せっけい)を提言(ていげん)している。
同(どう)制度(せいど)の導入(どうにゅう)自体(じたい)は,事業(じぎょう)者(しゃ)に比(くら)べ情報(じょうほう)力(りょく)・交渉(こうしょう)力(りょく)に劣(おと)る消費(しょうひ)者(しゃ)が事業(じぎょう)者(しゃ)の不当(ふとう)な行為(こうい)によって被(こうむ)る被害(ひがい)の未然(みぜん)防止(ぼうし)・拡大(かくだい)防止(ぼうし)に有効(ゆうこう)で,極(きわ)めて画期的(かっきてき)であり評価(ひょうか)できる。
しかし,その具体(ぐたい)的(てき)な内容(ないよう)については,裁判(さいばん)管轄(かんかつ)が狭(せば)められていること,不当(ふとう)条項(じょうこう)の「推奨(すいしょう)行為(こうい)」を差止(さしど)めの対象(たいしょう)としていないこと,
差止(さしど)めの対象(たいしょう)となる実体(じったい)法規(ほうき)に民法(みんぽう)等を含(ふく)まないこと等(とう),消費(しょうひ)者(しゃ)被害(ひがい)の未然(みぜん)防止(ぼうし)・拡大(かくだい)防止(ぼうし)の観点(かんてん)から不十分(ふじゅうぶん)な点(てん)がある。
とりわけ裁判(さいばん)管轄(かんかつ)について事業(じぎょう)者(しゃ)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)の他(ほか),不当(ふとう)行為(こうい)がなされた地(ち)などに管轄(かんかつ)を認(みと)めるべきことを示(しめ)していない点(てん)は,
本(ほん)制度(せいど)の実効(じっこう)性(せい)を著(いちじる)しく制約(せいやく)する重大(じゅうだい)な問題(もんだい)点(てん)である。また,その他(ほか)にも不十分(ふじゅうぶん)な点(てん)があるので,以下(いか)報告(ほうこく)書(しょ)の各(かく)項目(こうもく)ごとに当会(とうかい)の意見(いけん)を述(の)べる。
2 管轄(かんかつ)裁判所(さいばんしょ)の決定(けってい)について
報告(ほうこく)書(しょ)は,「管轄(かんかつ)裁判所(さいばんしょ)の決定(けってい)」(報告(ほうこく)書(しょ)24ページ)については,「事業(じぎょう)者(しゃ)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)を基本(きほん)とする」とし,
事業(じぎょう)者(しゃ)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)の他(ほか),営業(えいぎょう)所(しょ)等の所在地(しょざいち),不当(ふとう)な行為(こうい)が行(おこな)われた地(ち)に管轄(かんかつ)を認(みと)めることが明示(めいじ)されていないが,これでは極(きわ)めて不都合(ふつごう)であり,強(つよ)く反対(はんたい)である。
そもそも,報告(ほうこく)書(しょ)がここで挙(あ)げる理由(りゆう)は,いずれも普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)を基本(きほん)とすることの理由(りゆう)としては不適当(ふてきとう)なものであり,
これらから普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)所在地(しょざいち)の裁判(さいばん)管轄(かんかつ)を基本(きほん)とすることが導(みちび)かれるわけではない。
本(ほん)制度(せいど)が有効(ゆうこう)に機能(きのう)するためには,事業(じぎょう)者(しゃ)が不当(ふとう)な行為(こうい)を行(おこな)い,または,行(おこな)うおそれのある地(ち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)にも土地(とち)管轄(かんかつ)を是非(ぜひ)とも認(みと)めるべきである。
勧誘(かんゆう)行為(こうい)を行(おこな)い,契約(けいやく)を締結(ていけつ)している場所(ばしょ)は,当該(とうがい)事業(じぎょう)者(しゃ)が活動(かつどう)を実際(じっさい)に行(おこな)っている場所(ばしょ)である。この場合(ばあい),被害(ひがい)は事業(じぎょう)活動(かつどう)を行(おこな)っている地(ち)で発生(はっせい)しており,
不当(ふとう)勧誘(かんゆう)や不当(ふとう)契約(けいやく)条項(じょうこう)使用(しよう)の証拠(しょうこ)も事業(じぎょう)活動(かつどう)を行(おこな)っている地(ち)に存在(そんざい)する。
また,事業(じぎょう)者(しゃ)が当該(とうがい)地(ち)で事業(じぎょう)展開(てんかい)する以上(いじょう),
展開(てんかい)した地域(ちいき)での応訴(おうそ)の負担(ふたん)を被(こうむ)るのはむしろ当然(とうぜん)なことである。また,実際(じっさい)には,個別(こべつ)消費(しょうひ)者(しゃ)からの個別(こべつ)訴訟(そしょう)も提起(ていき)されるはずであり,
それは金銭(きんせん)の給付(きゅうふ)訴訟(そしょう)が多(おお)いであろうから,実際(じっさい)上(うえ),被害(ひがい)消費(しょうひ)者(しゃ)のいる地(ち)で同一(どういつ)論点(ろんてん)について応訴(おうそ)をせざるをえないのである。
従(したが)って,不当(ふとう)行為(こうい)が行(おこな)われる地(ち)に管轄(かんかつ)を認(みと)めても,事業(じぎょう)者(しゃ)にとって特(とく)に不合理(ふごうり)な負担(ふたん)というわけではない。
実際(じっさい)上(うえ)も,地方(ちほう)の担当(たんとう)者(しゃ)が行(おこな)った勧誘(かんゆう)で地方(ちほう)の消費(しょうひ)者(しゃ)が被害(ひがい)を被(こうむ)っている場合(ばあい),当該(とうがい)地方(ちほう)で審理(しんり)するのが合理(ごうり)的(てき)であるが,
本店(ほんてん)が別(べつ)の地(ち)にあるために,担当(たんとう)者(しゃ)も被害(ひがい)消費(しょうひ)者(しゃ)も本店(ほんてん)所在地(しょざいち)に赴(おもむ)き審理(しんり)するべきとするのは,消費(しょうひ)者(しゃ)や消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)に過大(かだい)な負担(ふたん)を強(し)いるものであり,不合理(ふごうり)であることは明(あき)らかである。
以上(いじょう)からすれば,審理(しんり)の都合(つごう)からも,当事者(とうじしゃ)の負担(ふたん)の観点(かんてん)からも,事業(じぎょう)者(しゃ)の行為(こうい)地(ち)にも土地(とち)管轄(かんかつ)を認(みと)めるべきである。
また,事業(じぎょう)者(しゃ)の営業(えいぎょう)所(しょ)所在地(しょざいち)を管轄(かんかつ)する裁判所(さいばんしょ)には,応訴(おうそ)の負担(ふたん)を負(お)わせるのが妥当(だとう)と考(かんが)えられ,事業(じぎょう)者(しゃ)の営業(えいぎょう)所(しょ)所在地(しょざいち)にも管轄(かんかつ)が認(みと)められるべきである。
さらに,民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)が規定(きてい)する管轄(かんかつ)よりも狭(せま)く,事業(じぎょう)者(しゃ)の普通(ふつう)裁判(さいばん)籍(せき)の所在地(しょざいち)のみに管轄(かんかつ)を認(みと)めるのは,あまりに事業(じぎょう)者(しゃ)の都合(つごう)のみを重視(じゅうし)した不合理(ふごうり)な案(あん)である。少(すく)なくとも,民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)どおりの裁判(さいばん)管轄(かんかつ)が認(みと)められるべきである。
3 推奨(すいしょう)行為(こうい)について
報告(ほうこく)書(しょ)では,「いわゆる『推奨(すいしょう)行為(こうい)』」(他(ほか)の事業(じぎょう)者(しゃ)ないし事業(じぎょう)者(しゃ)団体(だんたい)等が,事業(じぎょう)者(しゃ)に対(たい)して,当該(とうがい)事業(じぎょう)者(しゃ)が消費(しょうひ)者(しゃ)との間(あいだ)で締結(ていけつ)する契約(けいやく)において特定(とくてい)の契約(けいやく)条項(じょうこう)につき妥当(だとう)なものとして
その使用(しよう)を勧(すす)める行為(こうい))を差止(さしど)め等の対象(たいしょう)とすることにつき「慎重(しんちょう)に検討(けんとう)する必要(ひつよう)がある」とされているが(報告(ほうこく)書(しょ)9ページ),推奨(すいしょう)行為(こうい)は是非(ぜひ)とも差止(さしど)め等の対象(たいしょう)とすべきである。
報告(ほうこく)書(しょ)は,事業(じぎょう)者(しゃ)団体(だんたい)による自主(じしゅ)ルール作(づく)りへの萎縮(いしゅく)効果(こうか)の懸念(けねん)を挙(あ)げるが,
これらは何(なん)ら具体(ぐたい)的(てき)なものではなく,却(かえ)って,事業(じぎょう)者(しゃ)団体(だんたい)の作成(さくせい)したルールに従(したが)ったのみの中小(ちゅうしょう)企業(きぎょう)に応訴(おうそ)の負担(ふたん)を負(お)わせることの方(ほう)が極(きわ)めて不都合(ふつごう)である。
事業(じぎょう)者(しゃ)ないし事業(じぎょう)者(しゃ)団体(だんたい)が不当(ふとう)な約款(やっかん)の推奨(すいしょう)を行(おこな)っていた事例(じれい)は過去(かこ)にも数多(かずおお)く見(み)られる(銀行(ぎんこう)取引(とりひき)約款(やっかん)のひな形(かたち),建物(たてもの)賃貸借(ちんたいしゃく)契約(けいやく)の原状(げんじょう)回復(かいふく)条項(じょうこう)など)。
また,ドイツ,イギリス,オランダ等(とう)の外国(がいこく)法制(ほうせい)でも推奨(すいしょう)行為(こうい)の差(さ)止(とめ)ないし撤回(てっかい)(推奨(すいしょう)受領(じゅりょう)者(しゃ)に対(たい)して条項(じょうこう)が無効(むこう)であることを通知(つうち)することなど)請求(せいきゅう)が認(みと)められている。このような実態(じったい)や海外(かいがい)法制(ほうせい)に鑑(かんが)みると,
少(すく)なくとも事業(じぎょう)者(しゃ)及(およ)び事業(じぎょう)者(しゃ)団体(だんたい)の推奨(すいしょう)行為(こうい)は差(さ)止(とめ)・撤回(てっかい)請求(せいきゅう)の対象(たいしょう)とすべきである。
4 差止(さしど)めの対象(たいしょう)とすべき実体(じったい)法(ほう)の規定(きてい)について
報告(ほうこく)書(しょ)は,差止(さしど)めの対象(たいしょう)とすべき実体(じったい)法規(ほうき)として,「消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)を基本(きほん)とする」としている(報告(ほうこく)書(しょ)6ページ)。
確(たし)かに,当面(とうめん)の立法(りっぽう)として消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)が差止(さしど)めの対象(たいしょう)となる実体(じったい)法規(ほうき)の中心(ちゅうしん)であることについては異論(いろん)はない。
しかし,消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)が消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)の代表(だいひょう)として差(さ)し止(と)めるべき事案(じあん)は,同(どう)法(ほう)違反(いはん)に尽(つ)きるものではない。この点(てん)について報告(ほうこく)書(しょ)が民法(みんぽう)及(およ)び商法(しょうほう)について「慎重(しんちょう)に検討(けんとう)する必要(ひつよう)がある」としている点(てん)はとりわけ不十分(ふじゅうぶん)である。
少(すく)なくとも,民法(みんぽう)の詐欺(さぎ),強迫(きょうはく)行為(こうい),公序良俗(こうじょりょうぞく)違反(いはん)は消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)が規定(きてい)する行為(こうい)よりも悪質(あくしつ)な行為(こうい)であり,
その要件(ようけん)判断(はんだん)についても消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)より困難(こんなん)というわけではなく明確(めいかく)性(せい)に欠(か)けるところはないから,差止(さしど)めの対象(たいしょう)とすべきある。
また,借地(しゃくち)借家(しゃくや)法(ほう)も消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)の特別(とくべつ)法的(ほうてき)なものであり,要件(ようけん)判断(はんだん)は明確(めいかく)であるから差止(さしど)めの対象(たいしょう)とすべきである。
なお,報告(ほうこく)書(しょ)が,不当(ふとう)な契約(けいやく)条項(じょうこう)の使用(しよう)のみならず事業(じぎょう)者(しゃ)の不当(ふとう)な勧誘(かんゆう)行為(こうい)を差止(さしど)めの対象(たいしょう)としていることは(報告(ほうこく)書(しょ)8ページ),深刻(しんこく)な被害(ひがい)実態(じったい)に鑑(かんが)みて適切(てきせつ)である。
5 今後(こんご)の緊急(きんきゅう)課題(かだい)
(1)報告(ほうこく)書(しょ)の「消費(しょうひ)者(しゃ)被害(ひがい)の損害(そんがい)賠償(ばいしょう)請求(せいきゅう)について」の項(こう)では(報告(ほうこく)書(しょ)4ページ),消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)が個々(ここ)の被害(ひがい)者(しゃ)に代(か)わって損害(そんがい)賠償(ばいしょう)請求(せいきゅう)する制度(せいど)の導入(どうにゅう)について,
「慎重(しんちょう)に検討(けんとう)されるべきである」とされている。しかし,近年(きんねん)の消費(しょうひ)者(しゃ)被害(ひがい)の急増(きゅうぞう)や,報告(ほうこく)書(しょ)が理由(りゆう)としている選定(せんてい)当事者(とうじしゃ)制度(せいど)が決(けっ)して有効(ゆうこう)に機能(きのう)しているとはいえない実情(じつじょう)等からすれば,
消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)が個々(ここ)の被害(ひがい)者(しゃ)に代(か)わって損害(そんがい)賠償(ばいしょう)請求(せいきゅう)する制度(せいど)は,
消費(しょうひ)者(しゃ)被害(ひがい)救済(きゅうさい)にとって是非(ぜひ)とも実現(じつげん)されるべき重大(じゅうだい)な課題(かだい)である。今回(こんかい)の検討(けんとう)委員(いいん)会(かい)では,スケジュールの関係(かんけい)で早々(そうそう)に検討(けんとう)外(がい)とされてしまったが,
引(ひ)き続(つづ)き緊急(きんきゅう)な課題(かだい)として実現(じつげん)に向(む)けた検討(けんとう)が必要(ひつよう)である。
また,消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)による,消費(しょうひ)者(しゃ)個々(ここ)の損害(そんがい)賠償(ばいしょう)請求(せいきゅう)権(けん)を前提(ぜんてい)としない,事業(じぎょう)者(しゃ)の不当(ふとう)な行為(こうい)によって得(え)られた不当(ふとう)な利益(りえき)の剥奪(はくだつ)を請求(せいきゅう)する制度(せいど)の実現(じつげん)(当会(とうかい)2004年(ねん)意見(いけん)書(しょ)で提言(ていげん)。
ドイツ不正(ふせい)競争(きょうそう)防止(ぼうし)法(ほう)は不当(ふとう)利益(りえき)剥奪(はくだつ)請求(せいきゅう)権(けん)の条項(じょうこう)を設(もう)けている)も必要(ひつよう)であると考(かんが)えられるが,
報告(ほうこく)書(しょ)はこれに対(たい)しても「慎重(しんちょう)な検討(けんとう)が必要(ひつよう)」としている(報告(ほうこく)書(しょ)8~9ページ)。
しかし,真(しん)に事業(じぎょう)者(しゃ)の不当(ふとう)な行為(こうい)を抑制(よくせい)するためには,差(さ)止(とめ)請求(せいきゅう)だけでなく,このような不当(ふとう)な利益(りえき)の剥奪(はくだつ)制度(せいど)が必要(ひつよう)不可欠(ふかけつ)であり,同(おな)じく緊急(きんきゅう)な検討(けんとう)がなされるべきである。
(2)また,今回(こんかい)は十分(じゅうぶん)な検討(けんとう)が行(おこな)われなかったものの,当会(とうかい)2004年(ねん)意見(いけん)書(しょ)で提言(ていげん)している,特定(とくてい)商取引(しょうとりひき)法(ほう)や各種(かくしゅ)業法(ぎょうほう)等(とう)に定(さだ)める強行(きょうこう)規定(きてい)(宅地(たくち)建物(たてもの)取引(とりひき)業法(ぎょうほう)など)により
無効(むこう)である条項(じょうこう)を使用(しよう)する行為(こうい)及(およ)び下記(かき)の勧誘(かんゆう)行為(こうい)についても差止(さしど)めの対象(たいしょう)として早急(そうきゅう)に検討(けんとう)する必要(ひつよう)がある。
(1) 特定(とくてい)商取引(しょうとりひき)法(ほう)によって禁止(きんし)されている行為(こうい)
(2) 独占(どくせん)禁止(きんし)法(ほう)によって禁止(きんし)されている行為(こうい)
(3) 不当(ふとう)景品(けいひん)類(るい)及(およ)び不当(ふとう)表示(ひょうじ)防止(ぼうし)法(ほう)によって禁止(きんし)されている行為(こうい)
(4) 消費(しょうひ)者(しゃ)を威迫(いはく)する言動(げんどう)
(5) 消費(しょうひ)者(しゃ)の私生活(しせいかつ)または業務(ぎょうむ)の平穏(へいおん)を害(がい)する言動(げんどう)
(6) 消費(しょうひ)者(しゃ)の知識(ちしき)や判断(はんだん)力(りょく)が不足(ふそく)している状況(じょうきょう)を利用(りよう)する行為(こうい)
(7) その他(た)信義(しんぎ)誠実(せいじつ)の原則(げんそく)に反(はん)する不当(ふとう)な勧誘(かんゆう)行為(こうい)
6 その他(ほか)の論点(ろんてん)について
(1)「消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)」の利益(りえき)を擁護(ようご)することを目的(もくてき)としていることについて
報告(ほうこく)書(しょ)が,消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)を,消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)の利益(りえき)を擁護(ようご)するため,
一定(いってい)要件(ようけん)を充足(じゅうそく)した消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)に対(たい)して民事(みんじ)実体(じったい)法(ほう)上(じょう)の請求(せいきゅう)権(けん)を認(みと)める制度(せいど)としていること(報告(ほうこく)書(しょ)5ページ)は,妥当(だとう)といえる。
但(ただ)し,ここで「消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)」としているのは,特定(とくてい)の消費(しょうひ)者(しゃ)の利益(りえき)のためだけではないという趣旨(しゅし)と解(かい)されるから,「消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)」という表現(ひょうげん)から不当(ふとう)な要件(ようけん)が導(みちび)かれないように留意(りゅうい)する必要(ひつよう)がある。
報告(ほうこく)書(しょ)8ページの「具体(ぐたい)的(てき)に差(さ)止(とめ)請求(せいきゅう)の対象(たいしょう)とすべき行為(こうい)等」において,
「消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)の利益(りえき)に影響(えいきょう)を及(およ)ぼす可能(かのう)性(せい)がある場合(ばあい)に差止(さしど)めを認(みと)める必要(ひつよう)がある」とされていることについては,
差止(さしど)めの対象(たいしょう)行為(こうい)は,消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)に該当(がいとう)する違法(いほう)であると評価(ひょうか)される行為(こうい)であり,差止(さしど)めの対象(たいしょう)の要件(ようけん)としてはそれで十分(じゅうぶん)である。
「消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)の利益(りえき)に影響(えいきょう)を及(およ)ぼす可能(かのう)性(せい)があること」を要件(ようけん)とすれば,差止(さしど)めの範囲(はんい)が不当(ふとう)に制限(せいげん)され,被害(ひがい)の未然(みぜん)防止(ぼうし)・拡大(かくだい)防止(ぼうし)という制度(せいど)趣旨(しゅし)に反(はん)する。
「適格(てきかく)消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)の要件(ようけん)の在(あ)り方(かた)」のうち「団体(だんたい)の目的(もくてき)」についても,報告(ほうこく)書(しょ)では,適格(てきかく)消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)の要件(ようけん)として,
定款(ていかん)等に団体(だんたい)の目的(もくてき)として「『消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)』の利益(りえき)擁護(ようご)」が掲(かか)げられている必要(ひつよう)があるとされているが(報告(ほうこく)書(しょ)11ページ),上記(じょうき)のとおり,
「消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)」の意味(いみ)は特定(とくてい)の消費(しょうひ)者(しゃ)利益(りえき)のみをはからないという趣旨(しゅし)と解(かい)すべきであるから,このことから不当(ふとう)に適格(てきかく)団体(だんたい)が限定(げんてい)されないよう留意(りゅうい)すべきである。
(2)「適格(てきかく)消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)の要件(ようけん)の在(あ)り方(かた)」のうち「団体(だんたい)の目的(もくてき)」について
報告(ほうこく)書(しょ)は,「団体(だんたい)の構成(こうせい)員(いん)の相互(そうご)扶助(ふじょ)を目的(もくてき)とする法人(ほうじん)は適格(てきかく)消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)の対象(たいしょう)から除外(じょがい)すべきである」としているが(報告(ほうこく)書(しょ)11ページ),相互(そうご)扶助(ふじょ)団体(だんたい)でも,
生活協同組合(せいかつきょうどうくみあい)のように,消費(しょうひ)者(しゃ)の権利(けんり)擁護(ようご)活動(かつどう)に果(は)たしてきた実質(じっしつ)的(てき)役割(やくわり)や規模(きぼ)に照(て)らして消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)の利益(りえき)擁護(ようご)活動(かつどう)を行(おこな)っているといえる団体(だんたい)については適格(てきかく)性(せい)を認(みと)めるべきである。
(3)同(どう)「活動(かつどう)実績(じっせき)」について
報告(ほうこく)書(しょ)が,適格(てきかく)性(せい)の判断(はんだん)に際(さい)して,適格(てきかく)団体(だんたい)に一定(いってい)の活動(かつどう)実績(じっせき)を要求(ようきゅう)すること(報告(ほうこく)書(しょ)12ページ)は,妥当(だとう)である。期間(きかん)としては,1年(ねん)程度(ていど)の活動(かつどう)期間(きかん)を要求(ようきゅう)すべきである。
なお,既存(きそん)団体(だんたい)が構成(こうせい)員(いん)となって新(あら)たな団体(だんたい)を結成(けっせい)する場合(ばあい),活動(かつどう)実績(じっせき)は既存(きそん)団体(だんたい)の活動(かつどう)を考慮(こうりょ)すべきである。
(4)同(どう)「団体(だんたい)の規模(きぼ)」について
報告(ほうこく)書(しょ)は,「団体(だんたい)の規模(きぼ)」(報告(ほうこく)書(しょ)12~13ページ)については,消費(しょうひ)者(しゃ)利益(りえき)代表(だいひょう)制(せい)や訴権(そけん)行使(こうし)基盤(きばん)の判断(はんだん)基準(きじゅん)の一(ひと)つであるとし,当該(とうがい)団体(だんたい)の構成(こうせい)員数(いんずう)の規模(きぼ)でなく,
人材(じんざい)の確保(かくほ),情報(じょうほう)収集(しゅうしゅう)・分析(ぶんせき)体制(たいせい),独自(どくじ)の事務(じむ)局(きょく)といった体制(たいせい)面(めん)や当該(とうがい)団体(だんたい)の行(おこな)っている事業(じぎょう)活動(かつどう)の内容(ないよう)が重要(じゅうよう)な指標(しひょう)となるとしている。
こうした考(かんが)え方(かた)は,形式(けいしき)的(てき)な人数(にんずう)要件(ようけん)よりもその実質(じっしつ)を重視(じゅうし)するものであり,十(じゅう)分(ふん)ありうると考(かんが)えられる。
ただ,人数(にんずう)要件(ようけん)を設(もう)けることで適格(てきかく)団体(だんたい)の要件(ようけん)が明確(めいかく)になる面(めん)もあり,
人数(にんずう)要件(ようけん)を設(もう)けるとすれば,本(ほん)制度(せいど)が積極(せっきょく)的(てき)に訴権(そけん)を行使(こうし)しようとする消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)に訴権(そけん)を認(みと)めることによって公正(こうせい)な消費(しょうひ)者(しゃ)取引(とりひき)の実現(じつげん)を図(はか)ることを目的(もくてき)としていること,
そのためには,団体(だんたい)の規模(きぼ)の要件(ようけん)をあまり高(たか)く設定(せってい)することは妥当(だとう)ではないこと,濫(らん)訴(そ)の弊害(へいがい)(もっとも差(さ)止(とめ)請求(せいきゅう)訴訟(そしょう)は消費(しょうひ)者(しゃ)全体(ぜんたい)の利益(りえき)のために提起(ていき)されるものであり,
経済(けいざい)的(てき)見返(みかえ)りを伴(ともな)うものではないので濫(らん)訴(そ)のおそれは少(すく)ない)を防止(ぼうし)することなども考慮(こうりょ)して,
当会(とうかい)では,本年(ほんねん)4月(しがつ)意見(いけん)書(しょ)で述(の)べたとおり,100名(めい)以上(いじょう)の構成(こうせい)員(いん)を有(ゆう)していることを要件(ようけん)とすべきであると考(かんが)える。
(5)同(どう)「事業(じぎょう)者(しゃ)等からの独立(どくりつ)性(せい)」について
報告(ほうこく)書(しょ)は,特定(とくてい)の事業(じぎょう)者(しゃ)の関係(かんけい)者(しゃ)ないし同一(どういつ)業界(ぎょうかい)関係(かんけい)者(しゃ)が意思(いし)決定(けってい)機関(きかん)の構成(こうせい)員(いん)の一定(いってい)割合(わりあい)以上(いじょう)を占(し)めないことが求(もと)められるとしている(報告(ほうこく)書(しょ)13ページ)。
当会(とうかい)は,営利(えいり)団体(だんたい)からの独立(どくりつ)性(せい)を要件(ようけん)とすることには賛成(さんせい)である。
しかし,営利(えいり)を目的(もくてき)とする事業(じぎょう)者(しゃ)等(会社(かいしゃ)等(とう))の他(ほか)に非(ひ)営利(えいり)の事業(じぎょう)者(しゃ)等(とう)(NPO法人(ほうじん),公益(こうえき)法人(ほうじん),弁護士(べんごし),医師(いし)など)からの影響(えいきょう)も排除(はいじょ)されるべきか否(いな)かは問題(もんだい)である。
確(たし)かに,これらの者(もの)は消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)上(じょう)はすべて事業(じぎょう)者(しゃ)とされているが,これは消費(しょうひ)者(しゃ)取引(とりひき)における消費(しょうひ)者(しゃ)の利益(りえき)擁護(ようご)の観点(かんてん)から規定(きてい)されたものであり,本(ほん)制度(せいど)においてそのまま妥当(だとう)するものではない。
しかも,消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)上(じょう)の事業(じぎょう)者(しゃ)であっても,自然(しぜん)人(じん)は一(いち)面(めん)消費(しょうひ)者(しゃ)であって,これを排除(はいじょ)することは消費(しょうひ)者(しゃ)問題(もんだい)に取(と)り組(く)みたいという自然(しぜん)人(じん)のマンパワーの結集(けっしゅう)をことさら害(がい)する結果(けっか)となる。
さらに,消費(しょうひ)者(しゃ)契約(けいやく)法(ほう)上(じょう)の事業(じぎょう)者(しゃ)であっても当該(とうがい)事業(じぎょう)者(しゃ)が扱(あつか)う事業(じぎょう)とは別(べつ)の事業(じぎょう)分野(ぶんや)について不当(ふとう)な影響(えいきょう)を及(およ)ぼすことは考(かんが)えにくい。
以上(いじょう)からすれば,影響(えいきょう)を排除(はいじょ)すべき事業(じぎょう)者(しゃ)等は営利(えいり)団体(だんたい)のみとすべきである。
実質(じっしつ)的(てき)にも,本(ほん)制度(せいど)の実効(じっこう)性(せい)を確保(かくほ)するには,事業(じぎょう)者(しゃ)となりうる弁護士(べんごし)や司法(しほう)書士(しょし)などの専門(せんもん)家(か)が構成(こうせい)員(いん),役員(やくいん)となる必要(ひつよう)がある。
弊害(へいがい)は例外(れいがい)的(てき)と思(おも)われるが,弊害(へいがい)排除(はいじょ)のために,もっぱら競合(きょうごう)事業(じぎょう)者(しゃ)に対(たい)する打撃(だげき)を与(あた)えるために訴訟(そしょう)を提起(ていき)したと認(みと)められる場合(ばあい)には,権利(けんり)の濫用(らんよう)として請求(せいきゅう)を棄却(ききゃく)し,
特(とく)に利害(りがい)関係(かんけい)のある案件(あんけん)については組織(そしき)内(ない)の意思(いし)決定(けってい)において議決(ぎけつ)権(けん)を停止(ていし)すれば足(た)りる。
(6)同(どう)「組織(そしき)運営(うんえい)体制(たいせい),人(にん)的(てき)基盤(きばん),財政(ざいせい)基盤(きばん)」について
報告(ほうこく)書(しょ)では,適格(てきかく)団体(だんたい)の要件(ようけん)として,適切(てきせつ)な組織(そしき)運営(うんえい)体制(たいせい)や人(ひと)的(てき)基盤(きばん),財政(ざいせい)基盤(きばん)を備(そな)えていることが必要(ひつよう)であるとされているが(報告(ほうこく)書(しょ)14ページ),この考(かんが)え方(かた)自体(じたい)は妥当(だとう)である。
しかし,「組織(そしき)運営(うんえい)体制(たいせい)」に関(かん)して,報告(ほうこく)書(しょ)に情報(じょうほう)収集(しゅうしゅう)体制(たいせい),検討(けんとう)部門(ぶもん),独自(どくじ)の事務(じむ)局(きょく)の設置(せっち)等が挙(あ)げられ,
「人(ひと)的(てき)基盤(きばん)」に関(かん)して,消費(しょうひ)生活(せいかつ)相談(そうだん)員(いん),弁護士(べんごし),司法(しほう)書士(しょし)等の専門(せんもん)的(てき)知識(ちしき)や経験(けいけん)等を備(そな)えた人材(じんざい)を確保(かくほ)していることを求(もと)めていることについては反対(はんたい)である。
これらは,多(おお)くの消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)の実情(じつじょう)を無視(むし)した要件(ようけん)であり,現実(げんじつ)に即(そく)していない。あまりに厳格(げんかく)な適格(てきかく)団体(だんたい)の要件(ようけん)を求(もと)めることは,本(ほん)制度(せいど)の実効(じっこう)性(せい)を損(そこ)なう。
報告(ほうこく)書(しょ)は,適格(てきかく)団体(だんたい)に法人(ほうじん)格(かく)を求(もと)めており,適格(てきかく)団体(だんたい)になるためには少(すく)なくともNPO法人(ほうじん)である必要(ひつよう)があるから,
組織(そしき)運営(うんえい)体制(たいせい)・人(にん)的(てき)基盤(きばん)に関(かん)してはNPO法人(ほうじん)の要件(ようけん)を満(み)たす程度(ていど)のものであれば足(た)りるとすべきである。
(7)「適格(てきかく)要件(ようけん)への適合(てきごう)性(せい)判断(はんだん)の在(あ)り方(かた)」について
適合(てきごう)性(せい)の判断(はんだん)に関(かん)しては,消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)の適合(てきごう)性(せい)の判断(はんだん)をする際(さい),行政(ぎょうせい)の恣意(しい)が入(はい)ることのないような公正(こうせい)かつ透明(とうめい)な手続(てつづき)を確保(かくほ)すべきである。
報告(ほうこく)書(しょ)では,適合(てきごう)性(せい)判断(はんだん)にあたって第三者(だいさんしゃ)機関(きかん)を設置(せっち)することについては「その必要(ひつよう)性(せい)を含(ふく)め慎重(しんちょう)に検討(けんとう)すべきである」とされているが(報告(ほうこく)書(しょ)17ページ),
透明(とうめい)な手続(てつづき)とするためには第三者(だいさんしゃ)機関(きかん)を設置(せっち)するのが妥当(だとう)であるし,事業(じぎょう)者(しゃ)代表(だいひょう)も当該(とうがい)機関(きかん)の構成(こうせい)員(いん)として適合(てきごう)性(せい)判断(はんだん)に加(くわ)わることができるような方策(ほうさく)などにより,適格(てきかく)団体(だんたい)の実体(じったい)要件(ようけん)を徒(いたずら)に厳(きび)しくする必要(ひつよう)もなくなるというべきである。
(8)「事後(じご)的(てき)担保(たんぽ)措置(そち)」について
事後(じご)的(てき)担保(たんぽ)措置(そち)としての更新(こうしん)制度(せいど)(報告(ほうこく)書(しょ)18ページ)の更新(こうしん)期間(きかん)については,行政(ぎょうせい)への事業(じぎょう)報告(ほうこく)の制度(せいど),適合(てきごう)性(せい)判断(はんだん)の取消(とりけ)しの制度(せいど)等もあるので,あまりに短(みじか)い期間(きかん)である必要(ひつよう)はなく,5年(ねん)が妥当(だとう)である。
また,外部(がいぶ)監査(かんさ)については「慎重(しんちょう)に検討(けんとう)する必要(ひつよう)がある」とされているが(報告(ほうこく)書(しょ)18ページ),他(ほか)の法律(ほうりつ)で外部(がいぶ)監査(かんさ)が必要(ひつよう)とされている場合(ばあい)と本(ほん)制度(せいど)で想定(そうてい)される適格(てきかく)団体(だんたい)の規模(きぼ)は全(まった)く異(こと)なっており不要(ふよう)である。
また報告(ほうこく)書(しょ)では,競合(きょうごう)事業(じぎょう)者(しゃ)に対(たい)する妨害(ぼうがい)目的(もくてき)の訴(うった)え提起(ていき),不当(ふとう)な利益(りえき)を得(え)ることを目的(もくてき)とした差(さ)止(とめ)請求(せいきゅう)権(けん)の行使(こうし)等を防止(ぼうし)するために責務(せきむ)規定(きてい),行為(こうい)規範(きはん)が必要(ひつよう)とされているが(報告(ほうこく)書(しょ)19ページ),これらが許(ゆる)されない行為(こうい)であることは当然(とうぜん)のことであり,
わざわざ責務(せきむ)規定(きてい)等で規定(きてい)する必要(ひつよう)はない。責務(せきむ)規定(きてい),行為(こうい)規範(きはん)の内容(ないよう)は今後(こんご)の検討(けんとう)に委(ゆだ)ねられているが,その内容(ないよう)によっては不当(ふとう)に適格(てきかく)団体(だんたい)の活動(かつどう)を阻害(そがい)するおそれがあり,
責務(せきむ)規定(きてい),行為(こうい)規範(きはん)を設定(せってい)する必要(ひつよう)があるかどうかは,その内容(ないよう)ごとに慎重(しんちょう)に検討(けんとう)する必要(ひつよう)がある。
(9)「既判力(きはんりょく)の範囲(はんい)」について
報告(ほうこく)書(しょ)は,「既判力(きはんりょく)の範囲(はんい)」は,既判力(きはんりょく)が他(た)の団体(だんたい)に及(およ)ばないとするものであるが(報告(ほうこく)書(しょ)20~21ページ),民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)の基本(きほん)原則(げんそく)に整合(せいごう)的(てき)であり,
また,他(ほか)の団体(だんたい)が独自(どくじ)の観点(かんてん)から団体(だんたい)訴権(そけん)を行使(こうし)することを認(みと)める必要(ひつよう)があるから,基本(きほん)的(てき)に妥当(だとう)である。しかし,不適切(ふてきせつ)な訴(うった)えの提起(ていき)自体(じたい)を認(みと)めない仕組(しく)みの導入(どうにゅう)(報告(ほうこく)書(しょ)21ページ)については,後記(こうき)のとおり反対(はんたい)である。
(10)「同時(どうじ)複数(ふくすう)提訴(ていそ)の可否(かひ)」について
報告(ほうこく)書(しょ)では,同時(どうじ)複数(ふくすう)提訴(ていそ)は制限(せいげん)されないとされており(報告(ほうこく)書(しょ)21ページ),基本(きほん)的(てき)に妥当(だとう)である。
ここでも,一定(いってい)の不適切(ふてきせつ)な訴(うった)えの提起(ていき)自体(じたい)を認(みと)めない仕組(しく)みの導入(どうにゅう)が言及(げんきゅう)されているが(報告(ほうこく)書(しょ)21ページ),これについては後記(こうき)のとおり反対(はんたい)である。
なお,不適切(ふてきせつ)な同時(どうじ)複数(ふくすう)提訴(ていそ)については,移送(いそう),併合(へいごう)の制度(せいど)で対応(たいおう)すべきである。
(11)「判決(はんけつ)の周知(しゅうち)・公表(こうひょう)」について
「判決(はんけつ)の周知(しゅうち)・公表(こうひょう)」(報告(ほうこく)書(しょ)22ページ)については,事業(じぎょう)者(しゃ)の費用(ひよう)による判決(はんけつ)の公表(こうひょう)制度(せいど)も創設(そうせつ)されるべきである。
また,裁判所(さいばんしょ)から国民(こくみん)生活(せいかつ)センターへ訴訟(そしょう)の提起(ていき)・和解(わかい)・判決(はんけつ)の内容(ないよう)が通知(つうち)され,国民(こくみん)生活(せいかつ)センターが事業(じぎょう)者(しゃ)や消費(しょうひ)者(しゃ)・消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)からの照会(しょうかい)に回答(かいとう)する制度(せいど)が創設(そうせつ)されるべきである。
(12)「判決(はんけつ)の援用(えんよう)制度(せいど)」について
報告(ほうこく)書(しょ)では,いわゆる援用(えんよう)制度(せいど)の導入(どうにゅう)につき,「慎重(しんちょう)な検討(けんとう)が必要(ひつよう)」とされている(報告(ほうこく)書(しょ)23ページ)。しかし,消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)を設(もう)ける趣旨(しゅし)は,
個々(ここ)の消費(しょうひ)者(しゃ)と事業(じぎょう)者(しゃ)との訴訟(そしょう)遂行(すいこう)能力(のうりょく)に格段(かくだん)の差(さ)があることも大(おお)きな理由(りゆう)であり,
「当該(とうがい)不当(ふとう)行為(こうい)が違法(いほう)である」との裁判所(さいばんしょ)の判断(はんだん)につき,個々(ここ)の消費(しょうひ)者(しゃ)が訴訟(そしょう)上(じょう)で援用(えんよう)すれば,
その訴訟(そしょう)においても効果(こうか)が及(およ)ぶとすることは,より本(ほん)制度(せいど)を実効(じっこう)あらしめるものであって,導入(どうにゅう)が検討(けんとう)されるべきである。これは,ドイツ等において既(すで)に制度(せいど)化(か)されているものでもある。
(13)「事業(じぎょう)者(しゃ)との事前(じぜん)交渉(こうしょう)」について
報告(ほうこく)書(しょ)では,事業(じぎょう)者(しゃ)との訴訟(そしょう)前(まえ)の事前(じぜん)交渉(こうしょう)に関(かん)し「通知(つうち)」は必要(ひつよう)とされているが(報告(ほうこく)書(しょ)23~24ページ),
事業(じぎょう)者(しゃ)が通知(つうち)を受領(じゅりょう)しない時(とき)のことを考(かんが)えると不要(ふよう)とすべきである。もし通知(つうち)を要件(ようけん)とする場合(ばあい)には,事業(じぎょう)者(しゃ)が通知(つうち)を受領(じゅりょう)しなかった場合(ばあい)の手当(てあて)が必要(ひつよう)である。
(14)「不適切(ふてきせつ)な訴(うった)えの提起(ていき)に対(たい)する措置(そち)」について
報告(ほうこく)書(しょ)は,「不当(ふとう)な目的(もくてき)でなされる訴(うった)えについては,その提起(ていき)自体(じたい)を認(みと)めない仕組(しく)みとする必要(ひつよう)がある」とし(報告(ほうこく)書(しょ)25ページ),訴(うった)えの却下(きゃっか)制度(せいど)の導入(どうにゅう)の必要(ひつよう)性(せい)を認(みと)めるかのようである(この点(てん),報告(ほうこく)書(しょ)は,
民事(みんじ)訴訟(そしょう)法(ほう)上(じょう)極(きわ)めて特異(とくい)な制度(せいど)であるにもかかわらず,具体(ぐたい)的(てき)な仕組(しく)みを明(あき)らかにしていない)。しかし,この点(てん)に関(かん)しては反対(はんたい)である。
本(ほん)制度(せいど)においては,提訴(ていそ)できる適格(てきかく)団体(だんたい)の要件(ようけん)を定(さだ)めているが,これはもともと不当(ふとう)な目的(もくてき)での訴(うった)えの提起(ていき)のおそれという弊害(へいがい)排除(はいじょ)の視点(してん)も検討(けんとう)され要件(ようけん)化(か)されたものである。そのなかには一定(いってい)の活動(かつどう)実績(じっせき),
事業(じぎょう)者(しゃ)等からの独立(どくりつ)性(せい),反(はん)社会(しゃかい)的(てき)存在(そんざい)等の排除(はいじょ)の措置(そち)や,行政(ぎょうせい)がこれを事前(じぜん)に審査(しんさ)すること,
事後(じご)的(てき)担保(たんぽ)措置(そち)のうち更新(こうしん)制(せい),行政(ぎょうせい)への事業(じぎょう)報告(ほうこく),行政(ぎょうせい)が行(おこな)う必要(ひつよう)な措置(そち)(報告(ほうこく)徴収(ちょうしゅう),立入検査(たちいりけんさ),
改善(かいぜん)命令(めいれい),適合(てきごう)性(せい)判断(はんだん)の取消(とりけ)し等)等の不適切(ふてきせつ)な訴(うった)えの提起(ていき)の抑制(よくせい)措置(そち)があり,これらによって十分(じゅうぶん)抑制(よくせい)されると考(かんが)えられる。
従(したが)って,不適切(ふてきせつ)な訴(うった)えの提起(ていき)に対(たい)する措置(そち)は,屋上(おくじょう)屋(や)を重(かさ)ねるものであり不要(ふよう)である。
もし,これが採用(さいよう)されるならば,訴(うった)え却下(きゃっか)の制度(せいど)自体(じたい)が濫用(らんよう)され訴訟(そしょう)遅延(ちえん)につながるおそれが強(つよ)い。
また,不当(ふとう)な目的(もくてき)を認定(にんてい)しようとすれば,結局(けっきょく)は訴訟(そしょう)の内容(ないよう)を審理(しんり)することが多(おお)いと考(かんが)えられ,
その場合(ばあい),一般(いっぱん)法理(ほうり)で請求(せいきゅう)棄却(ききゃく)を求(もと)める場合(ばあい)とそれほど差異(さい)があるとは考(かんが)えられず,また一見(いっけん)明白(めいはく)に不適切(ふてきせつ)な訴(うった)えであれば,通常(つうじょう)手続(てつづき)でも本案(ほんあん)の審理(しんり)のなかで,
速(すみ)やかに棄却(ききゃく)されるはずである。いずれにしても,このような制度(せいど)を設(もう)ける必要(ひつよう)性(せい)はない。
なお,報告(ほうこく)書(しょ)では,担保(たんぽ)提供(ていきょう)制度(せいど)についても言及(げんきゅう)があるが(報告(ほうこく)書(しょ)25ページ),濫(らん)訴(そ)のおそれは上記(じょうき)の抑制(よくせい)措置(そち)で抑制(よくせい)しうると考(かんが)えられるため不要(ふよう)である。
(15)「制度(せいど)の実効(じっこう)性(せい)を高(たか)めるための方策(ほうさく)」について
(1)「適格(てきかく)消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)の自主(じしゅ)的(てき)な取組(とりく)みの重要(じゅうよう)性(せい)」について
報告(ほうこく)書(しょ)では,「制度(せいど)の実効(じっこう)性(せい)を高(たか)めるための方策(ほうさく)」として,「適格(てきかく)消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)の自主(じしゅ)的(てき)な取組(とりく)みの重要(じゅうよう)性(せい)」を述(の)べるが(報告(ほうこく)書(しょ)25ページ),本(ほん)制度(せいど)が公益(こうえき)的(てき)な性格(せいかく)を有(ゆう)することから,まず第(だい)一(いち)に,環境(かんきょう)整備(せいび)が考(かんが)えられるべきである。
(2)「環境(かんきょう)整備(せいび)の方向(ほうこう)性(せい)」について
報告(ほうこく)書(しょ)は,「情報(じょうほう)面(めん)における環境(かんきょう)整備(せいび)」として,地方自治体(ちほうじちたい)の消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターや国民(こくみん)生活(せいかつ)センターの保有(ほゆう)する消費(しょうひ)生活(せいかつ)相談(そうだん)情報(じょうほう)を適格(てきかく)消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)に提供(ていきょう)することが提案(ていあん)されている(報告(ほうこく)書(しょ)26ページ)が,妥当(だとう)である。
これらの情報(じょうほう)は,被害(ひがい)実態(じったい)の把握(はあく)や立証(りっしょう),特(とく)に不当(ふとう)勧誘(かんゆう)行為(こうい)の把握(はあく)や立証(りっしょう)に不可欠(ふかけつ)であり,相談(そうだん)内容(ないよう)を活用(かつよう)できる形(かたち)で提供(ていきょう)されるよう法律(ほうりつ)に規定(きてい)する必要(ひつよう)がある。
また,「人材(じんざい)面(めん)における環境(かんきょう)整備(せいび)」では,国民(こくみん)生活(せいかつ)センターの研修(けんしゅう)が挙(あ)げられているのみであるが(報告(ほうこく)書(しょ)27ページ),弁護士(べんごし)会(かい)が団体(だんたい)訴訟(そしょう)を受任(じゅにん)する弁護士(べんごし)の名簿(めいぼ)を準備(じゅんび)する等弁護士(べんごし)会(かい)との連携(れんけい)などの諸(しょ)策(さく)も考(かんが)えられるべきである。
さらに「資金(しきん)面(めん)における環境(かんきょう)整備(せいび)」では,行政(ぎょうせい)として資金(しきん)面(めん)の援助(えんじょ)としては実質(じっしつ)的(てき)に何(なに)もしないとされているが(報告(ほうこく)書(しょ)27ページ),
本(ほん)制度(せいど)の公益(こうえき)的(てき)性格(せいかく)に鑑(かんが)み,適格(てきかく)団体(だんたい)への補助(ほじょ)金(きん)が考(かんが)えられるべきである。
その他(た),当会(とうかい)が2004年(ねん)意見(いけん)書(しょ)で提言(ていげん)している,弁護士(べんごし)費用(ひよう)の片面(かためん)的(てき)敗訴(はいそ)者(しゃ)負担(ふたん),法律(ほうりつ)扶助(ふじょ)制度(せいど)・訴訟(そしょう)援助(えんじょ)制度(せいど)の拡充(かくじゅう),理論(りろん)的(てき)検討(けんとう)の支援(しえん)体制(たいせい),
各地(かくち)の消費(しょうひ)生活(せいかつ)センターの相談(そうだん)業務(ぎょうむ)の拡充(かくじゅう),消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)間(かん)の情報(じょうほう)を相互(そうご)につなぐ全国(ぜんこく)的(てき)なネットワークの構築(こうちく)などが認(みと)められるべきである。
7 おわりに
消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)は,来年(らいねん)通常(つうじょう)国会(こっかい)への法案(ほうあん)提出(ていしゅつ)に向(む)けて,より具体(ぐたい)的(てき)な法案(ほうあん)検討(けんとう)の段階(だんかい)に入(はい)る。
報告(ほうこく)書(しょ)で示(しめ)された消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)訴訟(そしょう)制度(せいど)は,その導入(どうにゅう)は画期的(かっきてき)であるが,裁判(さいばん)管轄(かんかつ)など内容(ないよう)によっては本(ほん)制度(せいど)が有効(ゆうこう)に活用(かつよう)されなくなるおそれがあるものである。
今後(こんご)の法案(ほうあん)検討(けんとう)においては,真(しん)に,消費(しょうひ)者(しゃ)団体(だんたい)が実効(じっこう)的(てき)に事業(じぎょう)者(しゃ)の不当(ふとう)行為(こうい)を差(さ)し止(と)めることができるよう,
内閣(ないかく)府(ふ)国民(こくみん)生活(せいかつ)局(きょく),政府(せいふ),各(かく)政党(せいとう)において,精力(せいりょく)的(てき)な取(と)り組(く)みがなされるよう強(つよ)く求(もと)めるものである。
以上(いじょう)
判例(はんれい) 平成(へいせい)17年(ねん)09月(くがつ)13日(にち) 第(だい)三(さん)小(しょう)法廷(ほうてい)判決(はんけつ) 平成(へいせい)14年(ねん)(行(ぎょう)ヒ)第(だい)72号(ごう) 審決(しんけつ)取消(とりけし)請求(せいきゅう)事件(じけん)
要旨(ようし)
私的(してき)独占(どくせん)の禁止(きんし)及(およ)び公正(こうせい)取引(とりひき)の確保(かくほ)に関(かん)する法律(ほうりつ)(平成(へいせい)9年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)87号(ごう)による改正(かいせい)前(まえ)のもの)7条(じょう)の2第(だい)1項(こう)所定(しょてい)の売上(うりあげ)額(がく)は事業(じぎょう)者(しゃ)の事業(じぎょう)活動(かつどう)から生(しょう)ずる収益(しゅうえき)から費用(ひよう)を差(さ)し引(ひ)
く前(まえ)の数値(すうち)をいう
内容(ないよう)
件名(けんめい): 審決(しんけつ)取消(とりけし)請求(せいきゅう)事件(じけん) (最高裁判所(さいこうさいばんしょ) 平成(へいせい)14年(ねん)(行(ぎょう)ヒ)第(だい)72号(ごう) 平成(へいせい)17年(ねん)09月(くがつ)13日(にち) 第(だい)三(さん)小(しょう)法廷(ほうてい)判決(はんけつ) 破棄(はき)自(じ)判(はん))
原審(げんしん): 東京(とうきょう)高等裁判所(こうとうさいばんしょ) (平成(へいせい)12年(ねん)(行(ぎょう)ケ)第(だい)228号(ごう)、233号(ごう))
主文(しゅぶん)
原(げん)判決(はんけつ)のうち上告(じょうこく)人(じん)の敗訴(はいそ)部分(ぶぶん)を破棄(はき)する。
前項(ぜんこう)の部分(ぶぶん)につき,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らの請求(せいきゅう)をいずれも棄却(ききゃく)する。
訴訟(そしょう)の総(そう)費用(ひよう)は被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らの負担(ふたん)とする。
理由(りゆう)
上告(じょうこく)代理人(だいりにん)鈴木(すずき)亨(とおる)ほかの上告(じょうこく)受理(じゅり)申立(もうしたて)て理由(りゆう)について
1 本件(ほんけん)は,私的(してき)独占(どくせん)の禁止(きんし)及(およ)び公正(こうせい)取引(とりひき)の確保(かくほ)に関(かん)する法律(ほうりつ)(平成(へいせい)9年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)87号(ごう)による改正(かいせい)前(まえ)のもの。
以下(いか)「独禁法(どっきんほう)」という。)8条(じょう)1項(こう)1号(ごう)の規定(きてい)に違反(いはん)する営業(えいぎょう)保険(ほけん)料率(りょうりつ)に関(かん)するカルテル行為(こうい)がされたとして,
公正(こうせい)取引(とりひき)委員(いいん)会(かい)平成(へいせい)10年(ねん)(判(はん))第(だい)4ないし第(だい)24号(ごう)課徴(かちょう)金(きん)納付(のうふ)命令(めいれい)審判(しんぱん)事件(じけん)において
上告(じょうこく)人(じん)が被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らに対(たい)しそれぞれ平成(へいせい)12年(ねん)6月(ろくがつ)2日(にち)付(づ)けでした各(かく)審決(しんけつ)(以下(いか)「本件(ほんけん)審決(しんけつ)」という。)について,
被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らが上告(じょうこく)人(じん)に対(たい)し,本件(ほんけん)審決(しんけつ)のうち原(げん)判決(はんけつ)別表(べっぴょう)3の「原告(げんこく)ら主張(しゅちょう)の課徴(かちょう)金額(きんがく)(1)」欄(らん)記載(きさい)の金額(きんがく)又(また)は「原告(げんこく)ら主張(しゅちょう)の課徴(かちょう)金額(きんがく)(2)」欄(らん)記載(きさい)の金額(きんがく)を超(こ)えて課徴(かちょう)金(きん)の納付(のうふ)を命(めい)ずる部分(ぶぶん)の取消(とりけ)しを請求(せいきゅう)した事案(じあん)である。
2 原審(げんしん)の適法(てきほう)に確定(かくてい)した事実(じじつ)関係(かんけい)等の概要(がいよう)は,次(つぎ)のとおりである。
(1) 独禁法(どっきんほう)8条(じょう)の3において準用(じゅんよう)する独禁法(どっきんほう)7条(じょう)の2の規定(きてい)によると,独禁法(どっきんほう)2条(じょう)2項(こう)にいう事業(じぎょう)者(しゃ)団体(だんたい)が一定(いってい)の取引(とりひき)分野(ぶんや)における競争(きょうそう)を実質(じっしつ)的(てき)に制限(せいげん)し,それが商品(しょうひん)又(また)は役務(えきむ)の対価(たいか)に係(かか)るものであるときは,
公正(こうせい)取引(とりひき)委員(いいん)会(かい)は,事業(じぎょう)者(しゃ)団体(だんたい)の構成(こうせい)事業(じぎょう)者(しゃ)に対(たい)し,実行(じっこう)期間(きかん)における当該(とうがい)商品(しょうひん)又(また)は役務(えきむ)の政令(せいれい)で定(さだ)める方法(ほうほう)により算定(さんてい)した売上(うりあげ)額(がく)に100分(ぶん)の6等の所定(しょてい)の割合(わりあい)を乗(じょう)じて得(え)た額(がく)に相当(そうとう)する額(がく)の課徴(かちょう)金(きん)を国庫(こっこ)に納付(のうふ)することを命(めい)じなければならない。
そして,私的(してき)独占(どくせん)の禁止(きんし)及(およ)び公正(こうせい)取引(とりひき)の確保(かくほ)に関(かん)する法律(ほうりつ)施行(しこう)令(れい)(以下(いか)「独禁法(どっきんほう)施行(しこう)令(れい)」という。)5条(じょう)は,売上(うりあげ)額(がく)の算定(さんてい)の方法(ほうほう)は,
カルテルの実行(じっこう)期間(きかん)において引(ひ)き渡(わた)した商品(しょうひん)又(また)は提供(ていきょう)した役務(えきむ)の対価(たいか)の額(がく)を合計(ごうけい)する方法(ほうほう)とすると定(さだ)めている。
(2) 機械(きかい)保険(ほけん)事業(じぎょう)の免許(めんきょ)を受(う)けた者(もの)を会員(かいいん)とし,独禁法(どっきんほう)2条(じょう)2項(こう)にいう事業(じぎょう)者(しゃ)団体(だんたい)に該当(がいとう)する日本(にっぽん)機械(きかい)保険(ほけん)連盟(れんめい)(以下(いか)「連盟(れんめい)」という。)は,
平成(へいせい)5年(ねん)3月(さんがつ)7日(にち)から同(どう)8年(ねん)3月(さんがつ)6日(にち)までの間(あいだ)(以下(いか)「本件(ほんけん)実行(じっこう)期間(きかん)」という。)において,
会員(かいいん)の損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)が機械(きかい)保険(ほけん)及(およ)び組立(くみたて)保険(ほけん)(以下(いか)「機械(きかい)保険(ほけん)等」という。)の引受(ひきう)けをする際(さい)の保険(ほけん)料率(りょうりつ)を連盟(れんめい)が決(き)める一定(いってい)の保険(ほけん)料率(りょうりつ)によることとさせた。
(3) 上告(じょうこく)人(じん)は,連盟(れんめい)の上記(じょうき)行為(こうい)が,機械(きかい)保険(ほけん)等の引受(ひきう)けの取引(とりひき)分野(ぶんや)における競争(きょうそう)を実質(じっしつ)的(てき)に制限(せいげん)し,独禁法(どっきんほう)8条(じょう)1項(こう)1号(ごう)の規定(きてい)に違反(いはん)する営業(えいぎょう)保険(ほけん)料率(りょうりつ)に関(かん)するカルテル行為(こうい)であるとして,連盟(れんめい)に対(たい)し,
平成(へいせい)9年(ねん)2月(にがつ)5日(にち)付(づ)けで独禁法(どっきんほう)48条(じょう)4項(こう)の規定(きてい)に基(もと)づく勧告(かんこく)審決(しんけつ)をし,さらに,独禁法(どっきんほう)8条(じょう)の3の規定(きてい)に基(もと)づき,連盟(れんめい)の会員(かいいん)である被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らに対(たい)し,
同(どう)12年(ねん)6月(ろくがつ)2日(にち)付(づ)けで総額(そうがく)54億(おく)4976万(まん)円(えん)の課徴(かちょう)金(きん)の納付(のうふ)を命(めい)ずる本件(ほんけん)審決(しんけつ)をした。
(4) 損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)が保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)から収受(しゅうじゅ)する保険(ほけん)料(りょう)は,一般(いっぱん)に営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)と呼(よ)ばれている。この営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)は,純(じゅん)保険(ほけん)料(りょう)と付加(ふか)保険(ほけん)料(りょう)とに分(わ)けられる。
純(じゅん)保険(ほけん)料(りょう)は,営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)のうち将来(しょうらい)の保険(ほけん)金(きん)の支払(しはらい)に充(あ)てられると見込(みこ)まれるもので,その額(がく)は,営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)に予定(よてい)損害(そんがい)率(りつ)を乗(じょう)じて得(え)られた額(がく)である。
また,付加(ふか)保険(ほけん)料(りょう)は,営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)のうち純(じゅん)保険(ほけん)料(りょう)以外(いがい)のもの,すなわち損害(そんがい)保険(ほけん)代理(だいり)店(てん)に支払(しはら)われる手数料(てすうりょう),損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)の経営(けいえい)に必要(ひつよう)な経費(けいひ)及(およ)び利潤(りじゅん)となるべきもので,
その額(がく)は,営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)に予定(よてい)事業(じぎょう)費(ひ)率(りつ)を乗(じょう)じて得(え)られた額(がく)である。
損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)の会計(かいけい)処理(しょり)上(じょう),収受(しゅうじゅ)した営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)は収益(しゅうえき)項目(こうもく)に計上(けいじょう)され,支払(しはら)った保険(ほけん)金(きん)は費用(ひよう)項目(こうもく)に計上(けいじょう)されている。
(5) 本件(ほんけん)審決(しんけつ)は,機械(きかい)保険(ほけん)等の引受(ひきう)けという役務(えきむ)の対価(たいか)は営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)の全額(ぜんがく)であるとして,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らが本件(ほんけん)実行(じっこう)期間(きかん)中(ちゅう)に収受(しゅうじゅ)した営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)を合計(ごうけい)した額(がく)を売上(うりあげ)額(がく)とし,
これに100分(ぶん)の6(ただし,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)大同火災海上保険(だいどうかさいかいじょうほけん)株式会社(かぶしきがいしゃ)については,独禁法(どっきんほう)7条(じょう)の2第(だい)2項(こう)の規定(きてい)により100分(ぶん)の3)を乗(じょう)じて得(え)た額(がく)の課徴(かちょう)金(きん)の納付(のうふ)を命(めい)じたものである。
(6) これに対(たい)し,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らは,本件(ほんけん)において課徴(かちょう)金(きん)の額(がく)を算定(さんてい)する基礎(きそ)となる役務(えきむ)の対価(たいか)は,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らが本件(ほんけん)実行(じっこう)期間(きかん)中(ちゅう)に収受(しゅうじゅ)した営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)の合計(ごうけい)額(がく)から純(じゅん)保険(ほけん)料(りょう)又(また)は
実際(じっさい)に保険(ほけん)金(きん)の支払(しはらい)に充(あ)てられた部分(ぶぶん)の額(がく)等を控除(こうじょ)した残額(ざんがく)であると主張(しゅちょう)して,本件(ほんけん)審決(しんけつ)の一部(いちぶ)取消(とりけ)しを請求(せいきゅう)した。
3 原審(げんしん)は,本件(ほんけん)審決(しんけつ)のうち原(げん)判決(はんけつ)別表(べっぴょう)4の「原告(げんこく)ら主張(しゅちょう)の支払(しはらい)保険(ほけん)金(きん)を控除(こうじょ)した場合(ばあい)の課徴(かちょう)金額(きんがく)」欄(らん)記載(きさい)の金額(きんがく)を超(こ)えて課徴(かちょう)金(きん)の納付(のうふ)を命(めい)ずる部分(ぶぶん)を取(と)り消(け)した。
原審(げんしん)の判断(はんだん)の要旨(ようし)は,次(つぎ)のとおりである。
(1) 課徴(かちょう)金(きん)制度(せいど)が制裁(せいさい)的(てき)色彩(しきさい)を伴(ともな)っているものであることは否定(ひてい)できないが,課徴(かちょう)金(きん)制度(せいど)の基本(きほん)的(てき)性格(せいかく)はあくまでもカルテルによる経済(けいざい)的(てき)利得(りとく)のはく奪(だつ)にあるから,
役務(えきむ)とその対価(たいか)を把握(はあく)するに当(あ)たっては,可能(かのう)な範囲(はんい)では課徴(かちょう)金(きん)の額(がく)が経済(けいざい)的(てき)に不当(ふとう)な利得(りとく)の額(がく)に近(ちか)づくような解釈(かいしゃく)を採(と)るべきである。
そして,当該(とうがい)役務(えきむ)の把握(はあく)に当(あ)たっては,まず当該(とうがい)事業(じぎょう)活動(かつどう)の経済(けいざい)的(てき)性質(せいしつ)や実態(じったい)の分析(ぶんせき)を行(おこな)う必要(ひつよう)がある。
(2) 保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)は,保険(ほけん)契約(けいやく)に基(もと)づき,損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)(保険(ほけん)者(しゃ))に対(たい)して,営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)を支払(しはら)う。損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)は,
多数(たすう)の保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)から営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)を集(あつ)め,その一部(いちぶ)(純(じゅん)保険(ほけん)料(りょう)部分(ぶぶん))から基金(ききん)を形成(けいせい)した上(うえ),
被(ひ)保険(ほけん)者(しゃ)の中(なか)で実際(じっさい)に事故(じこ)に遭遇(そうぐう)した者(もの)が現(あらわ)れた場合(ばあい)には,保険(ほけん)契約(けいやく)に基(もと)づき,同(どう)被(ひ)保険(ほけん)者(しゃ)に対(たい)し基金(ききん)から保険(ほけん)金(きん)を支払(しはら)う。
保険(ほけん)金(きん)の支払(しはらい)も,機械(きかい)保険(ほけん)等(とう)の引受(ひきう)けという役務(えきむ)の一部(いちぶ)を成(な)している。そうすると,営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)のうち保険(ほけん)金(きん)の支払(しはらい)に充(あ)てられた部分(ぶぶん)は,
保険(ほけん)団体(だんたい)を形成(けいせい)する多数(たすう)の保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)から集(あつ)められ,当初(とうしょ)の保険(ほけん)契約(けいやく)に基(もと)づき,
保険(ほけん)団体(だんたい)の構成(こうせい)員(いん)で事故(じこ)に遭遇(そうぐう)した保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)又(また)はその指定(してい)する被(ひ)保険(ほけん)者(しゃ)に還元(かんげん)されるもので,
経済(けいざい)的(てき)には保険(ほけん)団体(だんたい)内部(ないぶ)での資金(しきん)の移動(いどう)とみるべきものである。
そして,この資金(しきん)の移動(いどう)を円滑(えんかつ)適正(てきせい)に行(おこな)うということこそが,機械(きかい)保険(ほけん)等(とう)の引受(ひきう)けという損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)の役務(えきむ)の中心(ちゅうしん)となるものというべきである。
したがって,営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)のうち保険(ほけん)金(きん)の支払(しはらい)に充(あ)てられた部分(ぶぶん)は,基金(ききん)に留保(りゅうほ)され,保険(ほけん)団体(だんたい)内部(ないぶ)での資金(しきん)移動(いどう)に供(きょう)せられるだけのものであるから,
前記(ぜんき)役務(えきむ)に対(たい)する経済(けいざい)的(てき)な反対(はんたい)給付(きゅうふ),すなわち対価(たいか)とみることはできない。
保険(ほけん)団体(だんたい)を構成(こうせい)する多数(たすう)の保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)から資金(しきん)を集(あつ)めて基金(ききん)を形成(けいせい)し,
この基金(ききん)から保険(ほけん)団体(だんたい)の構成(こうせい)員(いん)で事故(じこ)に遭遇(そうぐう)した保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)(又(また)はその指定(してい)する被(ひ)保険(ほけん)者(しゃ))に保険(ほけん)金(きん)を支払(しはら)うという損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)の役務(えきむ)に対(たい)する対価(たいか)は,営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)から支払(しはらい)保険(ほけん)金(きん)の額(がく)を控除(こうじょ)した部分(ぶぶん)である。
4 しかしながら,原審(げんしん)の上記(じょうき)判断(はんだん)は是認(ぜにん)することができない。その理由(りゆう)は,次(つぎ)のとおりである。
(1) 独禁法(どっきんほう)の定(さだ)める課徴(かちょう)金(きん)の制度(せいど)は,昭和(しょうわ)52年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)63号(ごう)による独禁法(どっきんほう)改正(かいせい)において,カルテルの摘発(てきはつ)に伴(ともな)う不利益(ふりえき)を増大(ぞうだい)させてその経済(けいざい)的(てき)誘因(ゆういん)を小(ちい)さくし,カルテルの予防(よぼう)効果(こうか)を強化(きょうか)することを目的(もくてき)として,
既存(きそん)の刑事(けいじ)罰(ばつ)の定(さだ)め(独禁法(どっきんほう)89条(じょう))やカルテルによる損害(そんがい)を回復(かいふく)するための損害(そんがい)賠償(ばいしょう)制度(せいど)(独禁法(どっきんほう)25条(じょう))に加(くわ)えて設(もう)けられたものであり,
カルテル禁止(きんし)の実効(じっこう)性(せい)確保(かくほ)のための行政(ぎょうせい)上(じょう)の措置(そち)として機動(きどう)的(てき)に発動(はつどう)できるようにしたものである。
また,課徴(かちょう)金(きん)の額(がく)の算定(さんてい)方式(ほうしき)は,実行(じっこう)期間(きかん)のカルテル対象(たいしょう)商品(しょうひん)又(また)は役務(えきむ)の売上(うりあげ)額(がく)に一定(いってい)率(りつ)を乗(じょう)ずる方式(ほうしき)を採(と)っているが,
これは,課徴(かちょう)金(きん)制度(せいど)が行政(ぎょうせい)上(じょう)の措置(そち)であるため,算定(さんてい)基準(きじゅん)も明確(めいかく)なものであることが望(のぞ)ましく,
また,制度(せいど)の積極(せっきょく)的(てき)かつ効率(こうりつ)的(てき)な運営(うんえい)により抑止(よくし)効果(こうか)を確保(かくほ)するためには算定(さんてい)が容易(ようい)であることが必要(ひつよう)であるからであって,個々(ここ)の事案(じあん)ごとに経済(けいざい)的(てき)利益(りえき)を算定(さんてい)することは適切(てきせつ)ではないとして,そのような算定(さんてい)方式(ほうしき)が採用(さいよう)され,維持(いじ)されているものと解(かい)される。
そうすると,課徴(かちょう)金(きん)の額(がく)はカルテルによって実際(じっさい)に得(え)られた不当(ふとう)な利得(りとく)の額(がく)と一致(いっち)しなければならないものではないというべきである。
(2) 独禁法(どっきんほう)7条(じょう)の2は,課徴(かちょう)金(きん)の額(がく)について,当該(とうがい)商品(しょうひん)又(また)は役務(えきむ)の政令(せいれい)で定(さだ)める方法(ほうほう)により算定(さんてい)した売上(うりあげ)額(がく)に所定(しょてい)の割合(わりあい)を乗(じょう)じて得(え)た額(がく)に相当(そうとう)する額(がく)と定(さだ)めており,これを受(う)けて独禁法(どっきんほう)施行(しこう)令(れい)5条(じょう)は,
売上(うりあげ)額(がく)算定(さんてい)の方法(ほうほう)の原則(げんそく)をいわゆる引(ひ)き渡(わた)る基準(きじゅん)によることと定(さだ)め,実行(じっこう)期間(きかん)において引(ひ)き渡(わた)した商品(しょうひん)又(また)は提供(ていきょう)した役務(えきむ)の対価(たいか)の額(がく)を合計(ごうけい)する方法(ほうほう)によることとしているが,この合計(ごうけい)額(がく)から控除(こうじょ)すべきものとして,
①商品(しょうひん)の量目(りょうめ)不足(ふそく),品質(ひんしつ)不良(ふりょう)又(また)は破損(はそん),役務(えきむ)の不足(ふそく)又(また)は不良(ふりょう)その他(た)の事由(じゆう)により対価(たいか)の額(がく)の全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)の控除(こうじょ)があった場合(ばあい)におけるその控除(こうじょ)した額(がく),
②商品(しょうひん)の返品(へんぴん)があった場合(ばあい)におけるその返品(へんぴん)された商品(しょうひん)の対価(たいか)の額(がく),③相手方(あいてがた)に対(たい)し商品(しょうひん)の引渡(ひきわた)し又(また)は役務(えきむ)の提供(ていきょう)の実績(じっせき)に応(おう)じて割戻金(わりもどしきん)を支払(しはら)うべき旨(むね)が書面(しょめん)によって明(あき)らかな契約(けいやく)があった場合(ばあい)におけるその割戻金(わりもどしきん)の額(がく),という三(みっ)つの場合(ばあい)だけを明文(めいぶん)で掲(かか)げている。
そして,独禁法(どっきんほう)施行(しこう)令(れい)6条(じょう)は,引()渡(わたる)基準(きじゅん)によって売上(うりあげ)額(がく)を算定(さんてい)すると事業(じぎょう)活動(かつどう)の結果(けっか)と著(いちじる)しく離(はな)れてしまう場合(ばあい)に,例外(れいがい)としていわゆる契約(けいやく)基準(きじゅん)によることとし,
実行(じっこう)期間(きかん)において締結(ていけつ)した商品(しょうひん)の販売(はんばい)又(また)は役務(えきむ)の提供(ていきょう)に係(かか)る契約(けいやく)により定(さだ)められた対価(たいか)の額(がく)を合計(ごうけい)する方法(ほうほう)とすると定(さだ)め(1項(こう)),その場合(ばあい)の合計(ごうけい)額(がく)から控除(こうじょ)するものとして,
上記(じょうき)の③だけを準用(じゅんよう)している(2項(こう))。これらの施行(しこう)令(れい)の定(さだ)めは,いずれも,課徴(かちょう)金(きん)算定(さんてい)の基礎(きそ)となる売上(うりあげ)額(がく)の定(さだ)め方(かた)について,一般(いっぱん)に公正(こうせい)妥当(だとう)と認(みと)められる企業(きぎょう)会計(かいけい)原則(げんそく)上(じょう)の考(かんが)え方(かた)に準拠(じゅんきょ)して,
カルテルの実行(じっこう)期間(きかん)における対象(たいしょう)商品(しょうひん)又(また)は役務(えきむ)の純(じゅん)売上(うりあげ)額(がく)(総(そう)売上(うりあげ)額(がく)から値引(ねび)き,返品(へんぴん)及(およ)びリベート(割戻(わりもど)し)を控除(こうじょ)したもの)を算定(さんてい)する方法(ほうほう)によることとしているのである。
(3) また,課徴(かちょう)金(きん)の額(がく)を定(さだ)めるに当(あ)たって売上(うりあげ)額(がく)に乗(じょう)ずる比率(ひりつ)については,業種(ぎょうしゅ)ごとに一定(いってい)率(りつ)が法定(ほうてい)されているが,この一定(いってい)率(りつ)については,課徴(かちょう)金(きん)制度(せいど)に係(かか)る独禁法(どっきんほう)の規定(きてい)の立法(りっぽう)及(およ)び改正(かいせい)の過程(かてい)において,
売上(うりあげ)高(だか)を分母(ぶんぼ)とし,経常(けいじょう)利益(りえき)ないし営業(えいぎょう)利益(りえき)を分子(ぶんし)とする比率(ひりつ)を参考(さんこう)にして定(さだ)められているところ,企業(きぎょう)会計(かいけい)上(じょう)の概念(がいねん)である売上(うりあげ)高(だか)は,
個別(こべつ)の取引(とりひき)による実現(じつげん)収益(しゅうえき)として,事業(じぎょう)者(しゃ)が取引(とりひき)の相手方(あいてがた)から契約(けいやく)に基(もと)づいて受(う)け取(と)る対価(たいか)である代金(だいきん)ないし報酬(ほうしゅう)の合計(ごうけい)から費用(ひよう)項目(こうもく)を差(さ)し引(ひ)く前(まえ)の数値(すうち)であり,
課徴(かちょう)金(きん)の額(がく)を定(さだ)めるに当(あ)たって用(もち)いられる上記(じょうき)売上(うりあげ)額(がく)は,この売上(うりあげ)高(だか)と同義(どうぎ)のものというべきである。
(4) 他方(たほう),損害(そんがい)保険(ほけん)契約(けいやく)は,当事者(とうじしゃ)の一方(いっぽう)が偶然(ぐうぜん)な一定(いってい)の事故(じこ)によって生(しょう)ずることのあるべき損害(そんがい)をてん補(ほ)することを約(やく)し相手方(あいてがた)がこれにその報酬(ほうしゅう)を与(あた)えることを約(やく)することによってその効力(こうりょく)を生(しょう)ずるものであるから(商法(しょうほう)629条(じょう)参照(さんしょう)),
損害(そんがい)保険(ほけん)契約(けいやく)に基(もと)づいて保険(ほけん)者(しゃ)である損害(そんがい)保険(ほけん)会社(かいしゃ)が保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)に対(たい)して提供(ていきょう)する役務(えきむ)は,
偶然(ぐうぜん)な一定(いってい)の事故(じこ)によって生(しょう)ずることのあるべき損害(そんがい)をてん補(ほ)するという保険(ほけん)の引受(ひきう)けである。
(5) 以上(いじょう)によれば,独禁法(どっきんほう)7条(じょう)の2所定(しょてい)の売上(うりあげ)額(がく)の意義(いぎ)については,事業(じぎょう)者(しゃ)の事業(じぎょう)活動(かつどう)から生(しょう)ずる収益(しゅうえき)から費用(ひよう)を差(さ)し引(ひ)く前(まえ)の数値(すうち)を意味(いみ)すると解釈(かいしゃく)されるべきものであり,損害(そんがい)保険(ほけん)業(ぎょう)においては,
保険(ほけん)契約(けいやく)者(しゃ)に対(たい)して提供(ていきょう)される役務(えきむ)すなわち損害(そんがい)保険(ほけん)の引受(ひきう)けの対価(たいか)である営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)の合計(ごうけい)額(がく)が,独禁法(どっきんほう)8条(じょう)の3において準用(じゅんよう)する同(どう)法(ほう)7条(じょう)の2の規定(きてい)にいう売上(うりあげ)額(がく)であると解(かい)するのが相当(そうとう)である。
そうすると,上告(じょうこく)人(じん)が,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らが本件(ほんけん)実行(じっこう)期間(きかん)中(ちゅう)に収受(しゅうじゅ)した営業(えいぎょう)保険(ほけん)料(りょう)の合計(ごうけい)額(がく)を売上(うりあげ)額(がく)とし,
これに所定(しょてい)の割合(わりあい)を乗(じょう)じて得(え)られた額(がく)の課徴(かちょう)金(きん)の納付(のうふ)を被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らに命(めい)じた本件(ほんけん)審決(しんけつ)は,適法(てきほう)である。
5 以上(いじょう)のとおりであるから,本件(ほんけん)各(かく)請求(せいきゅう)を一部(いちぶ)認容(にんよう)すべきものとした原審(げんしん)の判断(はんだん)には,判決(はんけつ)に影響(えいきょう)を及(およ)ぼすことが明(あき)らかな法令(ほうれい)の違反(いはん)がある。論旨(ろんし)は,
理由(りゆう)があり,原(げん)判決(はんけつ)のうち上告(じょうこく)人(じん)の敗訴(はいそ)部分(ぶぶん)は破棄(はき)を免(まぬか)れない。そして,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)らの請求(せいきゅう)は,理由(りゆう)がないから,いずれも棄却(ききゃく)すべきである。
よって,裁判官(さいばんかん)全員(ぜんいん)一致(いっち)の意見(いけん)で,主文(しゅぶん)のとおり判決(はんけつ)する。
(裁判(さいばん)長(ちょう)裁判官(さいばんかん) 濱田(はまだ)邦夫(くにお) 裁判官(さいばんかん) 上田(うえだ)豊三(とよぞう) 裁判官(さいばんかん) 藤田(ふじた)宙(ちゅう)靖(やすし) 裁判官(さいばんかん) 堀籠(ほりごめ)幸男(ゆきお))
判例(はんれい) 平成(へいせい)17年(ねん)09月(くがつ)08日(にち) 第(だい)一(いち)小(しょう)法廷(ほうてい)判決(はんけつ) 平成(へいせい)16年(ねん)(受())第(だい)1222号(ごう) 預託(よたく)金(きん)返還(へんかん)請求(せいきゅう)事件(じけん)
要旨(ようし):
相続(そうぞく)開始(かいし)から遺産(いさん)分割(ぶんかつ)までの間(あいだ)に共同(きょうどう)相続(そうぞく)に係(かか)る不動産(ふどうさん)から生(しょう)ずる賃料(ちんりょう)債権(さいけん)は,各(かく)共同(きょうどう)相続(そうぞく)人(じん)がその相続(そうぞく)分(ぶん)に応(おう)じて分割(ぶんかつ)単独(たんどく)債権(さいけん)として確定(かくてい)的(てき)に取得(しゅとく)し,この賃料(ちんりょう)債権(さいけん)の帰属(きぞく)は,
後(ご)にされた遺産(いさん)分割(ぶんかつ)の影響(えいきょう)を受(う)けない
内容(ないよう)
件名(けんめい): 預託(よたく)金(きん)返還(へんかん)請求(せいきゅう)事件(じけん) (最高裁判所(さいこうさいばんしょ) 平成(へいせい)16年(ねん)(受())第(だい)1222号(ごう) 平成(へいせい)17年(ねん)09月(くがつ)08日(にち) 第(だい)一(いち)小(しょう)法廷(ほうてい)判決(はんけつ) 破棄(はき)差戻(さしもど)し)
原審(げんしん): 大阪(おおさか)高等裁判所(こうとうさいばんしょ) (平成(へいせい)15年(ねん)(ネ)第(だい)3264号(ごう))
主文(しゅぶん)
原(はら)判決(はんけつ)を破棄(はき)する。
本件(ほんけん)を大阪(おおさか)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)に差(さ)し戻(もど)す。
理由(りゆう)
上告(じょうこく)代理人(だいりにん)田中(たなか)英一(ひでかず),同(どう)永井(ながい)一弘(かずひろ)の上告(じょうこく)受理(じゅり)申立(もうしたて)て理由(りゆう)について
1 原審(げんしん)の確定(かくてい)した事実(じじつ)関係(かんけい)の概要(がいよう)は,次(つき)のとおりである。
(1) Aは,平成(へいせい)8年(ねん)10月(じゅうがつ)13日(にち),死亡(しぼう)した。その法定(ほうてい)相続(そうぞく)人(じん)は,妻(つま)である被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)のほか,子(こ)である上告(じょうこく)人(じん),B,C及(およ)びD(以下(いか),この4名(めい)を「上告(じょうこく)人(じん)ら」という。)である。
(2) Aの遺産(いさん)には,第(だい)1審判(しんぱん)決別(けつべつ)紙(し)遺産(いさん)目録(もくろく)1(1)~(17)記載(きさい)の不動産(ふどうさん)(以下(いか)「本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)」という。)がある。
(3) 被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)及(およ)び上告(じょうこく)人(じん)らは,本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)から生(しょう)ずる賃料(ちんりょう),管理(かんり)費(ひ)等について,遺産(いさん)分割(ぶんかつ)により本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)の帰属(きぞく)が確定(かくてい)した時点(じてん)で清算(せいさん)することとし,
それまでの期間(きかん)に支払(しはら)われる賃料(ちんりょう)等を管理(かんり)するための銀行(ぎんこう)口座(こうざ)(以下(いか)「本件(ほんけん)口座(こうざ)」という。)を開設(かいせつ)し,本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)の賃借(ちんしゃく)人(じん)らに賃料(ちんりょう)を本件(ほんけん)口座(こうざ)に振(ふ)り込(こ)ませ,また,その管理(かんり)費(ひ)等を本件(ほんけん)口座(こうざ)から支出(ししゅつ)してきた。
(4) 大阪(おおさか)高等裁判所(こうとうさいばんしょ)は,平成(へいせい)12年(ねん)2月(にがつ)2日(にち),同(どう)裁判所(さいばんしょ)平成(へいせい)11年(ねん)(ラ)第(だい)687号(ごう)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)及(およ)び寄与(きよ)分(ぶん)を定(さだ)める処分(しょぶん)審判(しんぱん)に対(たい)する抗告(こうこく)事件(じけん)において,
本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)につき遺産(いさん)分割(ぶんかつ)をする旨(むね)の決定(けってい)(以下(いか)「本件(ほんけん)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)決定(けってい)」という。)をし,本件(ほんけん)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)決定(けってい)は,翌(よく)3日(にち),確定(かくてい)した。
(5) 本件(ほんけん)口座(こうざ)の残金(ざんきん)の清算(せいさん)方法(ほうほう)について,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)と上告(じょうこく)人(じん)らとの間(あいだ)に紛争(ふんそう)が生(しょう)じ,
被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)は,本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)から生(しょう)じた賃料(ちんりょう)債権(さいけん)は,相続(そうぞく)開始(かいし)の時(とき)にさかのぼって,
本件(ほんけん)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)決定(けってい)により本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)を取得(しゅとく)した各(かく)相続(そうぞく)人(じん)にそれぞれ帰属(きぞく)するものとして分配(ぶんぱい)額(がく)を算定(さんてい)すべきであると主張(しゅちょう)し,上告(じょうこく)人(じん)らは,
本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)から生(しょう)じた賃料(ちんりょう)債権(さいけん)は,本件(ほんけん)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)決定(けってい)確定(かくてい)の日(ひ)までは法定(ほうてい)相続(そうぞく)分(ぶん)に従(したが)って各(かく)相続(そうぞく)人(じん)に帰属(きぞく)し,
本件(ほんけん)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)決定(けってい)確定(かくてい)の日(ひ)の翌日(よくじつ)から本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)を取得(しゅとく)した各(かく)相続(そうぞく)人(じん)に帰属(きぞく)するものとして分配(ぶんぱい)額(がく)を算定(さんてい)すべきであると主張(しゅちょう)した。
(6) 被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)と上告(じょうこく)人(じん)らは,本件(ほんけん)口座(こうざ)の残金(ざんきん)につき,各自(かくじ)が取得(しゅとく)することに争(あらそ)いのない金額(きんがく)の範囲(はんい)で分配(ぶんぱい)し,争(あらそ)いのある金員(きんいん)を上告(じょうこく)人(じん)が保管(ほかん)し(以下(いか),
この金員(きんいん)を「本件(ほんけん)保管(ほかん)金(きん)」という。),その帰属(きぞく)を訴訟(そしょう)で確定(かくてい)することを合意(ごうい)した。
2 本件(ほんけん)は,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)が,上告(じょうこく)人(じん)に対(たい)し,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)主張(しゅちょう)の計算(けいさん)方法(ほうほう)によれば,本件(ほんけん)保管(ほかん)金(きん)は被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)の取得(しゅとく)すべきものであると主張(しゅちょう)して,
上記(じょうき)合意(ごうい)に基(もと)づき,本件(ほんけん)保管(ほかん)金(きん)及(およ)びこれに対(たい)する訴状(そじょう)送達(そうたつ)の日(ひ)の翌日(よくじつ)である平成(へいせい)13年(ねん)6月(ろくがつ)2日(にち)から支払(しはらい)済(ず)みまで民法(みんぽう)所定(しょてい)の年(とし)5分(ふん)の割合(わりあい)による遅延(ちえん)損害(そんがい)金(きん)の支払(しはらい)を求(もと)めるものである。
3 原審(げんしん)は,上記(じょうき)事実(じじつ)関係(かんけい)の下(した)で,次(じ)のとおり判断(はんだん)し,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)の請求(せいきゅう)を認容(にんよう)すべきものとした。
遺産(いさん)から生(しょう)ずる法定(ほうてい)果実(かじつ)は,それ自体(じたい)は遺産(いさん)ではないが,遺産(いさん)の所有(しょゆう)権(けん)が帰属(きぞく)する者(もの)にその果実(かじつ)を取得(しゅとく)する権利(けんり)も帰属(きぞく)するのであるから,
遺産(いさん)分割(ぶんかつ)の効力(こうりょく)が相続(そうぞく)開始(かいし)の時(とき)にさかのぼる以上(いじょう),遺産(いさん)分割(ぶんかつ)によって特定(とくてい)の財産(ざいさん)を取得(しゅとく)した者(もの)は,
相続(そうぞく)開始(かいし)後(ご)に当該(とうがい)財産(ざいさん)から生(しょう)ずる法定(ほうてい)果実(かじつ)を取得(しゅとく)することができる。そうすると,本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)から生(しょう)じた賃料(ちんりょう)債権(さいけん)は,
相続(そうぞく)開始(かいし)の時(とき)にさかのぼって,本件(ほんけん)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)決定(けってい)により本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)を取得(しゅとく)した各(かく)相続(そうぞく)人(じん)にそれぞれ帰属(きぞく)するものとして,本件(ほんけん)口座(こうざ)の残金(ざんきん)を分配(ぶんぱい)すべきである。これによれば,本件(ほんけん)保管(ほかん)金(きん)は,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)が取得(しゅとく)すべきものである。
4 しかしながら,原審(げんしん)の上記(じょうき)判断(はんだん)は是認(ぜにん)することができない。その理由(りゆう)は,次(つぎ)のとおりである。
遺産(いさん)は,相続(そうぞく)人(じん)が数(すう)人(にん)あるときは,相続(そうぞく)開始(かいし)から遺産(いさん)分割(ぶんかつ)までの間(あいだ),共同(きょうどう)相続(そうぞく)人(じん)の共有(きょうゆう)に属(ぞく)するものであるから,この間(かん)に遺産(いさん)である賃貸(ちんたい)不動産(ふどうさん)を使用(しよう)管理(かんり)した結果(けっか)生(なま)ずる金銭(きんせん)債権(さいけん)たる賃料(ちんりょう)債権(さいけん)は,
遺産(いさん)とは別個(べっこ)の財産(ざいさん)というべきであって,各(かく)共同(きょうどう)相続(そうぞく)人(じん)がその相続(そうぞく)分(ぶん)に応(おう)じて分割(ぶんかつ)単独(たんどく)債権(さいけん)として確定(かくてい)的(てき)に取得(しゅとく)するものと解(かい)するのが相当(そうとう)である。遺産(いさん)分割(ぶんかつ)は,
相続(そうぞく)開始(かいし)の時(とき)にさかのぼってその効力(こうりょく)を生(しょう)ずるものであるが,各(かく)共同(きょうどう)相続(そうぞく)人(じん)がその相続(そうぞく)分(ぶん)に応(おう)じて分割(ぶんかつ)単独(たんどく)債権(さいけん)として確定(かくてい)的(てき)に取得(しゅとく)した上記(じょうき)賃料(ちんりょう)債権(さいけん)の帰属(きぞく)は,後(あと)にされた遺産(いさん)分割(ぶんかつ)の影響(えいきょう)を受(う)けないものというべきである。
したがって,相続(そうぞく)開始(かいし)から本件(ほんけん)遺産(いさん)分割(ぶんかつ)決定(けってい)が確定(かくてい)するまでの間(あいだ)に本件(ほんけん)各(かく)不動産(ふどうさん)から生(しょう)じた賃料(ちんりょう)債権(さいけん)は,
被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)及(およ)び上告(じょうこく)人(じん)らがその相続(そうぞく)分(ぶん)に応(おう)じて分割(ぶんかつ)単独(たんどく)債権(さいけん)として取得(しゅとく)したものであり,本件(ほんけん)口座(こうざ)の残金(ざんきん)は,これを前提(ぜんてい)として清算(せいさん)されるべきである。
そうすると,上記(じょうき)と異(こと)なる見解(けんかい)に立(た)って本件(ほんけん)口座(こうざ)の残金(ざんきん)の分配(ぶんぱい)額(がく)を算定(さんてい)し,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)が本件(ほんけん)保管(ほかん)金(きん)を取得(しゅとく)すべきであると判断(はんだん)して,被(ひ)上告(じょうこく)人(じん)の請求(せいきゅう)を認容(にんよう)すべきものとした原審(げんしん)の判断(はんだん)には,
判決(はんけつ)に影響(えいきょう)を及(およ)ぼすことが明(あき)らかな法令(ほうれい)の違反(いはん)がある。論旨(ろんし)は理由(りゆう)があり,原(げん)判決(はんけつ)は破棄(はき)を免(まぬか)れない。そして,本件(ほんけん)については,更(さら)に審理(しんり)を尽(つ)くさせる必要(ひつよう)があるから,本件(ほんけん)を原審(げんしん)に差(さ)し戻(もど)すこととする。
よって,裁判官(さいばんかん)全員(ぜんいん)一致(いっち)の意見(いけん)で,主文(しゅぶん)のとおり判決(はんけつ)する。
(裁判(さいばん)長(ちょう)裁判官(さいばんかん) 才(さい)口(ぐち)千晴(ちはる) 裁判官(さいばんかん) 横尾(よこお)和子(かずこ) 裁判官(さいばんかん) 甲斐(かい)中(ちゅう)辰夫(たつお) 裁判官(さいばんかん)
|